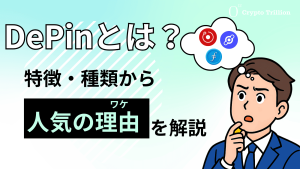DePIN(分散型物理インフラネットワーク)とは?仮想通貨の銘柄も含めわかりやすく解説!

プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- DePINとは現実世界のインフラをブロックチェーンを利用して向上させようというプロジェクトのこと
- インターネット上だけでなく、実際の物理設備の提供と運用に貢献することでも報酬を得られる
- 電波やネットワーク、ストレージ空間といったリアルな資源と直結するため、生活インフラに近い存在
- 通信インフラやクラウドストレージ、マップサービスといった実生活で欠かせない領域を扱うプロジェクトが多い
- Helium:小型ホットスポットでIoT無線を拡張し、貢献に応じてトークンを得る分散通信網プロジェクト
- Filecoin:IPFSを利用した分散ストレージで、保存証明によりFILを報酬として付与
- Hivemapper:車載映像から地図を更新し、貢献したドライバーにHONEYを配る分散マップ
- 物理的インフラを従来の大企業独占モデルから分散型のコミュニティ主導へと移行させる新しいムーブメント
- 大手IT企業や通信キャリアがDePINへ出資し、共同事業を模索するニュースが増えている
- HeliumはIoT向け無線網の実績をもとに、5G基地局の普及を積極的に進めている
 Trader Z
Trader Z従来、通信・エネルギー・輸送といった社会インフラは、大規模な中央集権的資本によって整備・管理されてまいりました。しかし、DePINの登場により、一般の個人や中小のプレイヤーが物理的なインフラ形成に参加し、その貢献に対してトークンで報酬を得ることが可能になるという新たな潮流が生まれています。



この構造は、まさに「物理世界におけるWeb3的アプローチ」であり、DeFiが金融領域を変えたのと同様のインパクトを、リアルなインフラの分野にもたらす可能性を秘めています。
たとえば、Helium Networkでは、個人が自宅に通信デバイスを設置し、ネットワーク構築に貢献することでトークンを獲得できる仕組みが既に運用されています。このように、中央集権的でない形での社会インフラ整備が現実のものとなりつつあるのです。


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
DePIN(分散型物理インフラネットワーク)とは
DePINの基本的な仕組み
DePINはブロックチェーン技術を使い、従来の中央集権型インフラをコミュニティで運営しようという考え方を指します。例えば通信なら、個人が専用アンテナを設置してネットワークを広げ、そこで発生した利用料がトークンとして参加者へ還元される仕組みです。
分散型の台帳によって情報を改ざんしにくい形で管理できるため、報酬配分や稼働状態のチェックが公正に行われやすい点がポイントになります。
高額な設備投資が必要だったインフラ事業を、多数の人が小口で担う形に置き換えられれば、今までサービスが届かなかった地域や規模の小さいコミュニティでもインフラを整備しやすくなるかもしれません。
従来のインフラモデルとの違い
従来のインフラは、大手キャリアや巨大クラウド事業者が大規模設備を所有し、利用者は固定的な料金を支払うのが通例でした。DePINは、ネットワークの参加者一人ひとりがノードを設置することでインフラを形成し、ブロックチェーン上のルールに沿って報酬が配分される構造をとります。
山間部や途上国でインターネットや電力が届きにくかった場所でも、個人が少額で機器を設置して繋いでいける点は魅力です。ただし、機器品質や法規制などのハードルがあり、一気に普及するには時間がかかる可能性もあります。
DePINが注目される4つの理由
リアルなインフラとブロックチェーンが結びつく新時代性
仮想通貨やトークンといえば、デジタル上でのやり取りが中心というイメージを抱く方が大半かもしれません。DePINでは、電波塔やストレージ装置などのリアルなハードウェアが稼働することで、実社会で役立つサービスを提供する形になります。
この仕組みを応用すれば、通信やデータ保存といった分野だけでなく、電力のP2P取引や農業センサーの共同利用など、インフラの概念を広げる動きが加速するかもしれません。単なる投機対象ではない、実益を感じられる暗号資産の出現が期待されているのです。
投資家やVCからの注目度が急上昇
暗号資産市場には常に新しいテーマが生まれますが、その中でも「リアルな問題解決につながるかどうか」が投資の判断材料となるケースが増えています。DePINは、通信やクラウドといった巨大市場に切り込み得るテーマです。
実際、すでに専用のDePIN投資ファンドが設立され、プロジェクトへ多額の資金が流れ始めています。機関投資家も「インフラは長期での需要が見込まれやすい」と考えており、技術リスクとリターンを天秤にかけながら参入を検討する動きが活発です。
参入障壁の低さとコミュニティ主導の運営
DePINプロジェクトでは、小型のアンテナやカメラ、ストレージ機器を設置するだけでネットワークを形成できる例が増えています。大手企業のように数百億円単位で設備投資を行うのではなく、地域や個人が少額でノードを追加していく形が基本です。
コミュニティ運営の場合、報酬設計やネットワーク拡大の方針がトークン保有者の投票などで決まります。オンラインフォーラムなどを通じて情報が共有されやすく、参入時の疑問点を解消しながらネットワークに加われる点が、初心者のハードルを下げている要因です。
収益性・実需の高さが期待できる
通信やストレージといった分野は、人々の日常生活や企業活動に不可欠です。こうした領域を分散型で賄うプロジェクトが成功すれば、利用者やデータ量の増加につれてノード運営者へのリターンが増えるかもしれません。
既存の大企業が提供するサービスより安価で柔軟な選択肢を提示できれば、ユーザーが拡大しやすくなるでしょう。ただし、市場環境の変化や技術的問題で期待通りの報酬を得にくい場面も考えられます。長期的視点とリスク管理が重要になりそうです。
DePINのメリットと課題
DePINがもたらすメリット
DePINの最大の利点は、特定の大企業だけが設備を独占するのではなく、多数の小規模プレイヤーがネットワークに参加できる点です。地域や途上国でも、小さなデバイスを設置して通信や電力を広める取り組みが登場しています。
ブロックチェーン上で稼働状況を証明し、その対価としてトークンを分配する仕組みが整えば、寄付や助成金に頼らなくても継続的にネットワークを運営しやすくなるかもしれません。結果として、多様なサービスや料金体系が誕生し、利用者にとっても選択の幅が広がることが期待されています。
DePINに残された課題
インフラ事業として実運用するには、法的・技術的な課題がつきまといます。地域によっては通信を提供するのに免許が要る場合もあり、周波数帯や電波法など既存の枠組みとどう調整するかが問題になりやすいです。
さらに、ネットワークが大きくなるほど品質管理が難しくなり、ノードの故障や不正を監視しきれないリスクが高まる可能性も指摘されています。暗号資産の価格下落時には、報酬が不十分になりノードを離脱する人が増える恐れもあるため、プロジェクトのインセンティブ設計がカギを握るでしょう。
DePIN代表的なプロジェクト事例
Helium(HNT)
Heliumは分散型通信プロジェクトの先駆けとして注目されています。個人宅や店舗にアンテナを置くことでIoT機器向けの電波を拡張し、その貢献度合いを独自アルゴリズムで測定してHNTトークンを発行する仕組みです。
最近は5Gネットワークへの対応を本格化し、モバイル通信分野にも乗り出す動きを見せています。既存キャリアとの併用を目指す地域が増え、都市部から郊外までカバーエリア拡大を狙う事例が増えています。
Filecoin(FIL)
Filecoinは、世界中の個人や企業が余っているストレージ空間をネットワークに提供し、ユーザーがデータを安全に保管できるプラットフォームを目指します。データが改ざんなく格納されているかを定期的にチェーン上でチェックし、問題なく稼働したノードがFILトークンを得る設計です。
FVM(Filecoin Virtual Machine)の登場で、データ管理やアクセス制御をスマートコントラクトで自動化する事例が増えてきました。クラウド大手との競争という課題もありますが、分散ならではの耐障害性や検閲耐性が評価されています。
Render Network(RNDR)
Render Networkは、高性能GPUを持つ参加者が計算処理を引き受け、トークンで報酬を得る仕組みを構築しています。映画制作やゲーム開発では膨大なレンダリング時間が必要になりますが、分散型ネットワークで多くのGPUを利用できれば大幅にコストと時間を抑えられるかもしれません。
今後、メタバースやAI分野へ応用が進むシナリオも語られており、GPUリソースの需要拡大が期待されている状況です。
Hivemapper(HONEY)
Hivemapperは、車載カメラの映像を活用し、地図情報を最新状態に保つプロジェクトです。Googleマップなど既存の中央集権型サービスと違い、誰でもデータ提供者として道路や建物の変化を反映できます。
運転中に撮影した映像をアップロードすると、人工知能が自動的に地図をアップデートし、その貢献に応じてHONEYトークンが付与される仕組みです。プライバシー問題やデータ整合性の確保などの課題があるものの、コミュニティ主導ならではの柔軟性が注目されています。
DePINの注目ニュース2025年版
Helium 5G対応の本格展開と提携ニュース
2025年、HeliumはIoT向け無線網の実績をもとに、5G基地局の普及を積極的に進めています。都市部や観光地での実証プロジェクトが複数立ち上がり、スマートフォンによるモバイルデータ通信まで視野に入れる段階に入りました。
ただし、5Gの周波数帯は国や地域によってライセンス管理されるケースが多く、法的な整備が追いついていないと指摘されることがあります。大手キャリアと競合する可能性があるため、長期的にどのように住み分けるかは注目点です。
Filecoinスマートコントラクト(FVM)の進展
FilecoinはFVM導入後、単なるストレージ提供にとどまらず、データのアクセス制御や収益化の仕組みをスマートコントラクトで実装する事例が増えてきました。
映像や研究データを共有するDAOが出現し、コミュニティ単位で管理費をまかなう試みも見られます。ただし、こうした高度な機能を実装するほどセキュリティリスクも高まり、ネットワーク全体での監査体制をどう整えるかが継続的なテーマとなりそうです。
その他注目トピック(規制や大手企業参入など)
大手IT企業や通信キャリアがDePINへ出資し、共同事業を模索するニュースが増えています。分散型ネットワークの強みを取り入れつつ、自社の設備や資金力を活用してハイブリッド型のインフラモデルを構築する狙いがあるようです。
一方で、電波法やエネルギー分野の規制が強い国では、ノード設置やトークン配布を制限する可能性も示唆されています。さらに、メタバース向けの高頻度データ通信やAIモデルの分散学習にDePINを活かす構想もあり、今後の展開が期待される一方、技術要件やコスト面の検討も欠かせません。
DePINとは?まとめ
DePINは、物理的インフラを従来の大企業独占モデルから分散型のコミュニティ主導へと移行させる新しいムーブメントとして注目されています。HeliumやFilecoinなど、すでに実用度や規模が拡大し始めている例も少なくありません。とはいえ、法整備や技術の成熟、相場変動への対処など、さまざまな課題が残るのも事実です。
それでも通信やストレージといった身近なインフラがブロックチェーンと結びつくことで、暗号資産はより実生活に根ざした存在へと進化する可能性があります。
国内取引所でDePIN関連銘柄を購入し、将来性を期待する投資スタイルも考えられますが、その際は十分な情報収集とリスク管理が重要になりそうです。当サロンでは、こうした新興トレンドの動向をいち早くキャッチし、コミュニティ間で情報を共有する仕組みを提供しています。
初心者からベテランまで、DePINに興味がある方はぜひ一度サロンを訪れ、トレード戦略や最新ニュースを通じて仮想通貨の世界を深く学んでみてください。インフラのあり方が変わる可能性を感じつつ、自分なりの投資スタイルを築けるきっかけになるかもしれません。