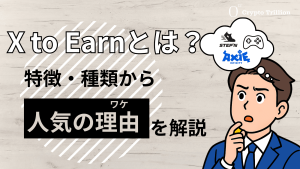仮想通貨の「X to Earn(X2E)」とは?基本的な仕組み/おすすめアプリなど解説!

プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- X to Earnとは自分の行動が仮想通貨やトークンとして還元される、新しい稼ぎ方や楽しみ方の総称
- 報酬のトークンは、ブロックチェーン上で発行されているため、各種取引所やマーケットで交換可能
- 初期費用の回収期間が長引いたり、想定を下回る形になったりするケースも珍しくない
- Play to Earn(P2E)、Move to Earn(M2E)、Learn to Earn(L2E)など代表的なジャンルが複数存在
- P2E:ゲームをプレイしてトークンを得る仕組みで、ゲーム内アイテムなどがNFTとして流通している
- M2E:「歩く」という生活の一部が暗号資産を稼ぐ手段になる
- L2E:暗号資産の取引所が提供するオンライン学習コースでクイズに答えるとトークンが付与される
- 歴史的にはPlay to Earnが火付け役で、Axie Infinityが「行動が収益化する」という概念を作った
- Move to EarnのSTEPNは、スマートフォンのGPS機能を活用して歩いた距離に応じた報酬が受け取れる
- 一時的なブームや投機対象というイメージだが、最近は持続可能な経済圏を構築する試みが増えている
 Trader Z
Trader Z「X to Earn」は、これからの時代の労働観を壊す革命的な概念と言えるでしょう。
昔は「働かざる者食うべからず」なんて言葉がありましたが、これからの時代は「遊ばざる者損をする」のような世界になるかもしれません。
それを加速させるのが「X to Earn」、つまり「何かすることで稼げる」という発想です。



根底にあるのは「価値の可視化」と「トークンエコノミーの参加」です。
ブロックチェーンという改ざんできない記録装置があるから、あなたの行動をトークンという形で「報酬化」できます。
こうした仕組みが成立するのは、中央集権じゃなく分散型経済圏だからです。
実際、地方創生の分野では、「貢献したらNFTがもらえる(デジさと)」みたいな施策もあり、X to Earnは社会貢献の可視化にまで踏み込めるのです。


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
X to Earn(X2E)とは?
基本的な仕組み
X to Earnは、特定の行動(X)に対して報酬として仮想通貨や独自トークンが与えられる仕組みの総称です。
遊ぶ・歩く・学ぶ・寝るといった、日常生活や趣味に近い行動を行うだけで経済的なインセンティブが発生するため、ゲームや健康管理と資産形成が結びつきやすいことが特徴です。
報酬として受け取れるトークンは、ブロックチェーン上で発行されているため、各種取引所やマーケットで交換できる可能性があります。
登場当初はゲームでモンスターを育成し、バトルに勝つとトークンがもらえるPlay to Earnが中心でしたが、徐々に運動習慣や学習習慣など他のジャンルへと広がり、総称としてX to Earnという言葉が定着しました。
Xを通じて手にしたトークンやアイテムはNFTとして保有できるケースもあり、単なるポイントではなく経済価値を持ちうる点が革新的です。
稼げる仕組みと収益性
X to Earnでは、行動を行うとプロジェクト運営元やコミュニティが発行するトークンが配布される仕組みが一般的です。特に、トークンの価格が上昇している時期には大きなリターンを得られるかもしれませんが、逆にトークン価値が下がる場合も考えられます。
あくまで投資的な側面もあるため、初期費用の回収期間が長引いたり、想定を下回る形になったりするケースも珍しくありません。
そのため、X to Earnを始める際には「お小遣い程度に狙えればいい」という考えで取り組むと精神的な負担が減るかもしれません。急激な価格変動やプロジェクト自体の存続リスクも念頭に置きながら、楽しむ感覚で参加すると良いでしょう。
X to Earnの主なジャンル
Play to Earn (P2E)
ゲームをプレイしてトークンを得る仕組みがPlay to Earnです。家庭用ゲームとは違い、ゲーム内のアイテムや通貨がNFTや仮想通貨として実際の価値を帯びる可能性がある点が画期的です。
代表的な例として、Axie Infinityというモンスター育成バトルゲームが世界的に人気を集めました。
このゲームでは、3体のモンスターを使って対戦し、勝利すると仮想通貨がもらえるというシンプルな仕組みが受け、特に新興国で生活費を補う手段としてブームになりました。
代表的なプロジェクト
先ほど挙げたAxie InfinityがPlay to Earnの先駆けとして有名です。ほかにもThe SandboxやSplinterlandsなど、カードバトルやメタバース内での土地運用を絡めたゲームが多数登場しています。
近年は大手ゲーム会社が続々と参入しており、日本国内でもPlay to Earnを視野に入れた新作タイトルがリリースされる可能性が取り沙汰されています。
メリット・デメリット
Play to Earnには、キャラクターやアイテムをコレクションする楽しみや、対戦のスリルを味わいつつトークン収益を狙える魅力があります。
一方で、初期投資がかかる場合もあり、強いキャラクターや装備を手に入れるためにNFTを高額購入するケースも見受けられます。
報酬が下がったりゲームの人気が落ちたりしたときには十分な収益を期待しにくくなるため、あくまで趣味と収入の両立を目指すイメージが大切です。
Move to Earn (M2E)
運動して稼ぐ仕組みがMove to Earnです。歩いたり走ったりするだけで暗号資産が付与されるため、健康志向のユーザーにとって大きな魅力を持っています。
なかでも有名なのがSTEPNで、専用のNFTスニーカーを購入して歩数を計測し、その結果に応じて仮想通貨が付与される仕組みが一躍注目されました。
代表的なプロジェクト
STEPNを筆頭に、SweatcoinやWalkenなどのプロジェクトが海外で話題を集めています。Sweatcoinは無料ダウンロードから始められ、歩数をスコア化して独自トークンに変換するスタイルを採用しています。
こうしたアプリは、運動を続けるモチベーションとしても役立ちやすく、生活習慣を改善したい方にとっても有用な選択肢かもしれません。
メリット・デメリット
運動不足を解消しながら仮想通貨を得られる点が最大のメリットです。
歩く習慣がもともとある方は、日々の生活に少しプラスアルファの収益をもたらしてくれるかもしれません。
ただし、プロジェクトによってはNFTスニーカーなどの初期投資が必要で、ブームが落ち着くと想定より報酬が下がる可能性もあります。適度なリスク管理を心がけ、運動習慣を楽しみながら続ける姿勢が大切です。
Learn to Earn (L2E)
学習することによって仮想通貨を得る仕組みがLearn to Earnです。
主に暗号資産の取引所や専門サイトが提供するオンライン学習コースで動画を視聴し、クイズに答えるとトークンが付与される形式が多く見られます。
代表的なプラットフォーム
海外のCoinbase EarnやBinance Learn & Earnが有名ですが、最近では日本の取引所も同様のキャンペーンを期間限定で行うケースがあります。
学ぶ内容は新規のアルトコイン概要やNFT基礎知識などが中心で、学習後にクイズに正解すると数ドル分のトークンが付与されることが一般的です。
メリット・デメリット
初心者でも暗号資産やNFTについて体系的に知る機会を得られる点が大きなメリットです。
さらに、クイズをクリアすることで少額ながら実際のトークンを体験できるため、投資リスクを大きく負わずに学べます。
一方で、もらえるトークンの額はそこまで大きくないことが多いので、短期間でまとまった利益を狙いたい方には物足りないかもしれません。
ただし、基礎知識を身につけられるメリットは将来的な投資活動にも生きる可能性があります。
Sleep to Earn (S2E)
眠ることでトークンを得るという新しい仕組みがSleep to Earnです。スマートフォンを枕元に置いてアプリを起動し、睡眠データを記録すると報酬としてトークンが付与される可能性があります。
睡眠習慣の改善を促すヘルスケアアプリとブロックチェーンを掛け合わせた形態といえます。
代表的なアプリ
SleeFiやSleepagotchiなど、まだ数は多くありませんが徐々に認知度が高まりつつあります。
基本的な流れは、眠る前にアプリを起動しておき、翌朝起きたときに睡眠の質が解析され、その数値に応じたトークンやNFTを得られるというものです。
メリット・デメリット
運動が苦手な方や、学習に時間を割きづらい方でも気軽に始めやすい点が魅力です。
健康管理との相性も高く、睡眠の質を意識するきっかけにもなります。
ただし、アプリによってはテスト段階のものが多く、安定した報酬が得られるかわからない段階かもしれません。これからの成長が期待される分野ですので、情報収集を怠らずに慎重に進めると良いでしょう。
その他のユニーク事例
Eat to Earn(食べて稼ぐ)やWatch to Earn(動画を観て稼ぐ)など、アイデア次第でさまざまな行動にトークンが付与される仕組みが考案されています。
たとえば、ブラウザ広告を閲覧するだけで仮想通貨を得られるブラウザBraveは、Browse to Earnの代表例としてユーザー数を増やしてきました。
Eat/Drink to Earn
飲食のレシートをスキャンしてポイントやトークンを獲得する仕組みが一部で実証されています。
レストラン利用の頻度に合わせてリワードを与える取り組みも見られるため、外食産業のプロモーションとして発展するかもしれません。
Watch/Listen to Earn
コンテンツを視聴したり音楽を聴いたりすることでトークンを得る試みが少しずつ登場しています。
分散型動画プラットフォームで視聴時間に応じて報酬を受け取れるものもあるため、将来的には動画配信サービスの仕組みが変わる可能性がありそうです。
Create/Write to Earn
クリエイターが作品を発表することで報酬を得る取り組みです。
NFTアートの作成やブログ記事を投稿して収益化する事例が増えています。自分のスキルや得意分野を生かしやすいため、普段から創作活動をしている方には魅力的に映るでしょう。
X to Earnが有名になった理由と歴史的背景
Axie Infinityから始まったPlay to Earnブーム
Play to Earnが一躍注目されたきっかけは、Axie Infinityの流行にあります。
特に新型コロナウイルス感染症の影響で家にいる時間が増えたことで、オンラインで収入を得る手段としてAxieに参入する人が急増したことが大きかったのです。
モンスターを育成してバトルに勝利すると得られるトークンの価格が上昇し、新興国では生活費をまかなえるレベルだと話題になりました。
ただし、その後はユーザー増加に伴う報酬のインフレ化や、ハッキング被害による資金流出などが重なり、ピーク時の収益を維持するのが難しくなったという面もあります。
それでも、ここで生まれた「行動が収益化する」という概念はGameFi全体に衝撃を与え、後続プロジェクトの誕生を促すきっかけになりました。
STEPNの爆発的ヒットとMove to Earnの躍進
Move to Earnを世に広めたSTEPNは、スマートフォンのGPS機能を活用して歩いた距離に応じた報酬が受け取れるアプリとして一気に広がりました。
歩くだけで仮想通貨を得られる可能性があるというインパクトが大きく、SNS上で注目を集めた結果、NFTスニーカーの価格が高騰するほどのブームが生まれました。
しかし、やはりユーザーが増えすぎるとトークンの価値が下がる可能性があります。
運営はトークンの焼却機能や新たな報酬体系の導入を検討するなど、持続可能な仕組みに向けて試行錯誤を続けています。こうした取り組みが成功すれば、Move to Earnは今後も成長していくかもしれません。
NFTとブロックチェーン技術の進化
X to Earnの普及には、NFTやブロックチェーン技術そのものの進化が大きく関係しています。
NFTを用いればゲームのキャラクターやスニーカーをはじめとするアイテムに実際の資産価値を持たせやすくなり、取引所で自由に売買できる道が開けます。
さらにブロックチェーンが処理能力や手数料の点で改善すれば、より多くのユーザーがストレスなく参加しやすくなるでしょう。
このように、技術の進歩がX to Earnの裾野を広げた背景があります。
一時的なブームに終わるのではなく、多様な行動をトークン化する取り組みとして定着する可能性も感じられます。
X to Earnの注目ニュース・トレンド(2025年)
大手企業や投資家の参入
近年は大手ゲーム会社や金融機関がブロックチェーンゲームやNFT事業に積極的に投資するようになりました。
スクウェア・エニックスがブロックチェーンゲームの開発を続々と表明したり、セガやバンダイナムコなどの日本企業がNFTプラットフォームやメタバース領域を研究したりする動きが相次いでいます。
これにより、従来のゲームユーザーや投資家以外にも認知が広がり、X to Earnという言葉自体が多くのメディアに取り上げられるようになっています。
新興プロジェクトの事例
X to Earnの概念をさらに拡張した「Tap to Earn」という単純操作で仮想通貨を取得できるプロジェクトが2024年以降に複数立ち上がりました。
SNSやチャットアプリの中でボタンを押すだけ、もしくはミニゲームを軽く遊ぶだけといった低ハードルの行動が報酬につながるスタイルです。
背景には、ブロックチェーンがより軽量化され、多くのトランザクションに対応できるようになった技術的進歩があります。
こうした新興プロジェクトの一部は短期間で膨大なユーザー数を獲得し、既存のX to Earnジャンルとは異なる層を取り込むことに成功しています。
今後はさらに多様化が進み、従来想像していなかった行動がトークン化される可能性もあるでしょう。
報酬モデルの持続可能性への取り組み
X to Earnプロジェクトは一時的なブームや投機対象というイメージを持たれがちですが、最近は持続可能な経済圏を構築する試みが増えています。
たとえば、トークンの供給量を制限する仕組みや、NFTのバーン(焼却)機能を導入して、インフレを抑制しようとする動きが代表的です。
STEPNなど大手プロジェクトも、運営がトークンを安易に配りすぎないよう調整を行い、ゲームやアプリの本来の楽しみや価値を高めようとしています。
こうした試行錯誤が功を奏すことで、市場の信頼が向上し、X to Earnが長期的なカルチャーとして根付くかもしれません。
X to Earn(X2E)とは?まとめ
X to Earnは、自分が行うさまざまな行動を通じて仮想通貨を得る可能性がある新しい仕組みです。
代表的なPlay to EarnやMove to Earnだけでなく、学ぶことでトークンを得たり、睡眠データを活用して報酬を受け取ったりと、ジャンルの幅はますます広がっています。
ただし、すべての行動が安定した収益につながるわけではなく、市場やプロジェクトの状況次第では損をするリスクも考えられます。
ブロックチェーン技術やNFTが今後どのように進化していくかによっても、可能性は大きく変わるでしょう。
もし本格的に始めたい場合は、国内仮想通貨取引所での口座開設が第一歩になりやすいです。初期費用と報酬のバランスを考慮しながら少額からチャレンジしてみてください。
また、当サイトが運営する自社サロンでは、コミュニティとの交流や短期トレード戦略のアドバイスが受けられますので、X to Earnを通して仮想通貨をより楽しみたい方はぜひ参加を検討してみてください。
生活の一部に少しずつ組み込みながら、自分らしい稼ぎ方と価値ある情報の取得を両立していただければ幸いです。