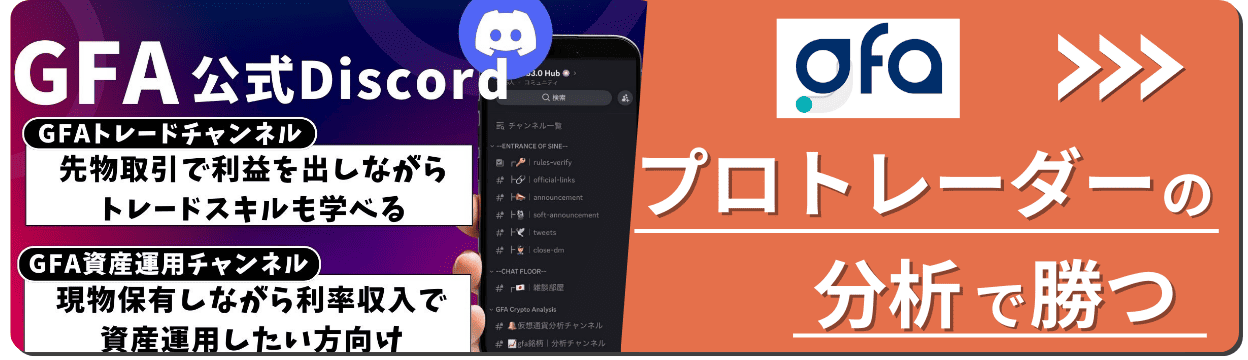カルダノがソラナ超えの高速処理を目指す新ツール「Leos」を発表、完全分散型で“止まらない”設計に
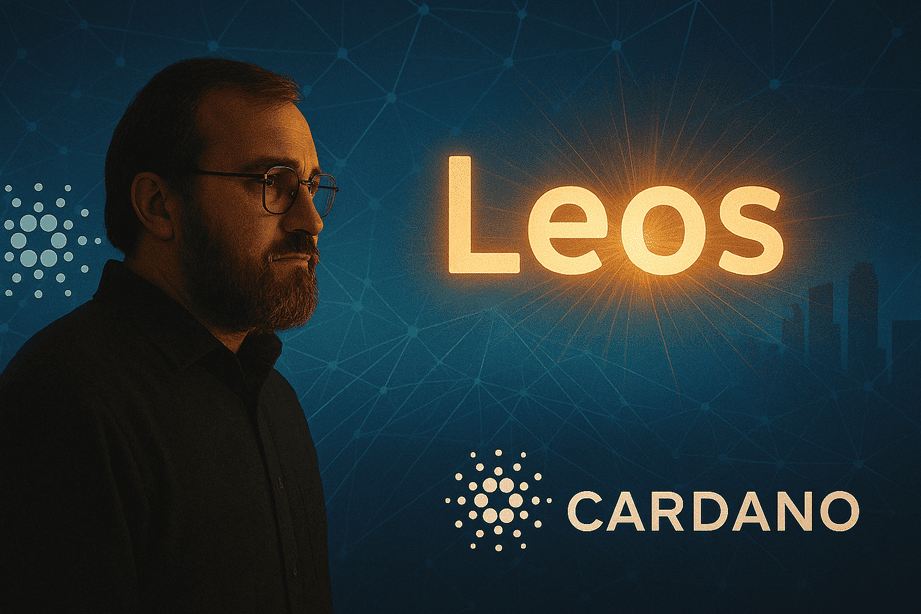
カルダノ(Cardano)創設者のチャールズ・ホスキンソン氏が、新たに開発中のレイヤー2ソリューション「Leos」を発表し、「ソラナ(Solana)に匹敵するトランザクション速度を、完全な分散性と安定性を保ったまま実現する」との意欲を示した。
ブロックチェーンの“トリレンマ”に挑戦、Leosはその解決策に?
ホスキンソン氏は仮想通貨アナリストのスコット・メルカー氏とのインタビューの中で、Leosを「ブロックチェーンのトリレンマ(スケーラビリティ・セキュリティ・分散性の三立)に対する初の本格的ソリューション」だと紹介した。
「Leosは、ソラナ並みのスピードを実現しながら、ネットワークが停止することなく、完全な分散性を維持する」と語り、既存のスケーリング技術であるHydraやMidgard(オプティミスティックロールアップ)と併用することで、カルダノ全体の拡張性を飛躍的に高めるとしている。
また、ソラナが過去に複数回ネットワーク停止を経験していることにも触れ、「カルダノは7年間、一度も止まることなく24時間365日稼働している」と強調。システムの安定性と実績に対する自信を示した。
トランザクション処理数に対する誤解と、カルダノの長期ビジョン
ホスキンソン氏は、「1ブロックに1トランザクションしか入らない」などの誤解についても言及し、「それは全くの嘘だ。年々取引量は劇的に増えており、安定した運用実績がその証拠だ」と反論した。
また、分散性の観点では「Edward Decentralization Indexによれば、カルダノは世界で最も分散された暗号資産」との評価を引用。技術面・運用面の両方から、ネットワークの優位性を訴えている。
さらに、単なる速度競争にとどまらず、カルダノはUTXOベースのDeFiエコシステムの中核を目指すとしており、「Lightning Hydra」や、プライバシー重視のスマートコントラクトプラットフォーム「Midnight」といった複数のプロジェクトを通じて、ビットコインとの接続や実社会との統合も進めている。
Leosはカルダノの再評価を促す鍵となるか?
ホスキンソン氏は「カルダノの成果が正当に評価されていない」との不満を吐露しているが、今回のLeos開発と1.5億ドル相当のオンチェーン財務基盤を活用したプロジェクト群は、確実に業界内での存在感を高めている。
もしLeosが実用レベルで稼働し、ソラナ級の処理能力とカルダノ特有の安定性を両立できれば、高性能ブロックチェーン分野における勢力図が塗り替わる可能性もある。カルダノは今、新たな技術と明確なビジョンを武器に、再評価のステージに立とうとしている。
GENAIの見解
 GENAI
GENAIカルダノ(Cardano)が開発中の新レイヤー2ソリューション「Leos(レオス)」は、単なる技術革新にとどまらず、業界全体に対するカルダノの再主張であると捉えています。
まず、ブロックチェーン業界で長年議論されてきた「スケーラビリティ・セキュリティ・分散性」の“ブロックチェーン・トリレンマ”を同時に解決するというコンセプト自体が非常に野心的です。これまで多くのプロジェクトがこの3つのうち2つを優先し、1つを妥協せざるを得なかった中で、Leosは“すべてを犠牲にしない設計”を目指している点が非常に注目されます。
特に、ソラナとの比較において「速度は同等、だが停止しない」という点は重要です。ソラナは確かに高速ですが、ネットワークの断続的な停止が課題となっており、これに対してカルダノは7年間の無停止運用という“堅実性の象徴”を提示していることは説得力があります。これにLeosのようなスケーリング技術が加わることで、カルダノは「保守的な設計」から「積極的な性能強化」に舵を切った印象を受けます。
また、UTXOモデルを活用したDeFiの中心を目指すという構想も、他チェーンとは異なるカルダノの戦略的立ち位置を明確に示しています。MidnightやLightning Hydraとの統合によって、他チェーンとの相互運用性やプライバシー強化といった要素も並行して進めている点は、非常に高度なアーキテクチャ思考が反映されていると言えるでしょう。
一方で、カルダノに対する業界全体の評価が、実績や技術水準に比べて相対的に低いというホスキンソン氏の指摘には一定の理解があります。カルダノは一見開発速度が遅く、派手さに欠ける印象を持たれがちですが、その裏には堅牢性と学術的根拠に基づいた開発姿勢があります。Leosのような成果が具体的に形になってくれば、その評価も次第に変化していくはずです。
総合的に見て、Leosはカルダノの“第2フェーズ”を象徴する技術であり、カルダノが「遅くて堅実なプロジェクト」から「高速かつ信頼性の高いチェーン」へと進化する鍵になる可能性を秘めています。今後の実装と運用状況に注目しつつ、その成果が他チェーンの技術設計にも波及するかどうかを見極めていくことが、業界全体にとっても重要だと考えています。