
ブリッジ通貨とは?仮想通貨XRPやXLMとの関係も含め徹底解説!
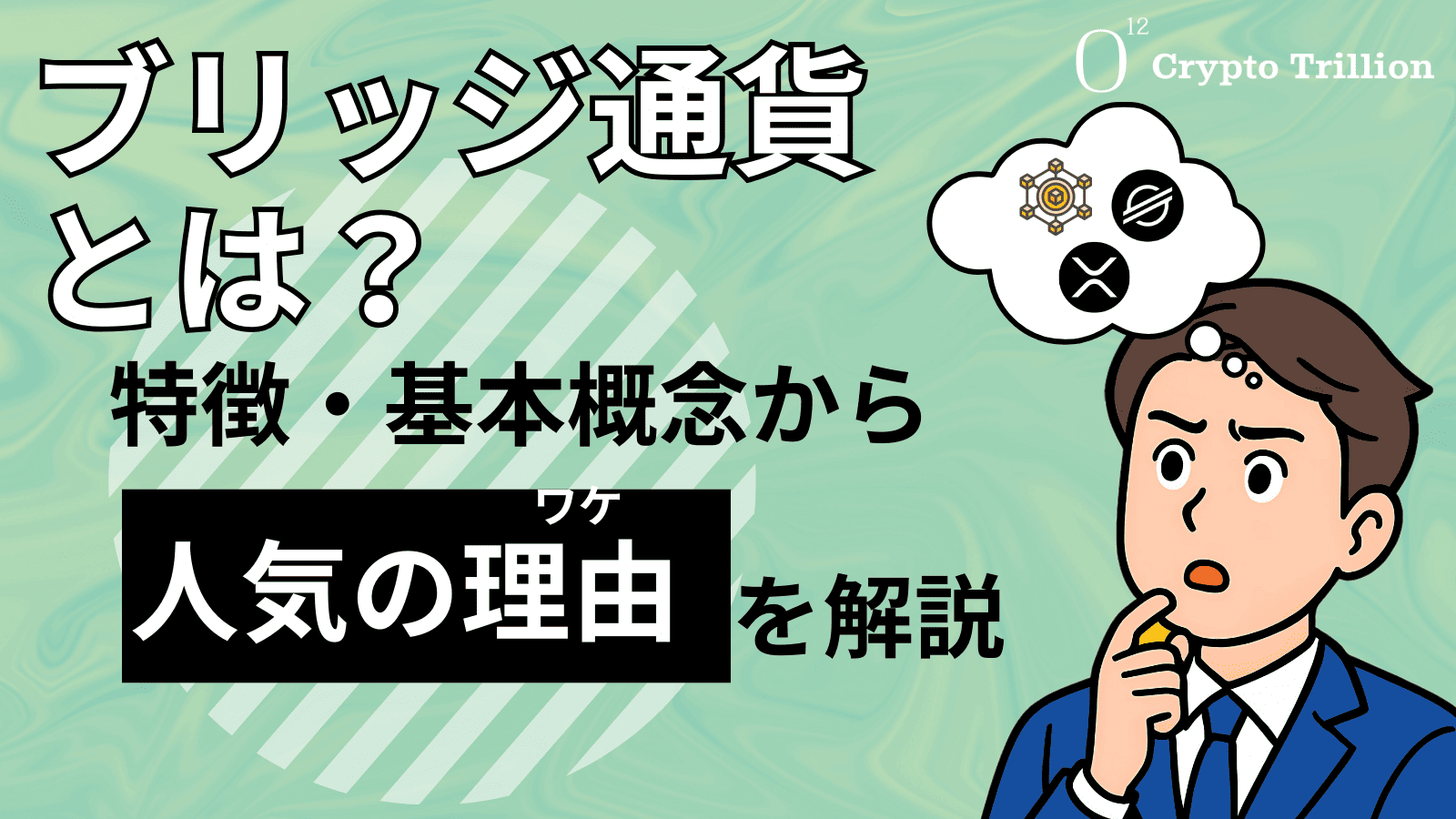
プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- ブリッジ通貨とは、「異なる仮想通貨同士の価値交換を仲介する法定通貨」のことを指す
- 銀行ネットワークを経由するより安価かつ高速な決済が期待できる
- 開発の意図は「ブロックチェーン技術を銀行や送金業に取り入れる」こと
- 従来のSWIFT経由の送金では複数日かかっていた処理を数秒〜数分で完了できる
- スマートフォンとネット接続さえあれば、ブリッジ通貨を使って手軽に海外へ送金できるサービスが続々と登場
- ブリッジ通貨を共通の仲介役とすることで流動性を高め、為替手数料を大幅に抑えられる可能性
- 銀行と連携して実際の送金テストを行うことで、リアルな送金コストの削減実績や送金速度の向上を示してきた
- 2012年国際送金企業Ripple社の仮想通貨「XRP」が最初のブリッジ通貨だと言われている
- Stellar (XLM)は途上国向けの安価な送金や金融包摂に力を入れる国際送金サービス
 Trader Z
Trader Zブリッジ通貨というものは、ある通貨と別の通貨を直接交換するのが難しい場合に、間に入って橋渡しの役割を担う通貨のことを指します。たとえば、通貨Aと通貨Bを直接交換する代わりに、通貨Cを一度介して交換する、というような仕組みです。
この考え方は一見便利に思えるかもしれませんが、ブロックチェーン技術の進化と、ビットコインのような世界共通のデジタル資産の普及が進んでいる現在においては、徐々にその必要性が薄れつつあるとも考えられます。



今後、ビットコインは「グローバルな共通通貨」としての地位を確立していくことが想定されます。
このようにビットコインが広く受け入れられるようになると、通貨同士を交換する際にわざわざブリッジ通貨を挟む必要がなくなっていくのです。つまり、「ビットコインで直接送金・決済が完結する」という時代が訪れるのは、時間の問題なのではないでしょうか。


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
ブリッジ通貨とは
ブリッジ通貨の定義
ブリッジ通貨とは、二つ以上の通貨を橋渡しする役割を担う暗号資産のことを指します。具体的には、送金する際に一度ブリッジ通貨に交換し、そこから受取通貨に再度交換する仕組みです。
たとえば日本円から米ドルへ国際送金を行う場合、まず日本円をブリッジ通貨(XRPなど)へ両替してから米ドルに換える流れになります。ブリッジ通貨を活用すると、直接円とドルを取引する手間やコストを削減できる可能性があります。
また、ブリッジ通貨は法定通貨のように特定の国家や中央銀行が管理するわけではありません。その代わり、ブロックチェーン技術を用いた台帳を使い、世界中のユーザーが相互に取引記録を検証できる点が特徴です。取引がネットワーク全体で承認されるしくみによって、中央集権型の管理者がいなくても両替や送金が完了します。
ブリッジ通貨の特徴
ブリッジ通貨は他の暗号資産や法定通貨とは異なり、支払いの中継を主な目的としています。
通常の暗号資産は「投資」や「価値保存」といった要素が強いですが、ブリッジ通貨は各国の金融機関や送金事業者に採用されることで、国際送金のインフラを支えることを想定してきました。
送金時の取引手数料が比較的安く、ネットワークの処理速度が速いものが多い点が評価されています。ただし、通貨価格の変動リスクは常に付きまとうため、送金に要する時間を短縮することで価格変動を最小化しようとする仕組みが多くのプロジェクトで導入されています。
実際、ブリッジ通貨の中には数秒から数十秒ほどで送金が完了するケースもあり、その速度は従来の国際銀行間送金より優れているとされます。
ブリッジ通貨が注目される背景
国際送金の課題と解決策
ブリッジ通貨が注目される最も大きな理由は、国際送金の煩雑さとコストの高さにあります。従来の銀行送金では、複数の中継銀行を経由しなければならないケースが多く、その過程で手数料が何重にも発生していました。さらに、途中で手続きが滞ると送金完了までに数日を要することもあります。
ブリッジ通貨はこの課題を解消するために、ブロックチェーン技術を活用して送金プロセスを簡素化しようとしています。特定の通貨ペアを直接交換するのではなく、ブリッジ通貨を共通の仲介役とすることで流動性を高め、為替手数料を大幅に抑えられる可能性があります。
加えて、ブロックチェーン上でリアルタイム承認を行えば、送金にかかる時間も大幅に短縮できると期待されています。
ブリッジ通貨の誕生と歴史
ブリッジ通貨は暗号資産市場の黎明期から存在していたわけではありません。最初に注目を集めたのは、国際送金企業として知られるRipple社が自社の暗号資産「XRP」を用いた送金ソリューションを打ち出したあたりからです。
2012年前後に本格的にプロジェクトが動き始め、2014年ごろから徐々に金融機関との提携をアピールするようになりました。
国際送金という具体的な用途を持つ暗号資産は当時珍しかったため、XRPは急速に知名度を高めました。その後、類似のコンセプトを持つプロジェクトが次々と登場し、ブリッジ通貨というカテゴリが形作られていきます。
中でもStellar(XLM)は、Ripple社の共同創業者の一人が立ち上げたプロジェクトであり、非営利財団を主体として国際送金と金融包摂をテーマに掲げました。
Ripple (XRP) の発展
XRPは銀行の協業が積極的に進められた点が大きな特徴です。銀行と連携して実際の送金テストを行うことで、リアルな送金コストの削減実績や送金速度の向上を示してきました。
特に2017年から2018年にかけて、多数の銀行や送金企業とパートナーシップ契約を結んだことで世界的な注目を集めた経緯があります。
現在でもXRPを使った送金ソリューションはオンデマンド流動性(ODL)と呼ばれ、海外送金の実需を狙ったサービスとして展開されています。
アメリカの証券規制当局との裁判など、法的な論争もありましたが、和解へ向けた動きが報じられ、Ripple社自身も新たな企業買収やステーブルコインの発行など積極的に事業拡大を図っているようです。
Stellar (XLM) の台頭
Stellar(XLM)は、途上国や個人ユーザーへのサービス提供に力を入れる点でRipple社とは少し異なる方向性を持っています。IBMとの共同実験や国際機関との協力で、手数料が安価な送金インフラとしての実用性を示してきました。近年ではCircle社のステーブルコイン(USDC)など、外部のデジタル資産と連携する取り組みも進んでいます。
特にMoneyGramとの提携によって、ユーザーが現金と暗号資産(USDCなど)を相互に交換できるサービスを展開したことは大きな話題になりました。伝統的な送金大手と非営利財団が共同でインフラを整備する形になり、従来の銀行口座を経由しなくても、携帯電話さえあれば国際的に送金を行いやすくなる可能性があります。
ブリッジ通貨の人気銘柄と選び方
Ripple (XRP)
XRPは「国際送金での中継を担う」というコンセプトがはっきりしており、銀行や送金企業との提携ニュースも多いです。送金スピードが非常に速く、手数料も安価な点が特徴とされます。実際の送金デモンストレーションが公開されるなど、技術的な裏付けが示されてきたことも注目度を高める一因になりました。
ただし、法的リスクの懸念が完全には拭えていないことも事実です。アメリカのSEC(証券取引委員会)から未登録証券疑惑をかけられた歴史があり、最終的な決着にはまだ時間を要するかもしれません。ブリッジ通貨の将来性を判断する際は、このような規制面のリスクにも目を向ける必要があります。
Stellar (XLM)
XLMは非営利財団によるプロジェクトであり、途上国向けの安価な送金や金融包摂に力を入れる姿勢をアピールしてきました。IBMなどの大企業との実証実験でも成果を上げ、近年はステーブルコインを積極的に受け入れるオープンなプラットフォームへと進化しています。
XLMは個人向けの国際送金サービスや、慈善団体の支援金配布を簡素化する取り組みも行っています。価格面ではビットコインやイーサリアムと比較してボラティリティがある程度小さい時期もありましたが、市場全体の影響を受けて上下する局面があるので注意は必要です。
その他のブリッジ通貨
ブリッジ通貨として名前が挙がりやすいのはXRPとXLMですが、近年はステーブルコインやDeFiプラットフォームで発行されるトークンも間接的にブリッジとして機能するケースが増えてきました。
仮想通貨市場は常に新しいプロジェクトが誕生しているため、すべてを把握するのは難しいかもしれません。大切なのは送金速度と手数料の低さ、そして流動性の高さをポイントに選ぶことです。
ブリッジ通貨と他の暗号資産の違い
決済・送金特化型 vs. 価値保存型
ビットコインが「デジタルゴールド」と呼ばれ価値の保存手段に重点を置く一方で、ブリッジ通貨は国際送金や通貨交換を支えるインフラとして生まれました。
ブリッジ通貨は取引の中継役を担うことを想定しているため、ネットワークの処理速度や手数料の安さを重視する設計になっています。投資目的で保有する人もいますが、開発の意図は「ブロックチェーン技術を銀行や送金業に取り入れる」ことにあります。
ブリッジ通貨とステーブルコイン
ブリッジ通貨と似た役割を果たす存在として、法定通貨の価格に連動するステーブルコインが挙げられます。ステーブルコインは価格変動リスクが小さいため、送金の中継に用いた場合にボラティリティの影響を抑えられる点が魅力です。
最近ではブリッジ通貨の機能をステーブルコインが代替するケースもあり、実際にStellar上でのUSDCやRipple社が独自に発行を目指すドル連動型コインなどが話題となっています。
流動性供給と相互運用性
ブリッジ通貨の強みは、複数の通貨ペアを一つの流動性プールに集約できることです。XRPやXLMなどの主要ブリッジ通貨は、多くの取引所や決済企業と連携することで、高い流動性を確保しやすいといわれます。
いろいろな国の銀行が同じブロックチェーンネットワークを利用することで相互運用性が高まり、地理的な制限を越えてリアルタイムに資金が動かせる可能性があります。
ボラティリティ対策と送金速度
ブリッジ通貨の送金は、通常数秒から数十秒で完了します。価格変動リスクをできるだけ抑えるために、送金にかかる時間を極力短縮しているのが特徴です。
それでも市場の状況によっては一日に数%以上価格が変動することがあるため、送金のたびに金額が変わる恐れも残ります。これに対処するため、送金プロセスを自動化し、ほぼリアルタイムで法定通貨へ換金する仕組みが各社によって模索されています。
ブリッジ通貨のメリット・デメリット
メリット
ブリッジ通貨を利用する大きなメリットは、従来の銀行送金よりも手数料が低く、送金にかかる時間も短縮できる可能性があることです。
銀行の国際送金では数日かかるうえに中継銀行ごとに手数料が発生しますが、ブリッジ通貨を使えばわずか数秒で取引が完了し、手数料も極めて安価になる場合があります。さらに、ブロックチェーン技術を活用することで透明性が高まり、不正や二重支払いのリスクを減らせるかもしれません。
デメリット
ブリッジ通貨はあくまでも暗号資産の一種であり、市場価格の変動は避けられません。送金時に急激なレート変動があった場合、送金額が想定よりも減ってしまうリスクがあります。
また、米国など一部の国では暗号資産を証券と見なすかどうかの議論が続いており、規制の行方次第では大きく環境が変わる可能性があります。プロジェクトが想定したスケジュールどおりに金融機関との連携が進まないケースもあるため、その点にも注意が必要です。
ブリッジ通貨の注目ニュース
世界各国の規制と国際協力
ブリッジ通貨を取り巻く規制は国や地域によって温度差があります。欧州ではMiCAと呼ばれる包括的な暗号資産規制が制定され、ステーブルコインを含む多様なトークンを法的に整備しようという動きが進みました。
アジア地域でもシンガポールや日本が比較的明確なルールを示し始めており、認可を得たうえで金融機関と連携する事例が増えています。
中央銀行デジタル通貨(CBDC)の議論もブリッジ通貨に影響を与えています。複数の国が共同で実験しているプロジェクトでは、デジタル通貨を相互に交換する仕組みとしてブロックチェーンが用いられるケースがあります。
公的なCBDCプロジェクトが本格化すれば、ブリッジ通貨の需要が高まるか、それともCBDCが直接の交換を担うかという議論がさらに深まるかもしれません。
主要プロジェクトのアップデート
Ripple社の動向
Ripple社はXRPの送金ソリューションを「オンデマンド流動性(ODL)」として展開し、銀行や送金企業とのパートナーシップを拡大してきました。米国SECとの長期にわたる訴訟が一部解決に近づいたことで、アメリカ市場へ再進出する可能性が高まっています。
また、最近は外国為替企業を買収し、ステーブルコイン「RLUSD」の発行やネットワークへの組み込みを目指すといったニュースも話題です。
Ripple社は以前から「XRPに頼らない送金インフラも検討している」と言及しており、ステーブルコインやCBDCとの共存を図る姿勢が見られます。ブリッジ通貨の概念をさらに進化させ、伝統的な金融機関と暗号資産市場を同時に取り込もうとする動きが加速している印象です。
Stellar財団の動き
Stellar財団(SDF)は非営利組織として、主に金融包摂と手数料の安い送金サービスを普及させる活動を続けています。MoneyGramとの提携によって、現金と暗号資産を直接交換できるサービスを世界各地で展開し始めたことが特筆されます。
さらに、Stellarネットワーク上で複数のステーブルコインが発行・利用されるようになり、XLMをブリッジ通貨として活用する事例とステーブルコインを活用する事例が混在する環境が整いつつあります。
また、Stellarがスマートコントラクト機能を導入することで、ブロックチェーン上でのアプリケーション開発が進む可能性があります。送金だけでなくDeFi分野のサービスが増えれば、ネットワーク全体としての流動性が高まり、XLMを中心にしたエコシステムがさらに拡大するかもしれません。
ブリッジ通貨の将来性と展望
国際送金・金融インフラへの影響
ブリッジ通貨は、銀行間ネットワークにおける国際送金を根本から変える可能性があります。従来のSWIFT経由の送金では複数日かかっていた処理を数秒〜数分で完了でき、マルチ通貨間の交換コストを下げることも視野に入ります。
金融機関がこのメリットを積極的に受け入れるようになれば、ブリッジ通貨は新たな「グローバル決済基盤」の一部を形作る存在になるかもしれません。
同時に、個人利用のハードルも徐々に下がっています。スマートフォンとネット接続さえあれば、ブリッジ通貨を使って手軽に海外へ送金できるサービスが続々と登場しているため、送金難民と呼ばれる銀行口座を持たない層への金融サービス拡大が期待されています。
CBDCとの連携と競合
各国の中央銀行が開発を進めるCBDCが本格的に普及すれば、ブリッジ通貨の存在感に影響を与えるとみられています。複数のCBDCを直接交換できる「mBridge」などのプロジェクトが成功すれば、ブリッジ通貨の役割が縮小するのではないかという見方もあります。
しかし、CBDCの相互運用を支える技術基盤としてブロックチェーンが使われるなら、既存のブリッジ通貨がその技術や流動性を提供する形で連携する可能性も否定できません。
特にRipple社は各国政府や中央銀行と対話しながらCBDC発行に協力すると発表しており、Stellar財団も途上国のデジタル通貨導入に積極的です。
CBDCとブリッジ通貨は対立する概念ではなく、むしろ補完関係にあるという声もあります。将来的にはブリッジ通貨がCBDC同士の交換を支え、さらにステーブルコインや従来の暗号資産とも自由に行き来できる多層的なエコシステムが生まれるかもしれません。
ブリッジ通貨のよくある質問(FAQ)
ブリッジ通貨とは何ですか?
異なる通貨間の取引を仲介する暗号資産です。具体的には、日本円から米ドルなどに交換する際に、一度ブリッジ通貨へ両替してから目的の通貨に換える仕組みを指します。これにより、直接交換できない通貨ペアでも効率的に送金できる可能性があります。
XRPとXLMの違いは?
どちらもブリッジ通貨として活用されやすい暗号資産ですが、Ripple社が商業ベースで展開するXRPは銀行との提携が多く、Stellar財団が非営利で運営するXLMは途上国や個人送金を重視する点が異なります。実装する技術やコミュニティの方向性にも少し差があります。
ブリッジ通貨は投資対象としてどうですか?
投資対象とされる場合もありますが、価格変動リスクがあるため慎重な検討が必要です。ブリッジ通貨は本来、国際送金や決済インフラをサポートする目的で設計されました。したがって投資というよりは、実際の利用が進むかどうか、そして規制環境が整うかどうかといった点が注目される要素になります。
送金でブリッジ通貨を使うメリットは何ですか?
従来の国際送金に比べて手数料が安く、送金スピードが速い可能性があります。また、複数の通貨をまとめて取り扱えるため、銀行口座や現地の規制に左右されにくい点も魅力です。一方、暗号資産のボラティリティや規制の変化には注意が必要です。価格が大きく動いた場合、結果的に想定より高いコストがかかる可能性もあります。
以上が「ブリッジ通貨とは?」を中心とした解説です。最初にもお伝えしたように、ブリッジ通貨は今後の国際送金や金融インフラに変化をもたらすかもしれません。最終的な判断には各通貨プロジェクトの公式情報や金融機関の動向も含め、総合的に検討することが大切です。
ブリッジ通貨とは?まとめ
ブリッジ通貨は国際送金の手間とコストを大幅に削減し、複数の通貨を滑らかにつなぐ存在として期待されてきました。代表的なXRPやXLMは金融機関との協業が進む一方で、市場価格の変動や規制リスクといった課題にも直面しています。
それでも従来の銀行間ネットワークを置き換える可能性があることから、今後も新たなニュースが続々と登場するかもしれません。ステーブルコインやCBDCとの連動が進めば、さらに送金が簡素化されることも考えられます。
将来的に大規模な採用が実現すれば、多くの人が日常生活の中でブリッジ通貨の恩恵を実感するシーンが増えるでしょう。




