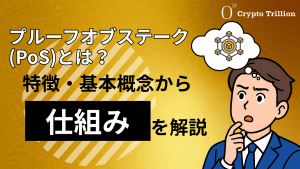プルーフオブステーク(PoS)とは?仕組みや将来性をわかりやすく解説!

プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- プルーフオブステーク(Proof of Stake, PoS)は仮想通貨のネットワークを安全に維持するための仕組み
- 保有しているトークン量に応じてブロック生成や取引承認に参加できるアルゴリズム
- PoWのマイニングのように高い計算能力を必要としないため、省エネ性能に優れ、環境負荷を軽減可能
- 自分が保有している仮想通貨をステーキング(担保として預け入れ)することでネットワーク維持に参加
- 正しい取引を承認すれば報酬を得られる一方、不正があれば自分のステークを失う可能性がある
- 消費電力の削減やブロック生成の高速化が期待できることから、多くの新興プロジェクトがPoSを採用
- Ethereum(イーサリアム)がPoWからPoSへ大型移行を行い、その成功によってPoSの認知度が急激に高まった
 Trader Z
Trader ZPoSでは、たくさんの仮想通貨を保有している人が、それに応じた確率でブロック生成の権利を得る仕組みとなっており、電力消費は極めて少なく、非常にエコロジカルです。
また、この方式はシステム全体に過度な負荷をかけないため、ネットワークの拡張性、すなわちトランザクション処理速度も向上しやすくなります。



このように、PoSはエネルギー効率に優れ、拡張性も高く、現代社会の倫理観や実利的な合理性に非常によくフィットしていると言えるでしょう。
だからこそ、イーサリアムのような巨大プロジェクトがPoSに移行したのも、時代の流れとしてはごく自然な選択だったわけです。
\日本円の入出金・仮想通貨の送金手数料無料!/


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
プルーフオブステーク(PoS)とは?
結論からお伝えすると、プルーフオブステーク(Proof of Stake, PoS)は仮想通貨のネットワークを安全に維持するための仕組みであり、保有しているトークン量に応じてブロック生成や取引承認に参加できるアルゴリズムです。
マイニングのように高い計算能力を必要としないため、省エネ性能に優れ、環境負荷を軽減できる可能性があります。
ビットコインなどが採用するプルーフオブワーク(PoW)に代わる方式として、近年は多くのブロックチェーンプロジェクトや投資家から注目を集めています。
PoSの概念は、自分が保有している仮想通貨を「ステーキング(担保として預け入れ)」することでネットワーク維持に参加する点に特徴があります。
正しい取引を承認すれば報酬を得られる一方、不正があれば自分のステークを失う可能性があるため、誠実な行動が促進されやすい仕組みです。
消費電力の削減やブロック生成の高速化が期待できることから、多くの新興プロジェクトがPoSを採用しています。
最近ではEthereum(イーサリアム)がPoWからPoSへ大型移行を行い、その成功によってPoSの認知度が急激に高まったといえるでしょう。
PoSが注目を集める理由
PoWとの比較
PoSが脚光を浴びるようになった背景には、PoWとの決定的な違いが関係しています。
PoWは高度な計算能力でブロック生成を競うため、大規模なマイニングプールが電力を大量に消費することが常態化していました。
ビットコインのマイニングにかかる年間消費電力量が世界の小国と同程度になるという報道が出たことで、暗号資産業界に対して批判の目が向けられるようになったのです。
一方のPoSでは、高性能のコンピュータを用いた計算競争が不要になります。
ブロック生成者として選ばれるかどうかはステーキングしたトークン量やランダム性によって決まり、選ばれた参加者は正しくブロックを承認することで報酬を獲得できます。
不正が発覚するとステークを失うペナルティが課されるため、結果的に真面目にネットワークを維持・管理しようとする動機づけが働きます。
こうした仕組みによって、PoSは環境負荷を抑えながらもネットワークの安全性を高められるという評価を得ています。
エネルギー効率と環境への影響
PoWで必要とされる大規模マイニングのための電力は膨大です。
実際に、世界的な電気自動車メーカーが「マイニングによる環境負荷」を理由にビットコイン決済の停止を発表したこともありました。
それ以来、暗号資産そのものが二酸化炭素排出量を増大させているという議論が高まり、PoWは社会的批判を受ける機会が増えています。
PoSの手法であれば、計算競争による消費電力はほぼ発生しません。
そのため、既存のPoW型チェーンに比べて環境負荷が大きく低減される可能性があります。
EthereumがPoSへ移行した際には、エネルギー消費が約99.9%削減されたとの報告があり、暗号資産市場だけでなく一般メディアでも大きく報道されました。
こうした環境面での優位性は、多くの新規プロジェクトや投資家にとって非常に魅力的に映るようです。
ネットワークの拡張性とガバナンス
PoSには、スケーラビリティやガバナンス面での利点も期待されています。
PoWでしばしば問題になる処理の遅延や手数料の高騰は、計算競争が激しくなるほど顕在化しやすいといわれます。
それに対してPoSでは、ブロック生成が比較的軽量に行える設計が多く、ネットワークの拡張性を高める可能性があります。
さらに、PoSではトークン保有者がステーキングを通じてネットワークのガバナンスに直接参加できる仕組みが整えられることが珍しくありません。
バリデータとして運用するだけでなく、プロトコルのアップグレードや開発方針の議論に投票権を行使することができるチェーンも増えています。
こうした参加型のガバナンス構造は、投資家やコミュニティが積極的にプロジェクトに関わるきっかけになるかもしれません。
PoSを採用する代表的な仮想通貨
Ethereum(イーサリアム)
Ethereumは当初ビットコイン同様、PoWを採用していましたが、2022年9月の「Merge(マージ)」によってPoSへと移行しました。
これは暗号資産界隈で大きな話題となり、Ethereumネットワークの年間エネルギー消費量が劇的に下がったことが報告されています。
PoS移行後は「ステーキング」によって報酬を得られる可能性があり、大手取引所や専門プールでも個人投資家が手軽に参画できる仕組みが整いつつあります。
2023年4月には「Shanghai(Shapella)アップグレード」が実施され、ステークしていたETHの引き出しが解禁されました。
これによりバリデータ参加の資金拘束リスクが下がり、より多くの参加者がステーキングを検討するようになっています。
EthereumはDeFiやNFTなど多彩な分散アプリケーションが稼働しているため、PoS化によってさらにエコシステムが拡大する可能性があります。
Cardano(カルダノ)
CardanoはEthereum共同創設者の一人、チャールズ・ホスキンソン氏が率いるブロックチェーンプロジェクトです。
独自の「Ouroboros(ウロボロス)」というPoSプロトコルを採用し、学術的な研究論文をベースに開発が進められてきました。
学術論文によるエビデンスを重視する特徴があり、カルダノ財団やIOHK(Input Output Hong Kong)といった組織がプロジェクトを支援しています。
バリデータは「ステークプール」と呼ばれる仕組みを通じて運用が行われることが多く、少額保有者でもステーキング報酬を得られる委任(デリゲート)機能が備わっています。
これによって、一般投資家でも簡単にPoSネットワークの維持に参加できるようになり、Cardanoコミュニティは世界各地で拡大しているようです。
Solana(ソラナ)
SolanaはPoSに加え、独自の「Proof of History(PoH)」という時間の証明手法を組み合わせることで、高速なトランザクション処理を実現することを目指したブロックチェーンです。
理論上は毎秒数万件の取引を処理できるともいわれ、従来のネットワークより手数料が安く済む可能性があります。
NFTやDeFiといった分散型アプリケーションがSolana上で多数稼働しており、その高速性が注目される理由の一つになっています。
ただし、過去に何度か大規模なネットワーク障害を起こした経緯もあるため、安定性とセキュリティ面の強化が今後の課題になるかもしれません。
とはいえ、高い拡張性を期待する開発者コミュニティや投資家からの支持は厚く、新しいアプリケーションが続々と生まれています。
Polkadot(ポルカドット)
Polkadotは、複数の異なるブロックチェーンを相互に接続するマルチチェーン構造を特徴とするプロジェクトです。
コンセンサスとしては「NPoS(ノミネーテッド・プルーフオブステーク)」を採用しており、バリデータだけでなくノミネーターという役割を設定することでセキュリティを保っています。
トークン保有者は信頼するバリデータに自分のDOTを委任し、その見返りとして報酬を得る可能性があります。
Polkadot上には「パラチェーン」という独立したブロックチェーンが並行して存在しており、リレーチェーンが全体のセキュリティを管理する仕組みです。
この構造によって、各パラチェーンは独自の機能やルールを持ちながら、Polkadot全体のセキュリティを共有できる可能性があります。
分散型金融(DeFi)やNFT、ゲームなど、多岐にわたるプロジェクトがパラチェーン枠を獲得するために競い合っています。
その他のPoS採用プロジェクト
近年は多くの新興ブロックチェーンがPoSベースで開発されるようになりました。
AvalancheやCosmos、Algorand、Tezosなど、それぞれ独自のコンセンサスアルゴリズムや特徴を打ち出しています。
さらに、AptosやSuiのような新興プロジェクトもPoSを中心に設計しており、高速トランザクション処理やユーザーエクスペリエンスの向上を狙っています。
ほとんどのプロジェクトが環境性能やスケーラビリティを重視していることから、PoSが暗号資産業界の主流アルゴリズムになりつつあるといっても過言ではないでしょう。
PoSの課題と今後の動向
セキュリティリスクとナッシング・アット・ステーク問題
PoSには大きなメリットがある一方で、特有の課題も存在します。とりわけ議論の的になりやすいのが「ナッシング・アット・ステーク問題」です。
PoSの仕組みでは、複数のブロックチェーンが同時に分岐した際、バリデータがどのチェーンにも署名を行ってもコストをほとんど負わない可能性があります。
PoWであれば膨大な電力を要するため、複数チェーンを同時にマイニングするのは現実的ではありませんが、PoSではステークをロックしているだけで署名が可能になり得るからです。
この問題を回避するため、多くのPoSチェーンは不正を行ったバリデータに対してステークを強制的に没収するスラッシング機構を導入しています。
また、ブロックに対する投票の最終性(ファイナリティ)を確立し、正当なチェーンが確定した後に別のチェーンを承認する行為を厳しく罰するプロトコル設計も行われています。
こうした対策によってセキュリティリスクを抑える取り組みが進んでおり、今後も改良が重ねられていくかもしれません。
富の集中リスクとステーキング規制
PoSは計算能力ではなく保有量に応じてブロック生成の機会が得られるため、大量にトークンを保有する参加者が報酬を獲得しやすくなります。
その結果、富の集中を助長する可能性があるという批判も出てきました。
特に大口ホルダーや大手取引所が運営するステーキングプールに多くの資金が集まると、ネットワークのガバナンスが一部勢力に偏りかねないという懸念が高まります。
この富の集中問題はPoWにおけるマイニングプールの中央集権化と同様、コンセンサスアルゴリズムが抱える構造的課題ともいえます。
規制当局もステーキングビジネスに関心を示しており、国や地域によってはステーキングサービスが証券取引に該当するかどうかを検討する動きがあるようです。
そうした背景もあり、事業者やコミュニティはガバナンスの分散度や透明性を高める仕組みを整える必要があるでしょう。
これからのPoS技術開発の方向性
PoSはすでに複数のプロジェクトで活用されていますが、より高い安全性と分散化を目指す研究が今も盛んに行われています。
たとえば「分散型バリデータ技術(DVT)」などは、バリデータノードが障害を起こしてもステーキング全体に影響が及びにくくする仕組みとして注目を集めています。
大手プロジェクトでもこうした新技術を取り入れる動きが進んでおり、PoSの安定性や耐障害性がさらに向上するかもしれません。
また、PoWからPoSへの移行を検討しているプロジェクトも増えています。
Ethereumに続いてZcashなどもハイブリッド型の導入を検討しているとの情報があります。
こうしたアップグレードには長期的な技術検証が必要ですが、成功すれば環境負荷低減だけでなくガバナンス面の進化も望めるかもしれません。
今後、既存のPoWチェーンがPoSへ移行する動きが相次ぐようであれば、PoSは暗号資産界全体のスタンダードになる可能性があります。
注目のニュース・アップデート
Ethereum MergeとShanghaiアップグレード
2022年9月に行われたEthereumのMergeは、PoWからPoSへ本格移行する歴史的イベントでした。
ネットワークの電力消費量が約99.9%削減されたと報告され、暗号資産業界のみならず一般紙でも大々的に取り上げられました。
Mergeによりマイニングは廃止され、ステーキングがネットワークを支える主軸となりました。
これを機にETHをステークする投資家も増え、ステーキングによる報酬の獲得を目指す動きが活発になったようです。
2023年4月のShanghai(Shapella)アップグレードでは、ステーキングしていたETHを引き出せるようになる機能が実装されました。
それまでロックされていたETHが自由に移動できるようになったことで、市場の流動性が高まる可能性があります。
大量の売り圧力が懸念されるという見方もありましたが、実際にはステーキング報酬を受け取りながら長期的に保有しようとする投資家が一定数いるようで、ネットワークの安定性は維持されているとみられます。
大手取引所のステーキングサービス
PoSチェーンの普及に伴い、大手取引所もステーキングサービスを積極的に提供するようになりました。
ユーザーが手持ちの通貨を取引所に預けるだけでステーキング報酬を受け取れるため、参入障壁が下がり、一般投資家にも利用しやすい環境が整いつつあります。
複雑なノード運用が不要になる半面、取引所がユーザーの資産を一括管理することで中央集権化が進む可能性もあり、PoSの「分散性」を損なわないか懸念を示す声も出ています。
ただし、すべての取引所が同じ条件でステーキングサービスを提供しているわけではありません。
運用手数料や報酬率、ロック期間などは事業者によって異なります。
規制面での縛りが強まる国・地域ではステーキングサービス自体が制限される場合もあり、ユーザーが利用する際には各取引所の仕組みを十分に理解する必要があるでしょう。
既存PoW通貨のPoS移行計画
Ethereumの成功を見て、既存のPoW通貨がPoSへの移行を検討する動きが広がる可能性があります。
たとえばZcash(ZEC)はプライバシー保護機能が特徴の暗号資産として知られていますが、PoSまたはハイブリッド型の導入を視野に入れた開発ロードマップを示唆しています。
これが実現すれば、プライバシー技術と省エネ性を両立するブロックチェーンとして新たな局面を迎えるかもしれません。
PoS化には技術的検証やコミュニティの合意形成が不可欠です。
Ethereumでさえ数年がかりで準備を重ね、ようやくMergeを成功させました。
Zcashなど他のプロジェクトも同様に時間を要する可能性があります。
ただし、PoWの電力消費が社会的に批判される流れの中で、PoSへの転換を試みる暗号資産が増えていくことは想定されるでしょう。
まとめ
プルーフオブステーク(PoS)は、仮想通貨の世界においてエネルギー効率やスケーラビリティ、ガバナンス強化など多面的なメリットがある合意形成アルゴリズムとして大きな注目を集めています。
ビットコインで採用されているプルーフオブワーク(PoW)の問題点を克服しようとする動きが後押しとなり、Ethereumをはじめ数多くのプロジェクトがPoSを導入しました。
PoSはトークンをステーキングすることでネットワーク維持に参加できる半面、富の集中やバリデータの不正行為をどのように抑止するのかといった課題も依然として残っています。
実際にPoSに移行したチェーンではスラッシングや厳格なファイナリティを導入するなど、問題に対処するためのさまざまな仕組みが試みられています。
EthereumのMerge成功後、ステーキングサービスが急速に普及し、投資家の参加意欲も高まっているようです。
すでに新規プロジェクトの多くはPoS型を標準に採用する流れが定着しており、今後は既存のPoW通貨が相次いでPoSへ移行する可能性もあるでしょう。
暗号資産全体が持続可能性や分散性、セキュリティの観点でさらに成熟していく上で、PoSの存在感はこれからも大きくなっていくかもしれません。