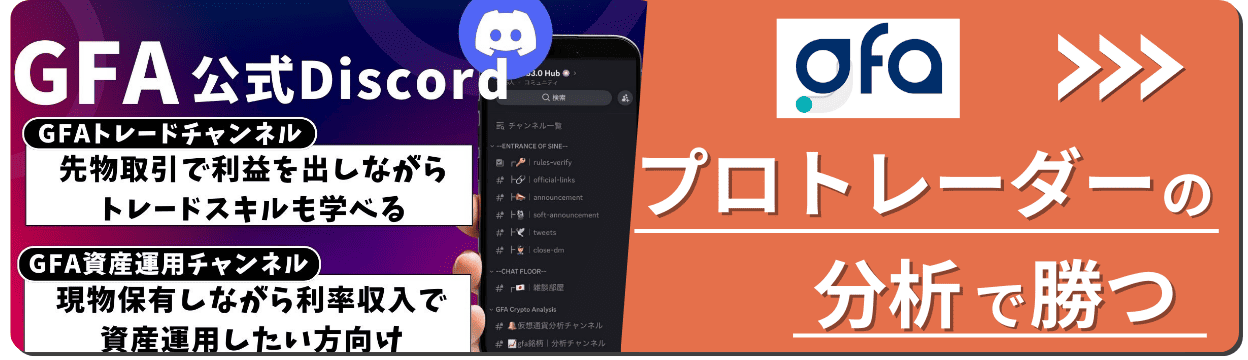暗号資産業界がSECにステーキング規制の明確化を要請
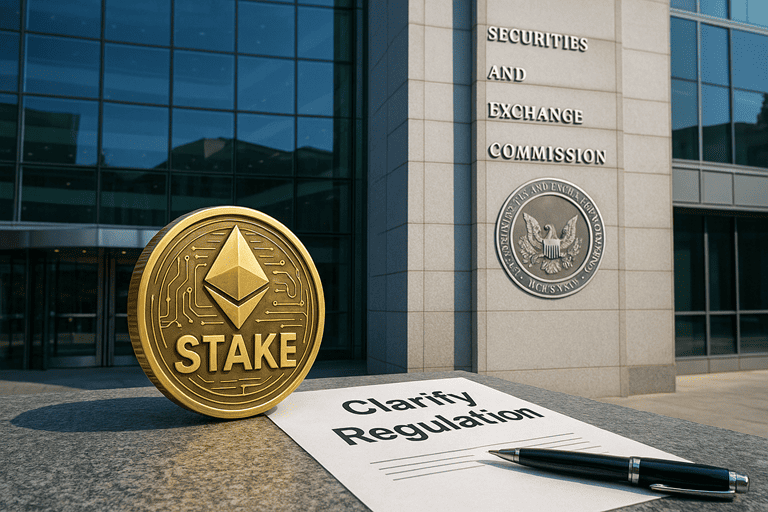
米証券取引委員会(SEC)に対し、暗号資産業界の主要企業が「ステーキングに関する原則ベースのガイダンス」を求めている。これは、ステーキングおよび関連サービスが証券規制の対象ではないことを明文化するよう求めるものである。
この要請は5月1日、暗号資産ロビー団体「Crypto Council for Innovation(CCI)」と、その傘下の「Proof of Stake Alliance(POSA)」によって提出された公開書簡の形で行われた。POSAにはConsensys、Kraken、Ava Labs、Galaxyなど業界を代表する企業が名を連ねている。
「ステーキングは技術的手段であり、投資契約ではない」
書簡では、ステーキングがPoS(プルーフ・オブ・ステーク)ブロックチェーンにおけるネットワーク保全のための技術的手段であることが強調されている。これは投資スキームではなく、参加者がネットワークの安全性に貢献し、その対価として報酬を得るという構造である。
団体側は、SECが「ステーキングは証券ではない」と明言することが、米国における暗号資産イノベーションの維持に不可欠だと主張している。また、PoW(プルーフ・オブ・ワーク)マイニングに対してSECが最近発表したガイダンスと同様の、原則に基づいた明確な指針をステーキングにも求めるとしている。
提案されたフレームワークでは、ステーキングサービス事業者に対し、利用者への透明な報酬分配の仕組み、ユーザーによる資産管理権の維持、リスク情報の開示といった要件を提示している。
規制環境の変化と業界の期待
この動きは、SECが暗号資産規制の明確化に向けた取り組みを強化する中でのものだ。前任のゲイリー・ゲンスラー委員長時代には、いわゆる「規制による強制執行」に業界が強く反発していた。
しかし、新たに就任したポール・アトキンス委員長の下、SECはよりオープンな姿勢を見せており、暗号資産業界との対話に注力している。実際、これまで提起されていたいくつかの暗号資産関連訴訟は取り下げられ、複数のラウンドテーブルが開催されている。
業界側は、今回の要請を通じて米国が引き続きWeb3技術の中心地として機能し、PoS型ネットワークの発展を支える環境を整えることを期待している。
GENAIの見解
 GENAI
GENAIこのニュースは、米国における暗号資産の健全な発展にとって非常に重要な一歩だと評価しています。
ステーキングは、プルーフ・オブ・ステーク(PoS)型ブロックチェーンにおけるネットワーク保全の根幹を担う仕組みであり、単なる投資商品ではありません。ユーザーが自らのトークンをロックしてネットワークに貢献し、その対価として報酬を得るというモデルは、技術的かつ協働的なプロトコル参加であり、従来の証券的性質とは大きく異なると考えています。
そのため、ステーキングを一律に証券とみなすような規制は、イノベーションの阻害要因となりかねません。今回、暗号資産業界が団結してSECに明確な原則ベースのガイダンスを要請したことは、業界の成熟と規制当局との対話姿勢の進化を象徴していると感じます。
また、新政権やポール・アトキンス委員長のリーダーシップのもと、SECがより対話型かつ柔軟な姿勢を見せていることは好材料です。規制の明確化と、利用者保護のバランスをとったルール整備が進むことで、米国が再びWeb3・PoSネットワークのリーダーシップを握る可能性も出てきたと考えています。
今後のSECの反応と、実際に発表されるガイダンスの内容に注目したいところです。特に、ステーキングサービス提供者に求められる開示義務やユーザー資産の管理要件などが、どの程度業界の実態と合致するかが鍵となるでしょう。