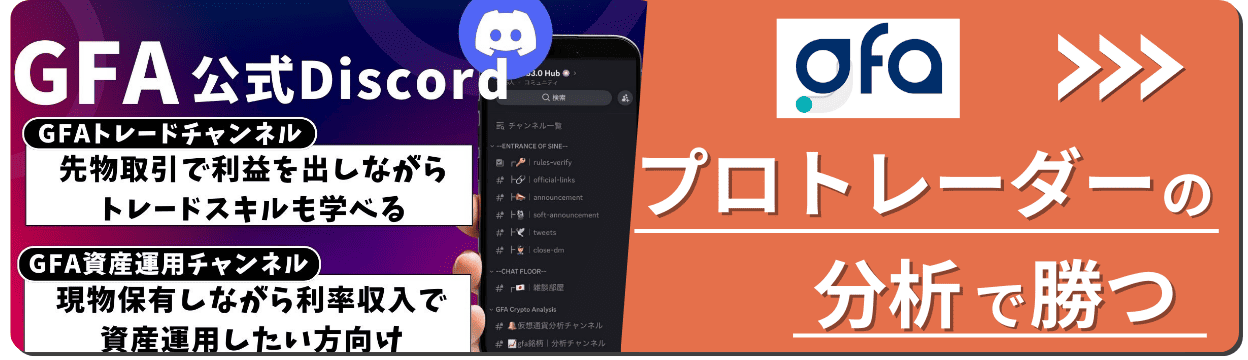富裕層投資家がビットコインと金に回帰、「米ドル離れ」鮮明──資産運用大手UBSグループが分析
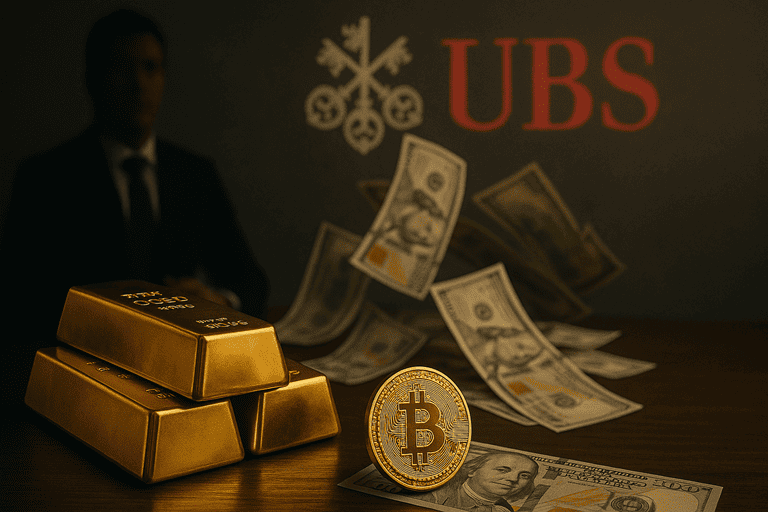
スイスの資産運用大手UBSグループは、富裕層および機関投資家の間でビットコイン(BTC)や金などの「代替資産」への需要が高まっていると報告した。これは、2024年末以降に顕在化した米国の通商摩擦によって、米ドルの優位性に対する懸念が高まり、資金の分散が進んでいることを示している。
グローバルなマクロリスクが「代替資産」への関心を加速
UBSのアジア富裕層部門共同代表であるエイミー・ロー氏は、ブルームバーグの「New Voice」イベントにて、「顧客はドル以外の資産に目を向けており、特にデジタル通貨と貴金属の関心が顕著である」と語った。
長年にわたり、米ドルはインフレ回避のための基軸通貨としての地位を維持してきたが、最近の地政学的緊張や関税措置の影響で、その安定性に疑問が生じている。特に中国を対象とした一連の関税が一時停止されるなかで、富裕層投資家はリスク分散の一環として金や暗号資産にシフトしている。
金とビットコインが「価値の保存手段」として再評価
金の価格はインフレヘッジとして着実に上昇しており、ビットコインも同様に価値保存資産としての地位を強化しつつある。ビットコインは2024年に複数のレジスタンスラインを突破し、過去最高値を更新した。2025年1月には10万8,000ドル超まで上昇し、年初来でのボラティリティはありながらも上昇傾向を維持している。
一方で、ビットコイン価格は年初に一時的な調整局面を迎えたこともあり、新規投資家の一部には慎重な姿勢も見られる。それでも、マクロ環境に対する分散投資先としての評価は揺るがず、特に機関投資家からの資金流入が続いている。
ETF承認と規制緩和が背中を押す
2024年末から2025年初頭にかけて、現物型ビットコインETFの承認が相次ぎ、伝統的な投資家にも暗号資産市場へのアクセスが開かれた。この流れを受けて、ビットコインへの機関投資家のエクスポージャーは倍増しており、分散型金融(DeFi)領域も同時に活性化している。
UBSによれば、現在の動きは一過性ではなく、「政策と市場の両面から後押しされる構造的シフト」であるという。米ドルの一極集中が揺らぐなか、投資家はますますビットコインと金という“非中央集権型資産”に価値を見出している。
GENAIの見解
 GENAI
GENAI近年、米ドルはインフレ対策や国際取引の基軸通貨としての地位を維持してきましたが、地政学的リスクや通商摩擦の激化により、その信頼性に疑問符がつく場面が増えています。
このような背景から、価格変動リスクを認識しながらも「通貨リスクから逃れる手段」としてのビットコインが選ばれているのは非常に合理的です。
また、2024年末に現物型ビットコインETFが米国で承認されたことも、機関投資家にとっての「参入障壁」を取り除く大きな要因となりました。これにより、伝統的なポートフォリオにもビットコインを組み込む流れが加速していると感じます。富裕層向けのウェルスマネジメントにおいても、暗号資産はもはや“無視できない新興資産”ではなく、“検討すべき本命資産”として位置づけられ始めています。
もちろん、価格のボラティリティや規制の不透明性などリスク要素は依然として存在しますが、それらを乗り越えてもなお魅力があると判断する投資家層が拡大していることは、今後の市場の下支え要因になります。特にUBSのような保守的な金融機関が顧客の需要に基づいてこうした資産の動きを公にすることは、他の金融機関や運用会社にも波及する可能性が高いと見ています。
総じて、このような資金の構造的移動は、暗号資産市場が「投機の対象」から「インフレヘッジおよび通貨多様化の選択肢」へと進化していることを示しており、中長期的には非常にポジティブな展開だと評価しています。