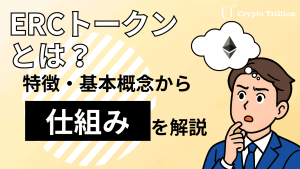イーサリアムの ERCトークンとは?特徴や種類、将来性などをわかりやすく解説!

プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- ERCトークンとはイーサリアムというブロックチェーンを基盤に発行・管理されるデジタル資産
- スマートコントラクトで定められたルール(ERC規格)に沿ってつくられるトークンの総称
- 2017年のICOで発行されたトークンの大半がイーサリアム上のERC-20という「規格」で作られた
- ERC規格とは開発者コミュニティで議論され、標準仕様として承認されたものを指す
- USDTやUSDCなどのステーブルコイン、LINK、SHIB、UNIなど多数のアルトコインがこの規格で作られる
- 「代替可能(Fungible)」なトークンを扱う基本的な規格ERC-20(USDT)
- 「非代替性」を特徴とするNFT(Non-Fungible Token)を扱う規格ERC-721(CryptoKitties)
- 一つのスマートコントラクト内で複数種類のトークンを管理できる ERC-1155(SAND)
- 米国や欧州の主要な金融機関が、イーサリアム上で証券のトークン化に積極的に取り組んでいる
- サンタンデール銀行:イーサリアムのパブリック・ブロックチェーン上で2,000万ドル相当の債券を発行
- UBS:イーサリアムブロックチェーン上で初のトークン化ファンドを立ち上げた
- ABNアムロ銀行:イーサリアム上で証券のトークン化に関するパイロットプログラムを成功裏に完了
 Trader Z
Trader ZERCトークンにより、信用と経済圏を個人や小さな組織でも構築できるようになりました。
たとえば、企業や自治体、コミュニティが独自のトークンを発行し、それを地域振興やプロジェクト支援に活用する。これまでは国家や大企業の専売特許だった「経済圏の創出」が、ERCトークンによって一気に民主化されたのです。



ERCトークンとは、単なる仮想通貨ではなく、「価値ある行動や貢献を、可視化・証明するためのデジタル証」でもあります。
これからの時代、「善いことをした人が得をする世界」をつくるためには、行動の見える化が必要です。その手段として、ERCトークンは大きな可能性を秘めていると言えるでしょう。


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
イーサリアムのERCトークンとは?
ERCトークンはイーサリアムというブロックチェーンを基盤に発行・管理されるデジタル資産です。イーサリアムにはスマートコントラクトと呼ばれる自動処理の仕組みがあり、そこで定められたルール(ERC規格)に沿ってつくられるトークンを総称して「ERCトークン」と呼んでいます。
結論から述べると、ERCトークンは「ビットコインのような独自のブロックチェーンを持たない代わりに、イーサリアムの利便性や知名度を活かして高い互換性を実現している存在」といえます。
例えば、2017年頃に多くのプロジェクトが実施したICO(イニシャル・コイン・オファリング)で資金調達の手段として発行されたトークンは、大半がイーサリアム上のERC-20という規格で作られました。
NFTアートやブロックチェーンゲームで耳にする「NFT(Non-Fungible Token)」も、ERC-721という規格に基づくERCトークンの一種です。こうした例から分かるとおり、ERCトークンは仮想通貨市場の主要トレンドを生み出す土台となり、多数のユーザーと企業の利用を後押ししてきました。
ERCトークンの基礎知識
ERCの成り立ちと役割
ERCは「Ethereum Request for Comments」の略称で、イーサリアム上の新しい機能や仕様を提案するための仕組みです。イーサリアムにはEIP(Ethereum Improvement Proposals)と呼ばれる改善提案が存在し、それらのうち特定の領域に関する標準仕様として認められたものがERCと呼ばれます。
ERCが重要視されるのは、ウォレットや取引所などのサービスが「同じインターフェース」でトークンを管理できるようになるからです。統一された規格がない状態だと、開発者やユーザーはトークンごとに扱い方を変えなくてはならず、利便性が低下してしまいます。
例えばERC-20は「送受信の方法」や「残高の確認」といった基本的なルールが統一されており、複数のERC-20トークンを一括でサポートしやすくなっています。このように規格化による互換性こそが、ERCトークンの拡大を後押しした大きな要因です。
ERCトークンが持つ3つの特徴
最初の特徴は、イーサリアム上で動作するスマートコントラクトによってトークンの発行や送受信が自動化できることです。これは「条件を満たしたら自動で処理を実行する」という仕組みで、資金の移動や配当の分配などに応用される場合があります。
次に、ERC規格に従うことで、外部サービスとの互換性が得られる点も大きな特徴です。世界中のウォレット・取引所・アプリケーションがERC-20やERC-721といった標準規格に対応しているため、新しく発行されたトークンが素早く受け入れられる可能性があります。
さらに、ガバナンストークンやステーブルコインなど、多彩なトークン形態を柔軟に設計しやすいという点も見逃せません。単なる「通貨型トークン」にとどまらず、組織の議決権や配当権を与えるトークンや、米ドルに連動するステーブルコインなど、多様な目的をトークン化して表現できる仕組みが整っています。
主なERCトークン規格
ERC-20(最も一般的なトークン規格)
ERC-20は「代替可能(Fungible)」なトークンを扱う基本的な規格です。代替可能とは、1枚1枚のトークンが全て同じ価値と性質を持つことを指します。例えば「1ETHは誰のものでも同じETH」という概念と近く、同一規格のトークン同士で区別がなく交換可能な状態を指します。
2017年頃に流行したICOでは、資金調達を行うプロジェクトが自社のトークンをERC-20ベースで大量に発行し、出資者に配布する手法が広まりました。
その結果、ICOブームによってERC-20がほぼデファクトスタンダード(事実上の標準規格)となり、ウォレットや取引所もこれに対応する流れが急速に進みました。現在では、USDTやUSDCといった主要ステーブルコインのほか、数多くの銘柄がERC-20を採用し、世界的に多くのユーザーに利用されています。
ERC-721(NFT規格)
ERC-721は「非代替性」を特徴とするNFTを扱う規格です。非代替性とは、1トークンごとに異なる価値が割り当てられており、互いに交換できない一品ものを示す概念です。たとえば同じ仮想通貨のコインでも1枚ごとに固有の個性があるイメージを持つとわかりやすいかもしれません。
アートやコレクターズアイテム、ゲームアイテムなどで「この一点ものに価値がある」という性質を証明するときに使われます。2017年に登場した「CryptoKitties」や、2021年に話題となったデジタルアートオークションがNFTという形をとったことで、ERC-721が一気に有名になりました。
アーティストやコンテンツクリエイターにとっては、自分の作品をブロックチェーン上に登録し、偽造リスクを大幅に下げつつ所有権を売買できるメリットがあります。ファッションや音楽業界にも波及し、いまやブロックチェーンを代表するユースケースの一つに成長しています。
ERC-1155(マルチトークン規格)
ERC-1155は2019年に提案された比較的新しい規格で、一つのスマートコントラクト内で複数種類のトークンを管理できます。具体的には、ゲーム内通貨(ERC-20のようなFungibleトークン)と、キャラクターや武器のように一点物として扱うNFT(ERC-721のようなNon-Fungibleトークン)をまとめて定義することが可能です。
それまではERC-20とERC-721を別々に扱う必要があり、開発が煩雑でした。ERC-1155はこの問題を解決し、特にブロックチェーンゲーム開発において複数のアイテムを一括管理できる便利な規格として注目されています。ガス代や運用コストの削減につながるという利点もあり、NFT市場がさらに成熟するにしたがって広く採用されるかもしれません。
その他の規格(ERC-223、ERC-725など)
ERC-223は誤ったアドレスに送金したときのトークン消失トラブルを防ぐ設計が特徴であり、従来のERC-20の弱点を補う提案として注目されました。
ERC-725やERC-735はブロックチェーン上のID管理や証明書に関わる仕様を定義しており、個人情報を自分で管理する「自己主権型ID」の実現に寄与すると考えられています。このようにERC規格は多岐にわたっており、今後も新たな課題やユースケースに合わせて改良提案が増えていくかもしれません。
ERCトークンが注目される理由
ICOブームとERC-20の役割
2017年頃に盛り上がったICOブームでは、スタートアップや開発者コミュニティがERC-20を使って新しいトークンを発行し、出資者に配布する仕組みが注目を集めました。当時はビットコインのように独自ブロックチェーンを立ち上げるハードルが高かったため、手軽にトークンを作れるイーサリアムが選ばれたという経緯があります。
ICOに参加する投資家や利用者が増えた結果、世界の暗号資産取引所やウォレットがこぞってERC-20対応を進め、広く普及する下地ができたのです。
ただしICOブームの急拡大の裏側には、実質的な事業内容がともなわない案件や詐欺目的のプロジェクトが混在していた側面もありました。それでも、ブロックチェーンや暗号資産に関心を持つユーザーが大幅に増えた事実は業界発展の原動力となり、ERC-20規格の存在はその一翼を担っていました。
DeFi・NFTの隆盛
DeFi(分散型金融)は、貸し借りや取引所、デリバティブなどのサービスをブロックチェーン上で提供する試みです。従来の金融機関を介さずに、ユーザー同士がウォレットを通じて直接やり取りできるのが特徴で、多くのプラットフォームがイーサリアムを基盤としています。
そうしたプラットフォーム上ではガバナンストークンやユーティリティトークンとしてERC-20規格が頻繁に使われ、利用者が増えるほどトークンの需要が高まる仕組みが生まれました。
一方で、NFTとして知られるERC-721規格は、デジタルアートの売買やゲーム内アイテムの所有権移転をブロックチェーン上で実現し、2021年頃から大きな注目を浴びました。
アーティストがオンライン上で作品を販売するとき、ERC-721を使うことで唯一無二の価値を示しやすくなった点が評価されています。こうした分野の拡大がイーサリアム上の取引量を押し上げ、結果としてERC-20やERC-721をはじめとするERCトークン全体への注目度が高まりました。
企業やサービスでの導入事例
ステーブルコインは法定通貨(主に米ドル)と1対1で価値が連動する暗号資産を指します。USDTやUSDCなどの著名なステーブルコインはいずれもERC-20で発行されており、PayPalなどの大手決済企業もイーサリアム基盤のステーブルコインを展開する流れが出てきました。
これによって従来の銀行送金より安価で高速な国際送金が可能になり、暗号資産を生活やビジネスで活用する場面が世界的に増えつつあります。ゲーム企業やエンタメ企業がNFTを導入する事例も近年注目を集めています。
特にブロックチェーンゲームの分野では、キャラクターやアイテムをNFT化することで所有者に利益が還元される設計が試みられています。ファッションブランドがNFTを使って限定アイテムの所有証明を行うなど、非IT企業でも独自のトークン発行を検討する流れが加速しており、ERC規格の認知度が広範囲に広がっています。
ERCトークンと他の仮想通貨の違い
独自チェーンを持つコインとの違い
仮想通貨には「コイン」と呼ばれるものと「トークン」と呼ばれるものがあります。ビットコイン(BTC)やリップル(XRP)のように独自のブロックチェーンを持つものはコインと分類される一方、イーサリアムなどのプラットフォーム上で稼働するものはトークンと呼ばれます。
ERCトークンは後者であり、イーサリアムというレイヤー1のネットワークを利用している点が特徴です。トークンを送金するときは、処理を行うマイナーやバリデータに支払う手数料(ガス代)としてETH(イーサ)が必要になります。
一方で、開発者は独自チェーンを立ち上げるコストをかけずにイーサリアムのセキュリティやネットワーク効果を利用できるため、多くのプロジェクトがERCトークンの形を選んでいます。
メリットとデメリット
ERCトークンを採用するメリットには、既存のウォレットや取引所が対応しており流通面で優位に立てること、イーサリアムのスマートコントラクトを活用して高度な機能を実装しやすいことが挙げられます。専門知識を持つ開発者コミュニティや関連ツールが豊富なのも強みです。
一方で、イーサリアムのネットワークは需要が集中するとガス代が非常に高くなる場合があります。ICOやNFTが過熱した時期には手数料が跳ね上がり、小口送金が行いにくくなるケースがありました。また、誰でもトークンを作成できるがゆえに、投機的なプロジェクトや詐欺的なトークンも少なからず存在します。
将来的にはイーサリアムのスケーリング技術(レイヤー2ソリューションなど)が普及することで、高いガス代の問題が緩和されるかもしれませんが、常にリスクや課題が残ることは意識しておく必要があります。
ERCトークンに関する注目ニュース
海外における主な動向
2025年に入ってからは、欧米の大手金融機関がERCトークンを活用した証券トークン化の実証実験に取り組む事例が少しずつ増えてきました。従来はクローズドなブロックチェーンを使う動きが多かったのに対し、パブリックなイーサリアムを直接利用する流れが生まれている点が注目ポイントです。
一方、NFTの市場規模は2021年頃の急騰期と比べると落ち着きを見せているようです。ただ、既存の芸術作品やキャラクターコラボにとどまらず、スポーツのデジタルアイテム、音楽の権利分割、メタバース上の不動産など、多様な方向で応用が拡がり続けています。
- サンタンデール銀行(スペイン)
2019年9月、サンタンデール銀行はイーサリアムのパブリック・ブロックチェーン上で2,000万ドル相当の債券を発行しました。これは、エンドツーエンドでブロックチェーン技術を活用した初の債券発行とされています。 - 欧州投資銀行(EIB)
2021年4月、EIBはイーサリアム上で1億ユーロ(約1億2,100万ドル)の2年物デジタル債を発行しました。これは、主要な公的金融機関による初のデジタル債発行の一例です。 - ABNアムロ銀行(オランダ)
2024年2月、ABNアムロは21Xと協力し、イーサリアム上で証券のトークン化に関するパイロットプログラムを成功裏に完了しました。この試験では、ステーブルコインを用いたトークン化証券の発行と決済が行われ、金融システムの効率化が示されました。 - UBS(スイス)
UBSは、イーサリアム・ブロックチェーン上で初のトークン化ファンドを立ち上げ、投資家がファンドのシェアをデジタル資産として取引できるようにしました。これにより、管理コストの削減や決済の迅速化が実現されています。 - ドイツ銀行(ドイツ)
2024年12月、ドイツ銀行はイーサリアムのレイヤー2ソリューションであるZKsyncを活用し、デジタルトランザクションの最適化とデジタル資産サービスの拡充を目指す取り組みを開始しました。
日本国内の最新トピックス
日本では改正資金決済法の施行をきっかけに、海外発行のステーブルコインを取り扱う取引所が増えてきました。かつては法令上の問題からステーブルコインの購入や運用が制限されがちでしたが、最近は大手取引所を中心にUSDCなどが扱われるようになり、実務レベルでの活用が身近になってきています。
メガバンクや大手金融グループも、ブロックチェーン技術を使った企業決済や金融サービスに意欲的です。実証実験の段階を経て、実際に小売店やオンライン決済への活用例が増え始めています。
また、国内の大手企業がNFTを絡めたマーケティングを試みる例も目立ち始めました。エンタメやスポーツ系のイベントチケットをNFT化して偽造を防ぎつつ転売を管理する動きは、日本でも徐々に実用化されてきている状況です。
イーサリアムのERCトークンとは?まとめ
ERCトークンはイーサリアムのスマートコントラクト機能を活用し、誰でも比較的簡単に発行できる柔軟性が特徴です。ICOやNFT、DeFiなどの分野で積極的に利用され、暗号資産全体の発展に大きな役割を果たしてきました。
イーサリアムのネットワークがもともと備えるセキュリティやネットワーク効果を活用できる点が魅力である一方、ガス代の高騰や詐欺トークンのリスクなど、利用者が気をつけるべきポイントも存在します。
仮想通貨初心者にとっては、まずは信頼性の高い国内取引所で認知度の高いERCトークンを購入し、使い慣れたウォレットで保管するところから始めるのが無難かもしれません。投資対象として考える場合も、断定的に利益が得られるわけではなく、市場動向やプロジェクトの実力を慎重に見極めることが肝心です。
今後は金融機関や大手企業がブロックチェーンの利用をさらに拡大していくかもしれませんので、ERCトークンを取り巻くニュースをこまめにチェックしていくと、最新のトレンドや技術的な進化を把握しやすくなるでしょう。
長期的な視点を持ちながら、正しい知識と安全策を身につけていくことで、ERCトークンの世界をより安心して楽しめる可能性があります。