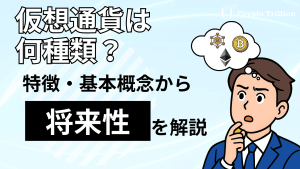仮想通貨のトークンは何種類?初めて聞く人にもわかりやすく解説します!

プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- 仮想通貨におけるトークンは「ブロックチェーン上で発行・管理されるデジタルな資産」
- ビットコインやイーサリアムは通貨型のトークンとして分類される
- 広義でのトークンとは本来「証拠」や「引換券」のような役割を持つもの
- トークンは発行主体が存在し、その用途や価値が何らかの形で保証・管理されている
- 通貨型・ユーティリティ型・アセット型などの種類がある
- 通貨型トークン:同価値で互換性があり、送金や決済に使える
- ユーティリティトークン:特定のサービスやプロダクト内で使える機能や権利を持つ
- アセットトークン:現実世界の資産や価値に裏付けられたトークン
- DeFi関連のトークンやNFT(非代替性トークン)が近年注目を集める
- DeFi系トークン:国家や銀行などの中央管理者がいなくても信頼できる価値交換が可能
- NFT:ブロックチェーン技術を活用して作成された、代替不可能なデジタルデータ
- 現実世界の資産をブロックチェーン上で表現する流れが加速
- 2024年にはマイクロファイナンス債券など、様々な資産のトークン化プロジェクトが登場
- 世界最大級の資産運用会社ブラックロックなどの大手金融機関もトークン化ファンドに参入
 Trader Z
Trader Z上記で述べたとおり、仮想通貨におけるトークンにはさまざまな使い道がありますが、トークン化の最大の意義は「現実世界の価値を、デジタルの世界で証明できる」点にあります。



たとえば、不動産は詐欺のリスクも多い資産ですが、NFTとしてブロックチェーン上に記録することで、その所有権や取引履歴を改ざん不可能な形で管理することができ、不正を防ぐ手段となります。
ブランド品は偽物対策として、ブロックチェーンで正規品を証明できます。ゲーム内アイテムも、NFT化により売買や所有の証明が可能です。
つまり、仮想通貨におけるトークンとは「価値あるモノを、透明性と信頼性をもって、世界中に瞬時に届けるための器」なのです。


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
仮想通貨とは
デジタルな通貨
仮想通貨はインターネット上でやり取りできるデジタルなお金です。
日本の法律では「不特定の者に対して代金の支払い等に使用でき、法定通貨と交換でき、電子的に記録されて移転できる財産的価値」と定義されています。
簡単に言えば、国家が発行する円やドルではないけれど、オンライン上で売買や送金に使えるお金ということです。
ブロックチェーン技術:
ブロックチェーンは、多くの仮想通貨やトークンの基盤となる技術です。トークンを理解するには、ブロックチェーンとの関係を押さえておくとスムーズでしょう。
ブロックチェーンとは直訳すると「ブロックの鎖」という意味で、取引データの塊(ブロック)を時系列に連結(チェーン)していくことで安全に記録を残す仕組みです
法定通貨との違い
日本円やドルなどの法定通貨とは異なり、仮想通貨は国家や中央銀行による保証がありません。その代わり、世界中の参加者の合意(ネットワーク上のプログラム)によって価値が維持されています。
仮想通貨は法定通貨と違って価格変動が大きい特徴がありますが、その分これまでにない資産運用の手段として世界中で注目されています。
有名なビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)は、銀行などの中央管理者を介さずに個人同士で直接取引できる仕組みを持っています。
これらはブロックチェーンという先端技術によって取引記録の改ざんが防がれ、信頼性が担保されています。
トークンとは
広義のトークン
トークンという言葉自体は日常生活でも使われています。
本来「token」とは「何か別の価値を代替するもの」という意味で、カジノのチップや商品券、ポイントカードなども広い意味でトークンと呼ばれます。
たとえばゲームセンターのコインや図書カードも、現金の代わりに使えるという点でトークンの一例です。
つまり、トークンとは本来「証拠」や「引換券」のような役割を持つものなのです。
仮想通貨におけるトークン
仮想通貨の世界における「トークン」も、この考え方を引き継いでいます。
仮想通貨の文脈では、ブロックチェーン技術を用いて発行されたデジタル資産全般を指して「トークン」と呼ぶことが多いです。
広い意味ではビットコインやイーサリアムなど既存の仮想通貨もトークンに含まれますが、一般的には独自のブロックチェーンを持たないデジタル資産を指すことが多いでしょう
仮想通貨との違い
厳密な定義では、人によって「コイン」と「トークン」を区別する場合があります。
簡単にまとめると、
コイン: 独自ブロックチェーン上の通貨(例: ビットコイン、イーサリアム)
トークン: 他のブロックチェーン上で動く資産(例: イーサリアム上で発行されるERC-20トークンなど)という違いがあります。
ただし仮想通貨全般を広く指して「トークン」と呼ぶこともあるので、文脈によって意味が変わる点に注意しましょう。
ブロックチェーンとトークンの関係
取引記録の台帳
従来の銀行などの台帳では一箇所で取引記録を管理しますが、ブロックチェーンでは世界中の参加者(ノード)が取引データを分散して保管し、互いに監視し合うことで改ざんを防いでいます。
そのため中央管理者が不要で、誰でもネットを通じて参加できる公開の取引台帳として機能しているのです。
スマートコントラクト
特にイーサリアム上のトークンであれば、発行量や配布ルール、追加発行の有無などもスマートコントラクト(プログラム)で定義されており、透明性が高く自律的に運用されています。
これにより、小さなベンチャー企業でも独自トークンを発行して資金調達(ICO=Initial Coin Offering)したり、ゲーム内アイテムをトークン化して流通させたりといったことが可能になりました。
要するに「ブロックチェーンという土台」の上に「トークンというデジタル資産」が載っているイメージです。
土台がしっかりしているからこそ、トークンの信用や取引の安全性が保たれているわけですね。
ブロックチェーン上での価値流通
トークンはブロックチェーン上を移動するデータなので、インターネットさえつながっていれば世界中どこへでも価値を送ることができます。
例えば日本から海外の人にトークンを送る場合でも、銀行などを介さず直接ブロックチェーン経由で送付が可能です。
トークンの種類
通貨型トークン(決済型)
通貨としての利用を目的としたトークンです。ビットコインやライトコインなど、送金や支払いに使われ価値の保存手段となるものが該当します。
価格変動を抑えて法定通貨と連動した「ステーブルコイン」もこの分類といえます(例: 米ドル連動のUSDTやUSDC)。
ユーティリティトークン
サービスやアプリ内で使用するためのトークンです。
言わば「利用券」のような役割で、特定のプラットフォーム上で手数料の支払いに使えたり、サービスを利用する権利を得たりします。
例えば仮想通貨取引所の手数料割引に使えるBNBトークンや、ゲーム内アイテム購入に使うトークンなどがユーティリティトークンです。
アセットトークン(資産担保型)
実在する資産と価値が連動したトークンです。
法定通貨や貴金属など現実資産の価値と連動するトークン(例:米ドル連動のUSDTやUSDC)が代表例です。実物資産を小口のデジタル資産として扱えるため、新たな投資機会を提供します。
セキュリティトークン(証券型)
証券(株式や社債など)としての性質を持つトークンです。有価証券をデジタル化したもので、利益配当や議決権など株式に似た権利が付与される場合もあります。
法規制の対象であり、適切な許可を得た上で発行・取引されます。
セキュリティトークンを用いた資金調達はSTO(Security Token Offering)と呼ばれ、企業が効率的に資金調達できる手段として注目されています。
ガバナンストークン
分散型プロジェクトの運営に参加するためのトークンです。ガバナンストークンを保有することで、プロジェクトの方針や仕様変更について投票権を得ることができます。
例として、ステーブルコイン「DAI」を運営するMakerDAOのMKRはガバナンストークンで、保有量に応じてプロジェクトの意思決定に影響力を持ちます。
コミュニティ主導の民主的な運営を支える重要なトークンです。
以上のようにトークンには多様な種類があります。それぞれの特徴を理解することで、新しいトークンに出会った際も「これはどのタイプかな?」とイメージしやすくなるでしょう。
DeFi系トークンとは
DeFiとは
DeFi(Decentralized Finance、分散型金融)では銀行など中央の仲介者を介さずに、ブロックチェーン上で貸し借りや取引(スワップ)、資産運用が行われます。
例えば、ユーザー同士が直接暗号資産を交換する分散型取引所(DEX)や、暗号資産を担保に資金を借りられるレンディングサービスなどがあります。これらのプラットフォームで発行・利用されるトークンがDeFi系トークンです。
DeFiの代表例
代表的なDeFiプロジェクトとトークンの例を挙げてみましょう。
Uniswap(ユニスワップ)とUNIトークン
Uniswapはイーサリアム上の分散型取引所(DEX)です。誰でも好きな仮想通貨同士を交換でき、手数料は取引参加者に分配されます。
UNIはそのガバナンストークンで、プロトコルの手数料率変更など重要事項の投票に使われます。また、UNI保有者へのエアドロップ(無料配布)が行われたこともありました。
Aave(アーベ)とAAVEトークン
Aaveは分散型の貸付・借入プラットフォームです。仮想通貨を預けると利息を得られ、借りる側は金利を支払います。
AAVEトークンはガバナンス機能に加え、一定量保有することでローンの手数料割引や清算リスクの軽減といった特典が受けられるユーティリティ要素も持っています。
Compound(コンパウンド)とCOMPトークン
CompoundもAaveと同様の貸し借りプロトコルです。COMPはガバナンス用ですが、Compoundを利用して貸し借りを行うユーザーに対するインセンティブ(報酬)としても毎日分配されています。
この仕組みにより、多くのユーザーが利息+COMP報酬目当てに資金を預け入れ、Compoundの流動性が向上しました。
このようにDeFiトークンはサービス内通貨+ガバナンス報酬として機能するケースが多いです。
DeFiの躍進により関連トークンの価値が急騰したり、逆に市場環境の変化で大きく下落することもあります。
金融商品的な性格上、流動性マイニング(資金提供)などで高利回りを得られる半面、価格変動リスクも高い点には注意が必要です。
NFT系トークンとは
NFTとは
NFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)もトークンの一種で、近年大きな注目を集めました。NFT系トークンとは、その名の通り「唯一無二のデジタル資産」を表すトークンです。
通常の仮想通貨やトークン(ビットコインやERC-20トークンなど)は互いに代替可能(1 BTCは他の1 BTCと同価値)ですが、NFTは一つひとつが固有の価値や情報を持ち、他のトークンで代替できません。
その特性により、デジタルアートやコレクターズアイテムの所有権を表現する用途で爆発的に広まりました。
NFTの代表例
デジタルアート
画家やクリエイターが作品をNFT化して販売できます。
世界的に有名になった例として、デジタルアーティストのBeeple氏がNFTアートを約75億円で落札されたニュースが話題になりました(2021年)。
ゲームアイテム
ブロックチェーンゲーム内のキャラクターやアイテムをNFTとして発行し、プレイヤー間で売買可能にしているケースがあります。
代表例がCryptoKitties(クリプトキティーズ)という猫のキャラクター収集ゲームで、ゲーム内アイテムのNFTが高額で取引され社会現象になりました。
メタバース・土地
仮想空間(メタバース)上の土地や不動産をNFTとして販売するプロジェクトもあります。DecentralandやThe Sandboxといったサービスでは、仮想空間内の区画がNFTで表現され、不動産のように取引されています。
会員証・チケット
イベントの入場券やクラブのメンバーシップをNFTで発行する例も出てきました。
NFTであれば転売履歴も追跡でき、不正コピーも困難なため、チケット転売問題の解決策として期待されています。
このようにNFTは「デジタルな所有権の証明書」として機能します。
所有者や取引履歴がブロックチェーン上に記録されるため、贋作や不正入手を防ぎ、本物の価値を担保できるのです。まさにアートやコレクターズアイテムの世界に革命を起こした技術と言えます。
トークンの購入方法
取引所の選択
まずは信頼できる国内の仮想通貨取引所を選びましょう。使いやすさや取り扱い通貨の種類、手数料などを比較し、自分に合ったサービスを選定します。
日本では Coincheck(コインチェック)や bitFlyer(ビットフライヤー)などが大手として知られており、初心者でも口座開設が簡単です。
口座開設と本人確認
選んだ取引所でアカウント登録を行いましょう。メールアドレスやパスワードを設定し、必要情報を入力します。
その後、運転免許証など本人確認書類の提出が求められます。これは法律上のKYC(本人確認)手続きで、セキュリティのためにも必須です。審査は通常数日以内で完了します。
日本円の入金
口座が開設できたら、自分の取引所口座に日本円を入金します。
銀行振込やクレジットカード、コンビニ入金など取引所によって方法が異なりますが、初心者の方は銀行振込が一般的でしょう。入金が反映されたら、その残高を使って仮想通貨を購入できます。
仮想通貨(トークン)の購入
取引所の売買画面から、購入したい仮想通貨やトークンを選び、数量を指定して購入します。
例えばビットコインやイーサリアムなどの主要コインをまず買い、その後、それらを使って目的のトークン(アルトコイン)に交換することもあります。
取引所によっては日本円で直接買えないトークンもあるため、その場合は一度メジャーな通貨を経由して交換しましょう。
ウォレットでの保管
購入したトークンは取引所の口座にそのまま置いておくこともできますが、長期保有する場合や大きな額になる場合は自分のウォレットに移すことを検討してください。
ウォレットとは、自分だけが管理する暗号資産用の口座のようなもので、スマートフォンアプリ型から専用端末(ハードウェアウォレット)まで種類があります。
自分のウォレットに移しておけば、取引所のハッキングリスクから資産を守ることができます。ただしウォレットの秘密鍵や復元フレーズは厳重に保管しましょう。
以上が基本的な購入手順です。初心者の方は、まずは信頼性の高い国内取引所で少額から始めてみるのが安心です。(例:Coincheckなどで無料の口座開設が可能です)といった公式サイトから口座開設をするとスムーズでしょう。
トークン投資のメリット
大きな成長可能性
仮想通貨市場はまだ新興市場であり、将来的に価値が大きく伸びる可能性があります。実際、過去には発行直後から価格が大幅に跳ね上がったトークンも存在します。
有望なプロジェクトのトークンを早期に保有できれば、高いリターンを得られるチャンスがあるのは魅力と言えるでしょう。
少額から投資できる
トークンは比較的少額(数千円程度)から購入できるものが多く、初心者でも試しやすい点はメリットです。
株式投資などに比べてハードルが低く、資金の一部で新しい分野に触れてみるという投資体験にもつながります。
新しいサービスへの参加
トークンを保有すること自体が、そのプロジェクトのサービスを利用する切符になる場合があります。
たとえばICOで発行されるトークンを購入すれば、そのプロダクトがリリースされた際に実際にサービスを利用できたり、ゲームのトークンならゲーム内で使用できたりします。
またガバナンストークンを持っていれば、プロジェクト運営の投票に参加できるなど、単なる経済的利益以上の体験価値があります。
購入時の注意点
価格変動とボラティリティ
仮想通貨は価格変動が非常に大きいことが知られています。一日のうちに20〜30%以上値動きすることも珍しくありません。
株や為替以上にボラティリティ(変動性)が高いため、短期間で資産が大きく増える可能性がある反面、大きく減少するリスクもあります。
投資した金額が短期間で半減するようなケースもあり得るため、余裕資金で行うことが大前提です。
セキュリティと管理
仮想通貨はデジタルデータなので、ハッキングや盗難のリスクがあります。取引所のセキュリティ対策(2段階認証の設定、パスワード管理など)を徹底し、自分のウォレットを使う際は秘密鍵の管理に十分注意しましょう。
また、「〇〇のトークンを無料であげる」という話は詐欺の可能性が高いので安易に個人情報や秘密鍵を入力しないようにしてください。
プロジェクトの信頼性と規制状況
新規発行のトークンやICOに投資する際は、そのプロジェクトが信頼できるか見極めましょう。
公式サイトやホワイトペーパーを確認し、実態のない詐欺的な案件を避けることが大切です。トークンやICOに関する法整備はまだ十分とは言えず、最終的には自己責任での情報収集と判断が求められます。
以上の点を踏まえ、焦らず冷静に投資判断を行いましょう。少しでも不明点がある場合は無理に取引せず、まずは知識を身につけることが大切です。
身近に詳しい人がいれば相談したり、交流できるコミュニティに参加して情報収集するのも良いでしょう。
なお、仮想通貨の売買益には税金(雑所得)が課される点も念頭に置いておきましょう。
将来性と最新動向
実物資産のトークン化が進展
不動産や債券、美術品といった現実世界の資産をブロックチェーン上でトークンとして扱う「資産のトークン化」が加速しています。
2024年には現実資産(RWA)トークン市場が前年から60%以上拡大し、不動産や債券など実物資産を小口のデジタル証券として扱う事例が増えました。
大手金融機関もこうした分野に参入しており、伝統的な金融と暗号資産の融合が進みつつあります。
企業や銀行の参入
仮想通貨やブロックチェーン技術に対し、大企業や銀行も本格的に取り組み始めています。
日本でも三菱UFJ信託銀行が商取引向けの円建てステーブルコイン発行を計画しているとの報道があり、ブロックチェーンを使った決済やデジタル証券の分野でメガバンクが動き出しています。
海外でも仮想通貨決済を導入する企業が出始めており、トークンが従来の経済圏に少しずつ溶け込み始めています。
NFT・メタバースの新展開
NFTはブーム後の次の段階として実用性重視の流れに入っています。
例えばNFTを持っていると参加できるリアルイベントやバーチャル体験、オンラインサービスのプレミアム機能がアンロックされる仕組みが増えています。
また、メタバース(仮想空間)上の土地やアイテムにNFTが使われ、ユーザーが経済活動を行うケースも出てきました。
ゲームと金融が融合したGameFi(ゲームファイ)と呼ばれる分野も成長しており、遊びながらトークンを稼げるゲームが登場しています。
分散型金融の進化
DeFiの世界でもユーザビリティ向上や伝統金融との連携が進んでいます。高額な手数料(ガス代)といった課題に対処するため、イーサリアムのレイヤー2技術などでより安価かつ高速な取引が可能になってきました。
また、中央集権型金融(CeFi)とDeFiをつなぐサービスも登場し、機関投資家も参入しやすい環境が整いつつあります。
規制と市場の成熟
各国で仮想通貨に関する法整備も進みつつあります。
日本では2022年にステーブルコインの発行や暗号資産管理に関する法律が整備され、EUでも包括的規制(MiCA)が始まるなど、市場の透明性と安全性を高める動きが見られます。
このように、トークンを取り巻く環境は常に進化しています。新しいニュースや技術動向をウォッチし続けることで、将来のチャンスを掴みやすくなるでしょう。
まとめ
仮想通貨のトークンには、通貨型・ユーティリティ型・セキュリティ型・ガバナンストークン・NFTなど、実に多種多様な種類があります。初心者の方はまず各種類の基本的な特徴をつかみ、関心のある分野から学んでみると良いでしょう。
投資面ではリターンの可能性とリスクが表裏一体であるため、メリットと注意点の両方を理解することが重要です。特に初めは無理のない範囲で少額から始め、相場の変動やプロジェクト情報の収集に慣れることをおすすめします。
幸い、仮想通貨業界はコミュニティも活発で、情報交換が盛んに行われています。私たちのオンラインサロンでも、初心者から経験者まで交流しながらトレード戦略や最新情報を共有しています。独学で不安な方は、ぜひそうしたコミュニティも活用して楽しみながら知見を深めてみてください。
トークンの世界はまだ発展途上で、今後予想もつかない新たな潮流が生まれる可能性があります。常に最新動向にアンテナを張りつつ、ルールを守って安全に取引し、この将来性豊かな分野と上手に付き合っていきましょう。