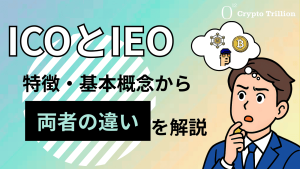仮想通貨ICOとIEOの違いとは?仕組みから誕生の背景などわかりやすく解説!
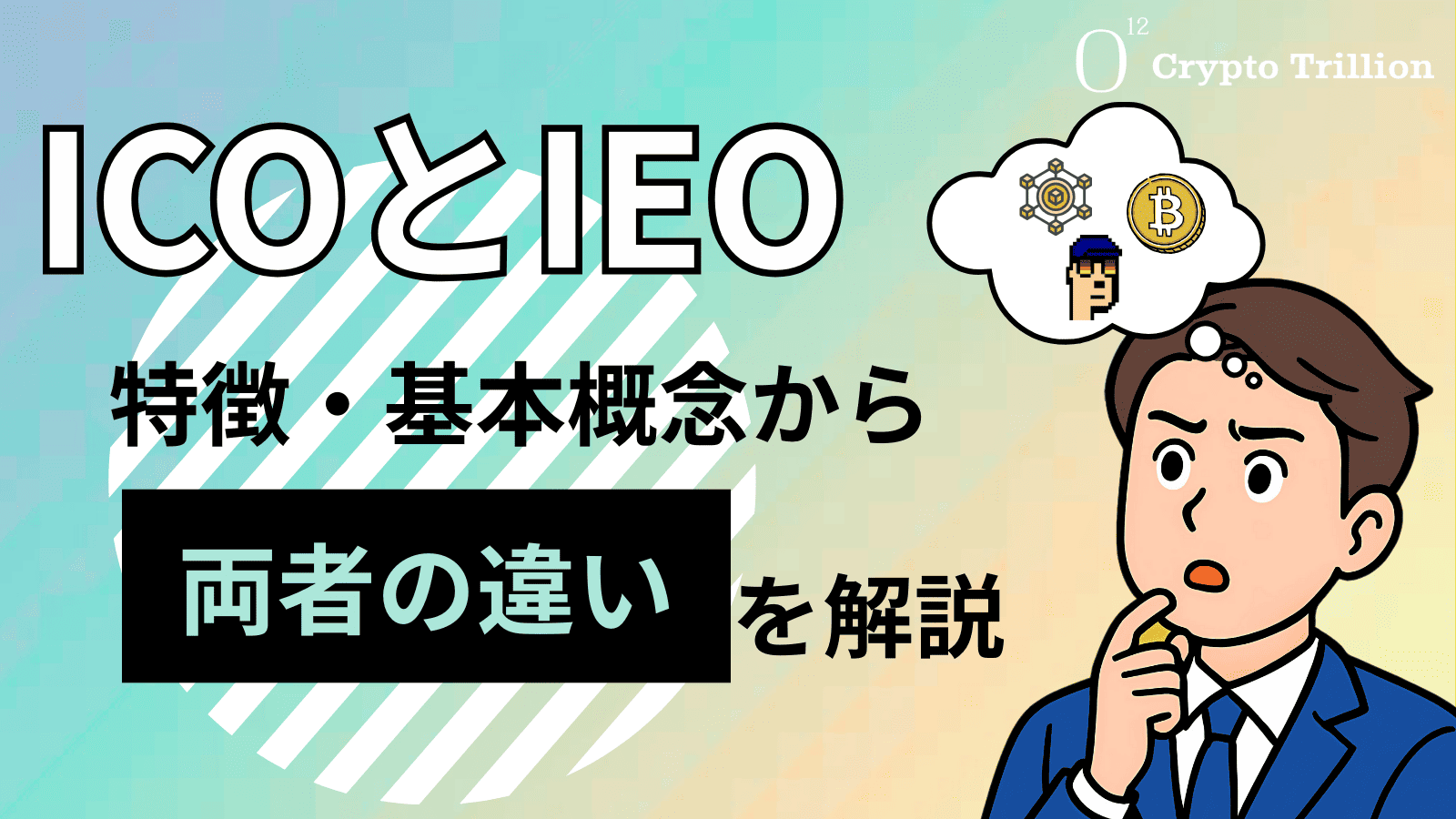
プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- ICOは企業やプロジェクトが独自のトークンを発行し、投資家やユーザーに販売する資金調達法
- プロジェクトがホワイトペーパーを公開し、一定期間に仮想通貨と引き換えに独自トークンを販売
- 実際、EthereumやFilecoinなど著名プロジェクトもICOで資金調達し成功を収めた
- 2017年ICOブーム時には「ホワイトペーパーを掲げただけ」の案件が乱立し、約8割が詐欺と判定された
- IEOは暗号資産の発行体が仮想通貨取引所が仲介して資金調達する方法
- ICOで問題となった詐欺の多発や信頼失墜を受け、より安全な代替策として2019年頃から登場
- 取引所による上場審査やKYC(本人確認)の実施により、プロジェクトの信頼性が一定担保される
- 購入したトークンは即座に取引所で売買可能となるため、流動性が確保されやすい
- ICOはスマートコントラクト上、IEOは取引所が提供する専用プラットフォーム上で実施される
- ICOは誰でも実施可能だが、IEOは取引所がプロジェクトの審査をするので敷居がたかい
- ICOはウォレットがあれば実施できるが、IEOは対象取引所での口座開設や本人確認が必須
 Trader Z
Trader ZICO(Initial Coin Offering)は、2017年〜2018年にかけて異常な盛り上がりを見せました。
しかし…
・実態のないプロジェクトが続出
・トークンを売るだけ売って開発放棄(通称「ラグプル」)
・投資家は保護されず、損を被るだけのケースも多数
この結果、「ICO=詐欺の温床」という認識が広まり、市場の信頼はガタ落ちしました。



ICOが荒れに荒れたことで、次に求められたのは 「信用の担保」と「投資家の保護」です。
そこで登場したのが IEO(Initial Exchange Offering)です。
IEOでは、
・取引所がプロジェクトの内容を審査
・KYC(本人確認)やAML(マネロン対策)を実施
・上場が確約されているため流動性の担保がある
・一定の透明性・信頼性が確保される
つまり、投資家保護+プロジェクトの品質向上+市場の健全化を同時に実現するスキームとしてIEOが広まりました。


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
ICO(Initial Coin Offering)とは?
ICOの基本的な仕組み
ICOとは「イニシャル・コイン・オファリング」の略で、新規の暗号資産(コインやトークン)の販売による資金調達方法を指します。
企業やプロジェクトが独自のトークンを発行し、投資家やユーザーに販売して資金を募る点で、株式の新規公開(IPO)に似た概念です。ただしIPOが株式を対象とするのに対し、ICOではブロックチェーン上のトークンを対象とします。
プロジェクトチームがホワイトペーパー(事業計画や技術仕様を書いた文書)を公開し、一定期間に仮想通貨(主にETHやBTCなど)と引き換えに独自トークンを販売します。
販売はプロジェクトの公式サイトや専用プラットフォーム上で行われ、多くの場合スマートコントラクトによって自動化されています。
ICOのメリット
調達した資金はプロジェクト開発やマーケティングに充てられます。
投資家側は将来そのトークンの価値が上がることを期待して購入します。早期に有望プロジェクトのトークンを入手できるチャンスとして注目されました。
企業にとってはベンチャーキャピタルに頼らず、誰でもグローバルに出資を募れる利点があります。
実際、EthereumやFilecoinなど著名プロジェクトもICOで資金調達し成功を収めました。
ICOのデメリットとリスク
規制当局の監視が及びにくく、詐欺の温床になりやすい点が大きな課題です。
2017年のICOブーム時には「ホワイトペーパーを掲げただけ」のような玉石混交の案件が乱立し、その約8割が詐欺と判定されたとの報告もあります。
実際、Pincoin(被害総額約6億6000万ドル)やAriseBank(約6億ドル)など大型詐欺案件も発覚しました。
こうした背景から、ICOには非常に高いリスクが伴います。米国証券取引委員会(SEC)は、ICOによる資金調達の多くが未登録証券の違法販売に当たるとして摘発を強化しました。
また開発チームが資金調達後にプロジェクトを放棄して消える例も相次ぎ、2018年以降ICOは急速に下火になりました。
IEO(Initial Exchange Offering)とは?
IEOの登場背景
IEOとは「イニシャル・エクスチェンジ・オファリング」の略で、暗号資産取引所が第三者としてプロジェクトを審査し、取引所を通じてトークンを販売する仕組みです。
ICOで問題となった詐欺の多発や信頼失墜を受け、より安全な代替策として2019年頃から登場しました。
ICOバブル崩壊後の反省と信頼再構築の文脈の中から自然発生的に生まれた、いわばWeb3資本市場のリカバリー戦略として登場したものです。
IEOの仕組みと特徴
プロジェクトは提携する暗号資産取引所に対してトークン販売を委託します。取引所はプロジェクトを審査し、承認された場合に自社のプラットフォーム上でトークンの販売を実施します。
投資家はその取引所の口座を通じて新トークンを購入でき、販売後は即座に同取引所に上場され、取引可能になるのが一般的です。
取引所による上場審査やKYC(本人確認)の実施により、プロジェクトの信頼性が一定担保されると期待されています。
IEOでは販売前に取引所側でホワイトペーパーやプロジェクトの実態確認が行われ、明らかな詐欺案件の排除に努めています。
投資家にとっては取引所の既存アカウントから直接購入できる手軽さがあります。
また購入したトークンは即座に取引所で売買可能となるため、流動性が確保されやすいのも利点です。プロジェクトにとっても、取引所が持つマーケティング力や多数のユーザー基盤を活用できるメリットがあります。
IEOの課題と懸念点
ただしIEOにも課題はあります。取引所での審査通過には手数料や一定の条件が課され、資金力や実績のあるプロジェクトでないと参加しにくいとも指摘されています。
また取引所自体がプロジェクト選定のゲートキーパーとなるため、優良プロジェクトでも取引所次第でチャンスを得られないケースがあります。
さらに根本的にはICOと同様に、トークン自体の将来価値が保証されるわけではない点に注意が必要です。
ICOとIEOの違いとは?
| 項目 | ICO | IEO |
|---|---|---|
| 主催者 | プロジェクトチーム自身 | 暗号資産取引所 |
| 販売場所 | プロジェクトのWebサイト等 | 取引所のIEOプラットフォーム |
| 信頼性 | 低い(自己責任) | 高い(取引所の審査あり) |
| 上場保証 | なし | 基本的に上場確約 |
| 規制・透明性 | ほぼなし | 比較的高い |
| 詐欺リスク | 高い | 低いがゼロではない |
実施プラットフォームの違い
ICOはプロジェクト自身が用意した公式サイトやスマートコントラクト上で実施されます。
これに対してIEOは、仮想通貨取引所が提供する専用プラットフォーム上で行われます。
IEOでは取引所が販売をホストする役割を担っており、その点が大きな違いといえるでしょう。
審査と信頼性の比較
ICOは基本的に誰でも実施できるため、審査がない代わりに質の低いプロジェクトが混在する傾向が強くありました。
一方でIEOは、取引所がプロジェクトの審査や実態確認を行ったうえで販売を許可するため、投資家にとっての安心感が高まります。
ただし、審査があるからといってすべてのリスクが排除されるわけではありません。
参加条件とコストの違い
ICOはウォレットさえあれば誰でも参加できるケースが多く、地域制限も少ない場合がありました。
一方、IEOは対象取引所での口座開設やKYC(本人確認)が必須となることが一般的です。
また、プロジェクト側から見ても、ICOは直接資金を受け取れますが、IEOでは取引所に対する手数料や報酬の支払いなどが発生します。
ICOとIEOが注目されるようになった背景
ICOブームとその反動
ICOが注目されたのは2016年から2017年にかけてです。
とくに2017年はICOによって世界中から莫大な資金が集まり、「次のビットコインを探せ」という投資熱が過熱していました。
Ethereumが登場し、ERC-20トークンを誰でも発行できるようになったことがこのブームを後押ししました。
しかし、熱狂の裏で多くの詐欺的プロジェクトや未完成の案件が乱立し、最終的には多くの投資家が損失を被りました。
2018年に入ると仮想通貨全体の相場が暴落し、ICO市場も急速に冷え込みます。
各国の規制当局もICOを違法な証券販売とみなし、法的措置を取り始めたことで、ICOブームは事実上終焉を迎えました。
IEOの台頭とその後
ICOの問題点を受けて登場したのがIEOです。2019年、バイナンスが最初のIEO案件をLaunchpadで販売し、数分で完売したことで業界の注目を集めました。
その後、各大手取引所がIEOプラットフォームを立ち上げ、人気を博します。
一時は抽選や先着方式での購入が激化し、価格が上場直後に急騰することも珍しくありませんでした。
ただし、こうした熱狂は長くは続かず、2020年以降は市場の沈静化や、分散型取引所によるIDO(Initial DEX Offering)といった新しい形のトークン販売に注目が移り始めました。
ICOとIEO実際にあった事件・トラブル事例
ICOを巡る主なトラブル事例
ICOで多く見られた問題は、詐欺的なプロジェクトの横行です。
実体のないプロジェクトが壮大なホワイトペーパーを掲げて資金を集め、そのまま逃げてしまうような「エグジットスキャム」が頻発しました。
代表例として、ベトナム発のPINCOINや、米国のAriseBankがあり、どちらも数億ドル規模の被害を出しました。
詐欺でなくとも、開発が頓挫してプロジェクトが自然消滅する例も多く見られました。
たとえばSNS「Cyworld」はトークンを発行して再起を図りましたが、結局サービスは閉鎖され、トークンは無価値となりました。
また、ハッキングによる被害も発生しています。The DAO事件では、スマートコントラクトの脆弱性を突かれ、数千万ドル相当のETHが流出しました。
この事件はEthereumのハードフォーク(EthereumとEthereum Classicの分裂)を引き起こすほど大きな影響を与えました。
さらに、SEC(米国証券取引委員会)による取り締まりも強化され、違法ICOとみなされたプロジェクトには罰金や資金返還命令が下されています。
たとえばBitClaveは、証券登録なしにICOを実施したとして摘発され、数百万ドル規模の賠償に応じました。
IEOを巡る主なトラブル事例
IEOにおいても、プロジェクトが失敗したり、想定された成果が出なかったりすることは珍しくありません。
韓国のCyworldのトークン販売もIEO形式でしたが、最終的にサービスは終了し、トークンはほぼ無価値となりました。
また、IEOで購入されたトークンが上場直後に急騰し、その後短期間で暴落する「ポンプ・アンド・ダンプ」のような動きも問題視されています。
こうした変動にうまく対応できなかった投資家が大きな損失を被ることもありました。
IEOは取引所主導であるため、販売プロセス中の技術的トラブルや、抽選方式の不透明さが問題になることもあります。
さらに、取引所自体がトラブルを抱えた場合には、購入したトークンの流通や取引に支障が出るリスクも否定できません。
IEOだからといってすべてのリスクが排除されるわけではなく、特に証券規制の観点ではICOと同様の問題を抱えています。
米国ではIEOであっても無登録での証券販売に該当する可能性があるとされ、投資家向けに注意喚起が出されました。
ICOとIEO注目のニュース・動向
香港と欧州での規制の変化
2023年末、香港ではICOに再び注目が集まりました。
過去のICOバブルや詐欺事件の記憶がある中で、証券業協会が当局に対し、「適切な規制のもとでICOを実施できるポータルサイトの創設」を提案したのです。
この動きは、ICOを完全に否定するのではなく、法的な枠組みの中で健全に実施できる可能性を模索する姿勢として受け止められました。
一方、欧州では2024年末に「MiCA(暗号資産市場規制)」が施行され、暗号資産の公開販売に関する統一ルールが導入されました。
ICOやIEOを行う際には、ホワイトペーパーの提出や投資家への情報開示が義務化されるなど、透明性を重視した枠組みが整備されつつあります。
これにより、欧州ではより安心して参加できるトークン販売の環境が整ってきました。
日本国内のIEO事例
日本でもIEOに関する動きが加速しています。2021年、コインチェックが国内初のIEOとしてPalette Token(PLT)を販売し、約10億円の調達に成功しました。
これは、金融庁の認可を受けた初のIEO案件として大きな話題となり、その後も日本の仮想通貨取引所ではIEOの取り扱いが徐々に拡大しています。
国内ではIEOを行う際の審査が厳しく、上場までに多くの手続きを要しますが、その分プロジェクトの信頼性も高く保たれる傾向にあります。
日本市場では、IEOが信頼できる資金調達手段として徐々に定着しつつあるといえるでしょう。
その他の資金調達手法との競合
IEO以外にも、新たな資金調達手法が登場しています。特に分散型取引所(DEX)上で行うIDO(Initial DEX Offering)は、中央集権的な取引所を通さず、より分散的な形でトークンを販売できる手段として注目されました。
これにより、誰でもグローバルに参加できる自由な市場が生まれています。
また、NFTの販売やエアドロップといった手法を用いた資金集めも広がりを見せています。ただし、詐欺的な案件も紛れ込みやすく、参加者側には一層のリテラシーが求められています。
その点において、取引所が関与するIEOの信頼性が相対的に高く評価される傾向は続いています。
ICOとIEO今後の将来性と展望
規制と信頼性の向上
ICOやIEOに対する規制は、過去の失敗を踏まえて各国で整備が進んでいます。
とくに欧州のMiCA規制や、香港のポータル構想、日本国内の認可制IEOなどは、投資家保護と技術革新のバランスを取りながら、より健全な市場の形成を目指す動きといえるでしょう。
今後は、信頼性の高いプロジェクトが制度に則って資金を集める場として、IEOがますます活用されていく可能性があります。
これにより、投資家が安心して参加できる資金調達手法としての地位が確立されるかもしれません。
成功例の増加と投資家の成熟
ICOやIEOを経て成功したプロジェクトは、実際に多数存在します。
EthereumやCardanoなどはICOからスタートし、今や業界を代表する存在となりました。
こうした成功例を見て、多くの投資家が「次のイーサリアム」を求めて新たなプロジェクトに注目しています。
ただし、過去に痛い目を見た投資家が多かったこともあり、現在ではプロジェクトの中身やチーム、法的な体制などをより慎重に調査する姿勢が広がっています。
短期的な利益だけを追わず、中長期的な視点で判断する投資家が増えているのは、市場の成熟の証といえるでしょう。
今後のIEO市場の展望
バイナンスやOKXをはじめとする大手取引所は、引き続きIEOの開催を定期的に行っています。
トークンの販売だけでなく、マーケティングや技術支援も含めて取引所が関与することで、プロジェクトにとっては信頼性と露出の両方を得られる仕組みが整っています。
将来的には、IEOがスタートアップにとっての「登竜門」として機能し、Web3時代のベンチャー支援インフラとなっていく可能性もあります。
参加する投資家も、まずはIEO案件をチェックしてから判断する、というスタイルが主流になっていくかもしれません。
リスクとの向き合い方
もちろん、どれだけ制度や仕組みが整っても、リスクがゼロになることはありません。
どんなに優れたプロジェクトでも、技術や市場の変化、経営上の判断ミスなどで失敗に終わる可能性は常にあります。
大切なのは、プロジェクトの将来性や透明性だけでなく、自身のリスク許容度や投資戦略に照らし合わせて慎重に判断することです。
「IEOだから安心」「審査済みだから大丈夫」と思い込むのではなく、最終的な意思決定は自分の責任で行う必要があります。
ICOとIEOの違いとは?まとめ
まとめると、ICOとIEOは今後も仮想通貨業界における資金調達手段として進化し続けるでしょう。
規制の枠組みの中で透明性と信頼性が高まれば、優良プロジェクトが資金を集めやすくなり、投資家も適切なリスクテイクによって恩恵を受ける可能性があります。
ただし「絶対に儲かる」魔法の仕組みでは決してありません。
初心者の方は特に、安易に飛びつかず十分な情報収集と理解に基づいて判断することが大切です。
本記事の解説が、ICOやIEOについて正しく理解し活用する一助になれば幸いです。