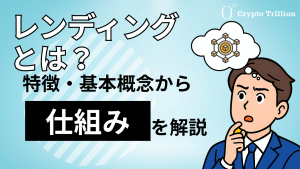仮想通貨レンディングとは?仕組みやステーキングとの違いをわかりやすく解説!
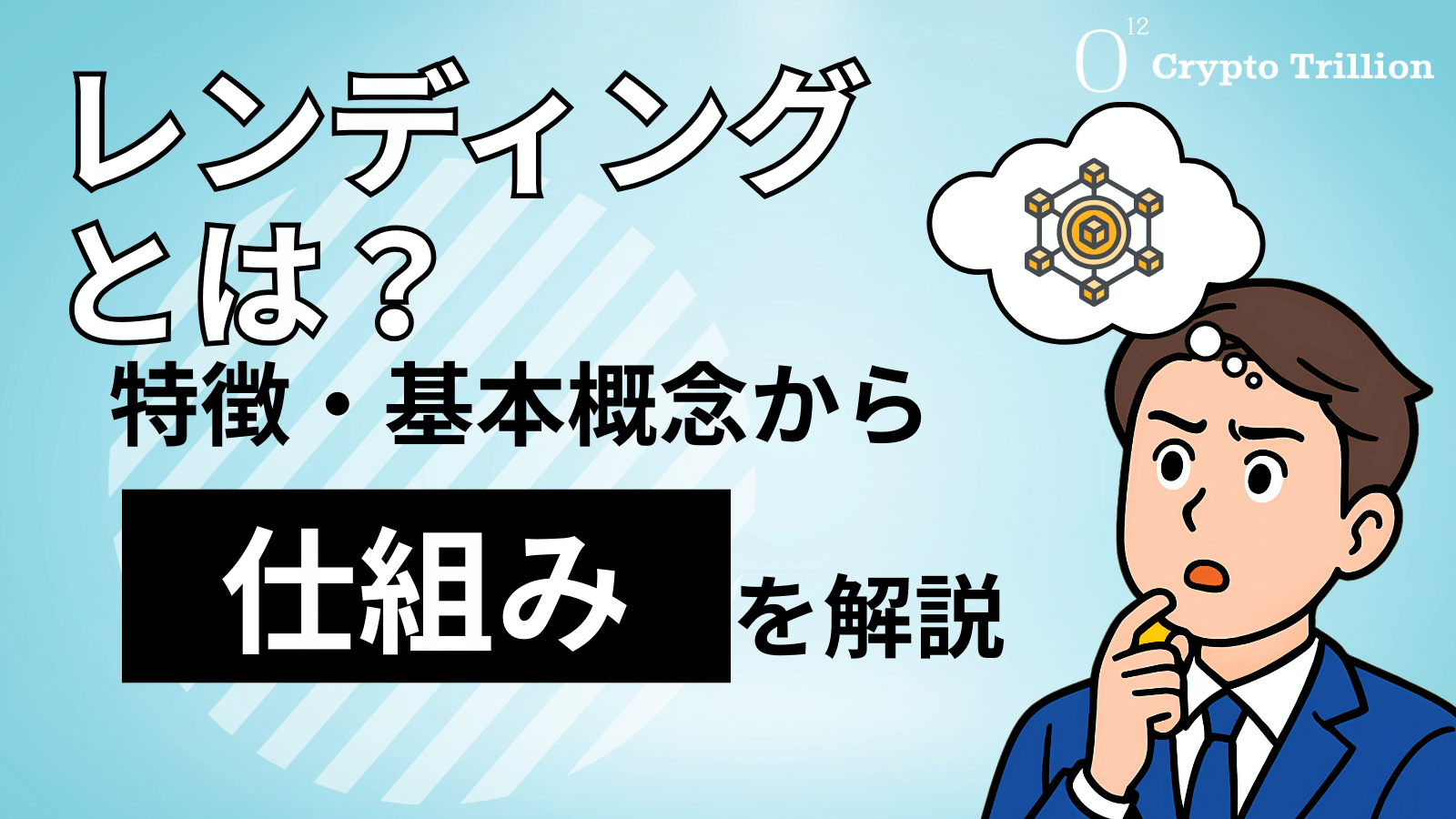
プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- 仮想通貨レンディングは保有している暗号資産を貸し出して利息収入を得る仕組み
- 銀行預金や債券など従来型の運用手段と比べて利率が高めに推移する傾向
- 資産を長期間ホールドする投資家にとっては、追加の収入源となる可能性が高い
- 銀行預金のように決済や送金を伴わない形でも利益を狙え、利率も比較的高い
- ステーキングはブロックチェーンの承認作業に参加し、仮想通貨を報酬として受け取る仕組み
- 大きな利益を狙える可能性がある一方、相場変動やプラットフォームの信用リスクなど注意点も多い
- 例えば、BTCを貸し出して利息を受け取れる一方、借り手側の破綻が起きた場合に元本を失う可能性
- 資産を長期間ホールドする投資家にとっては、追加の収入源となる可能性が高い
- 預けている通貨の量は増えるが預けている通貨自体の価格が下がる可能性がある
- プラットフォームには、中央集権型(CeFi)と分散型(DeFi)の両方にさまざまなプロトコルが存在
- CeFi:世界最大の取引所Binanceが提供するレンディングサービスや、LINE BITMAXなど
- DeFi:Aave、Compound、MakerDAO、JustLendなどが代表格として挙げられる
 Trader Z
Trader Z一般的な銀行預金の年利率が大体0.001〜0.2%なのに対し、仮想通貨レンディングにおける平均的な年利率は2〜10%、高いもので20%以上を超えます。



仮想通貨を預けるだけで利息を受け取れるという発想は一見魅力的です。銀行預金より高い利率に期待が集まり、金融市場に不安が広がる時代の代替手段としても注目されています。
ただし、取引所や専業レンディング企業が相次いで破綻した事例もあるため、利用時にはサービスの運営体制やリスク管理を十分に調べることが大切です。


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
仮想通貨レンディングの仕組み
中央集権型(CeFi)の基本構造
中央集権型レンディングは、企業や取引所など特定の管理主体がユーザーと借り手を仲介します。
利用者は自分の仮想通貨をサービス運営企業に預け、その企業が別のユーザーや金融機関などに貸し出す形です。
手続きや本人確認が比較的わかりやすく、法定通貨とのやり取りもスムーズな場合が多いです。
ただし、運営企業自体の破綻や不正運用に巻き込まれるリスクがあるため、信頼性の確認は必須といえます。
分散型(DeFi)の基本構造
分散型レンディングは、ブロックチェーン上のスマートコントラクトを利用して貸し借りを行う仕組みです。
中央に管理する企業が存在せず、ユーザー同士が直接資産を貸し借りできます。
プログラムが自動的に利率を設定し、担保が一定水準を下回ると清算が行われます。
過去にはハッキングやコントラクトのバグにより、預けた資産が流出した事例も報告されました。
透明性に優れる半面、技術リスクへの対策が欠かせない点が特徴です。
仮想通貨レンディングを利用するメリットとリスク
レンディングを活用するメリット
銀行預金より高い金利が得られるかもしれない点が強みです。
特に相場が好調な時期には、高い需要を背景に利率が上昇しやすい傾向があります。
たとえば、ビットコインを売却せずにステーブルコインを借りるなど、資産を手放さずに流動性を確保できる利点が挙げられます。
投資家にとっては、値上がり期待を維持しながら一時的な資金調達が可能になる場面もあるでしょう。
押さえておきたいリスク
相場が急落した場合は担保割れが起き、貸し手が思わぬ損失を被る可能性があります。
中央集権型プラットフォームでは運営企業が破綻した際に資金が凍結される事例もありました。
分散型のDeFiにおいても、スマートコントラクトの脆弱性が原因で預けていた資産を盗まれるリスクを否定できません。
信用力やセキュリティ、さらにはサービスの運営実績をしっかり確認しながら利用を検討することが求められます。
仮想通貨レンディングとステーキングの違い
仕組みと報酬源の比較
レンディングは貸し出し先から利息を受け取る仕組みです。
借り手が多いほど金利が上昇する傾向があり、運営会社(CeFi)や自動化されたプロトコル(DeFi)が仲介します。
一方、ステーキングはブロックチェーンの承認作業に参加し、新規発行されたトークンなどを報酬として受け取るかたちです。
対象となる通貨が限られ、用途がブロックチェーンの維持に直結している点が大きな特徴といえます。
リスク・リターンの違い
ステーキングは比較的リスクが低めで、報酬率も安定しやすいと考えられます。
これに対して、レンディングは利率が大きく変動する場合があり、短期的に高い利息を獲得できる可能性がある半面、市場急落時に大きく損失を被るケースも想定されます。
リスク許容度や運用目的に合わせて選択するのが無難です。
主要な仮想通貨レンディングサービス
| プラットフォーム | 評判・実績 | 年利(目安) |
|---|---|---|
| Binance Earn (CeFi) | 世界最大級の取引所。利用者数が多く、信用力は高いとみなされがちだが、過去にハッキング事件の報道もあり。 | 3〜10%程度(通貨・時期により変動) |
| Nexo (CeFi) | 欧州を中心に実績を積んでいる。米国撤退など地域差があり、利用制限に注意。 | 5〜15%程度(通貨とNEXO保有量次第) |
| Ledn (CeFi) | カナダ拠点で透明性を重視。ビットコインとステーブルコインに特化。 | 3〜8%程度(BTC・USDCのレンディング) |
| Aave (DeFi) | DeFiレンディングの代表格。多チェーン対応(Ethereum, Polygon, Avalanche等) | 0.5〜6%程度(主要通貨) 需要が高い時は10%超も |
| Compound (DeFi) | Aaveと並ぶ分散型プロトコルの草分け。 | 1〜5%程度(主要通貨) 流動性により変動 |
| MakerDAO (DeFi) | ステーブルコインDAIを発行するプロジェクト。 | ETHなどを担保にDAIを借りる仕組みにつき、 利率(安定化手数料)は1〜8%程度が一般的 |
代表的なCeFiプラットフォーム
暗号資産取引所が自社サービスとしてレンディング機能を提供する事例が増えています。
利用者は取引所にアカウントを持っているため、追加の登録作業が少なく始めやすい点が利点です。
しかし、運営企業が信用不安に陥ったり、突然サービスが停止する可能性はゼロではありません。
事前に企業の財務状況やセキュリティ対策をチェックする姿勢が大事です。
注目のDeFiレンディングプロトコル
代表格として、AaveやCompound、MakerDAOなどがあげられます。
これらはイーサリアムなどのブロックチェーン上で動作し、ユーザー同士が直接資金を貸し借りしています。
貸し出し可能なトークンの種類が多く、利率も需要と供給によって決まるため、リアルタイムで変動していく点がおもしろいところです。
金融機関が仲介しないため、人為的な制限や撤退リスクが少ない反面、システム上のバグやハッキングリスクには十分注意が必要です。
仮想通貨レンディングが注目される理由
高利回り・流動性の魅力
特に人気の通貨やステーブルコインを貸し出すと、銀行預金を大きく上回る年利を得られるかもしれません。
仮想通貨の価格変動が急激なため、借り手が担保を追加したりポジションを清算したりといった動きが頻繁に起きます。
それが市場の流動性を高め、結果として貸し手の利回り上昇につながる仕組みです。
相場が好調な時期に正しく運用すれば、高い利益率を狙える可能性は否定できません。
金融不安や規制強化との関係
銀行が続けて破綻する事例が出た際に、資産を自己管理できる手段に注目が集まることがあります。
分散型レンディングは中央の管理者に依存しない点が評価される一方、法令上の保護が弱い場面があるため、規制当局の目が厳しくなっています。
アメリカの証券取引委員会(SEC)によるサービス停止や罰金支払いの例も報じられており、今後はライセンス制や資産の保全義務など新しいルールの導入が加速していくかもしれません。
仮想通貨レンディングの注目ニュース・トピック
CeFi業界の再編と破綻事例
経営難に陥った事業者がユーザー資産を凍結し、返還が困難になるケースが報告されました。
こうした破綻をきっかけに、ユーザーは自分の資産をどこに預けるのかをより厳格に見直す傾向が出ています。
一方で一部の企業は新たな資金調達に成功し、再出発を図る動きも報じられました。
今後は信用できるプレイヤーが生き残り、寡占化が進むかもしれません。
DeFiレンディングの成長と技術アップデート
分散型プロトコルはハッキング被害が課題になる一方、システム更新による防御力強化が続けられてきました。
担保管理や清算機能も改良され、相場急変時に備えた仕組みが徐々に整備されています。
銀行破綻が目立ったタイミングで資金がDeFiに流入し、総預入額が回復する現象も観察されました。
使い勝手の向上やガバナンストークン配布の新制度など、ユーザー獲得策も活発になっています。
最新の規制動向と市場への影響
アメリカではレンディングサービスを証券とみなす判断が増えており、サービス停止を余儀なくされる事業者が出ています。
欧州連合ではMiCA規則が成立し、ステーブルコインを含む暗号資産全般をより明確に監督する方針が示されました。
日本でも金融庁の認可を得た上で事業を行うプラットフォームが存在し、カストディ体制や資金決済法との整合性がポイントになると考えられます。
今後は各国の規制がどのように整備されるかが、市場の成長に影響を与える要因として注目されるでしょう。
仮想通貨レンディングを始める流れ
口座開設・ウォレットの準備
中央集権型を利用するなら、まずは対応サービスのアカウントを作り、本人確認を完了する手順が必要です。
分散型の場合はウォレットを用意し、ネットワーク手数料などの仕組みを理解する必要があります。
いずれの方法でも秘密鍵やパスワードの管理は徹底して行うことが大切です。
サービス選択のポイント
運営企業やプロトコルの評判と実績を確認するとともに、年利や担保管理の仕組み、清算リスクの低減策などを比較します。
カスタマーサポートやガバナンストークンの発行形態もサービスによって異なります。
法定通貨の引き出しに対応しているかどうかも考慮すれば、いざというときに資金を動かしやすくなるでしょう。
運用開始時の注意点
実際に仮想通貨を預ける際には、どの通貨を貸し出すかや、どのくらいの金額を投入するかを決めることになります。
無理のない範囲で少額から始めるのが無難かもしれません。
予期せぬ相場急落やシステム障害に備えて、値動きを定期的にチェックする心構えも必要です。
まとめ
仮想通貨レンディングは、保有資産を売却せずに利息報酬を狙える可能性がある一方、価格変動リスクや運営者の破綻リスクなど注意点を伴うサービスです。
中央集権型なら手続きが簡単な反面、運営企業の信用に依存する部分が大きいと言えます。
分散型であれば透明性が高い一方、スマートコントラクトのバグなど技術的な問題に気を配る必要があります。
結論として、仮想通貨レンディングは高めの利回りを期待できるかもしれませんが、絶対に安全というわけではありません。
事前に自分が抱えるリスク許容度を見極めたうえで、企業やプロトコルの信用調査、利用規約や規制情報の確認を徹底しながら取り組むことが重要です。
投資初心者であっても、基本的な仕組みや市場の実態を理解し、資産を保護する対策を講じることで、より安心してレンディングサービスを活用できるでしょう。