
マークル木(マークルツリー)とは?ブロックチェーンで重要視される理由を徹底解説!
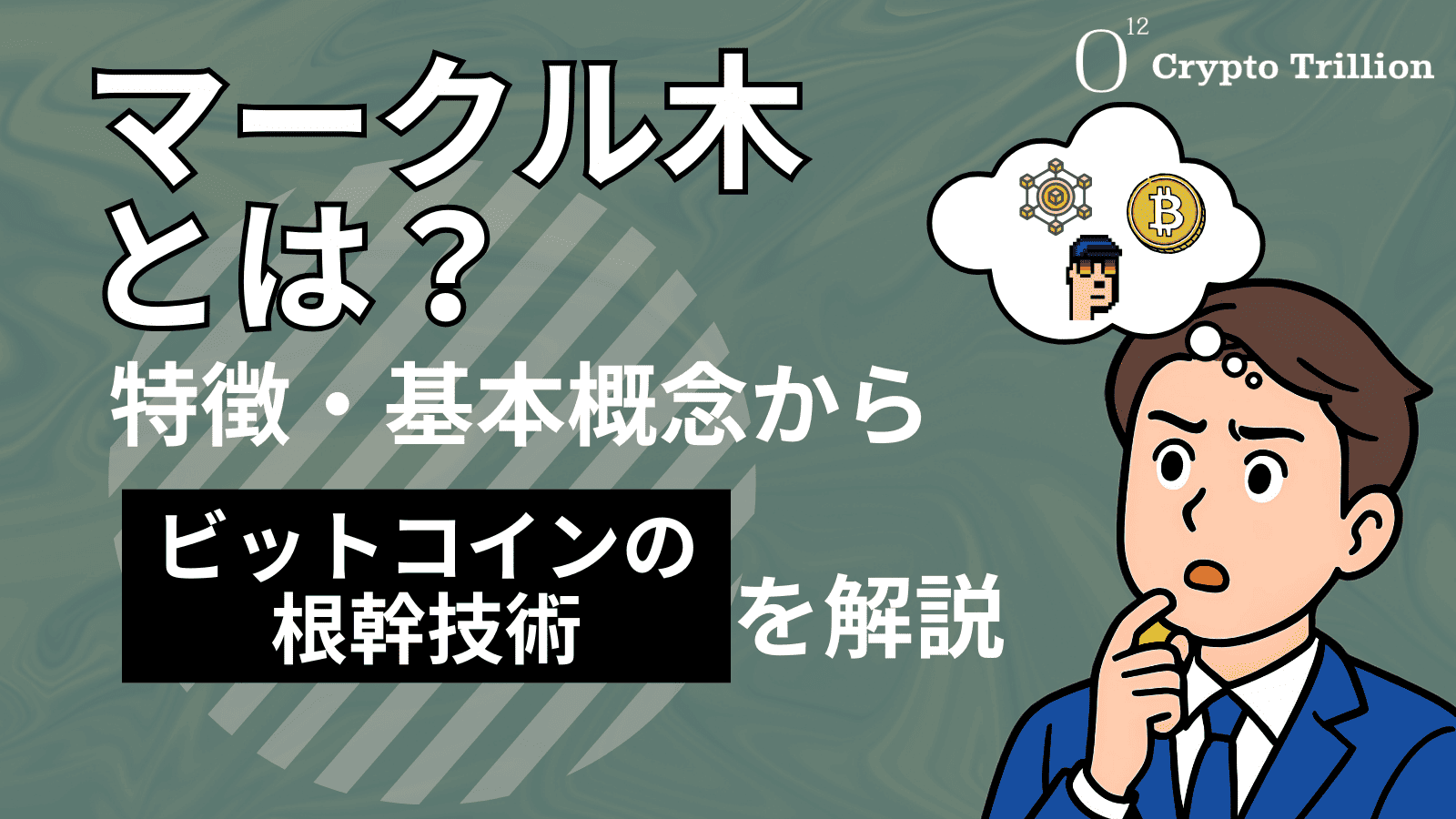
プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- マークル木は複数のデータをまとめてハッシュ化し、改ざんや不正を素早く検知する仕組み
- ビットコインやイーサリアムなど、主要なブロックチェーンの安全性と効率性を支える根幹要素
- 葉と呼ばれる最下層のノードにあるデータそれぞれのハッシュ値を上位へと段階的にまとめていく形が特徴
- 1970年代に生まれ、ハッシュ関数や公開鍵暗号の発展とともに理論的な基盤を築いてきた
- Proof of Reserves(準備金証明)やVerkle木など、透明性の確保や次世代のスケーラビリティ手法としても注目
- ある特定のトランザクションがブロックに含まれているかどうかを最小限のデータだけでチェックできる
- マークル木は「ハッシュ関数」という暗号的な処理を使って、次のように構成される:
- 1. トランザクション(取引)データをハッシュ化(暗号的に圧縮)
- 2. ハッシュ化されたデータを2つずつペアにし、それらをさらに合成して再びハッシュ化
- 3. この処理を繰り返し、最終的に1つのハッシュ値(=マークルルート)が得られる
- 「改ざんが不可能な取引台帳」であるブロックチェーン、その信頼性を裏付けるのがマークル木の存在
- 1件の取引が正しく記録されているかを、マークルルートと一部のハッシュだけで検証できる
- 1,000件あろうが10,000件あろうが、検証に必要な情報量はたったの数十バイト程度
- どれか1件でも改ざんされると、マークルルートが一致しなくなる
 Trader Z
Trader Zマークル木を簡単に一言で申し上げるならば、「どんなに大量の取引データがあっても、わずかな情報だけでそれが正しいことを証明できる仕組み」です。



マークル木を用いることにより、整合性の確認が容易、高速な検証が可能、改ざん検出が容易になります。
つまり、誰でも・どこでも・正確に「その取引が本物かどうか」検証できる。これが、ブロックチェーン技術における非中央集権型の信頼の要と言えるでしょう。


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
マークル木(マークルツリー)とは?
マークル木の定義・概要
マークル木とは、データの集合を効率よく要約し、その正しさを少ない情報で検証できるようにするためのデータ構造です。
もともとは暗号理論の一分野で発案され、葉と呼ばれる最下層のノードにあるデータそれぞれのハッシュ値を上位へと段階的にまとめていく形が特徴となっています。最終的にはツリーの頂点部分に「マークルルート」と呼ばれる一つのハッシュ値が生成される仕組みです。
すべての要素データを正しく含んでいればマークルルートは同じ値になりますが、一つでも不正や改ざんがあればルート値が変化するため、整合性の検証が容易になります。
データをコンパクトに扱いつつセキュリティを高める技術という点でブロックチェーンにぴったり合致しており、ビットコインが採用して以降、さまざまな仮想通貨プロジェクトで利用されるようになりました。
名前の由来と歴史
この技術は、アメリカの計算機科学者ラルフ・マークル氏によって考案されました。1970年代に暗号に関する研究が活発に行われていた時代に生まれたため、ハッシュ関数や公開鍵暗号の発展とともに理論的な基盤を築いてきた経緯があります。
ビットコインに限らず、分散型ネットワークの整合性確認などにも応用されており、インターネット上で大きなファイルを分割して配信する際の改ざん検知にも使われています。
ハッシュとの関係と基本的な仕組み
マークル木の核となるのがハッシュ値の活用です。ハッシュとは、どんなに大きなデータでも一定のビット長で表す演算結果のことで、少しでも内容が変化するとまったく異なる値に変わる性質を持っています。
データ同士をペアにしてハッシュ化し、その結果をさらに上位でペアにして…という工程を繰り返すことで、最終的に一つのハッシュ値に集約できるわけです。
さらに、部分的なデータが正しいかどうかを検証する際にわざわざ全データをダウンロードする必要がありません。
マークルルートと、そのデータに至るまでの経路上のハッシュ(マークル証明)があれば、改ざんが行われていないかどうかをすぐに確認できるためです。
このように、ハッシュを使ってデータを階層的にまとめ、偽造の余地を極力減らすのがマークル木の肝となっています。
マークル木(マークルツリー)がなぜ仮想通貨で活用されるのか
ブロックチェーン上での役割
仮想通貨のブロックチェーンでは、取引データ(トランザクション)が次々に蓄積されていきます。たとえばビットコインの場合、ブロックと呼ばれる単位にトランザクションを詰め込み、それが鎖のようにつながって巨大な台帳を形成する仕組みです。
その各ブロックの中身を要約しているのがマークル木であり、ブロックヘッダーにはマークルルートと呼ばれる要約値が記録されます。
このルートが変化すれば、ブロック内部のトランザクションも改ざんされた可能性があると判断できます。複数のトランザクションをまとめ上げる作業を効率的に行ううえで、マークル木が欠かせない存在になっています。
効率的かつ安全なデータ検証
ブロックチェーンは分散型の仕組みを維持するために、世界中のノードが取引データを検証し合う形をとっています。
通常であれば全データを保持して検証するのが確実ですが、マークル木を使えば、ある特定のトランザクションがブロックに含まれているかどうかを最小限のデータだけでチェックできる利点があります。
大量のトランザクションが生じる中でも、ネットワーク全体の通信量やストレージ容量をできるだけ抑えるうえで非常に有用です。
SPV(簡易支払い検証)への応用
フルノードではなく、すべてのブロックをダウンロードせずに動作する簡易ウォレットなどでは「SPV(Simplified Payment Verification)」という仕組みが使われています。これは、マークル木を用いた検証方式を前提にしています。
たとえばスマートフォンのウォレットアプリでも、ユーザーが自分の取引がブロックチェーン上に正しく含まれたかどうかを確認できるのは、マークル証明により要約された情報でチェックできるからです。これによって、軽量な端末でもブロックチェーンを利用しやすくなっています。
マークル木(マークルツリー)を使うメリット
スケーラビリティの向上
ブロックチェーンには膨大な数のトランザクションが格納され続けます。もしも直接すべてのデータを検証する方式しかなければ、新規ノードがネットワークに参加する際や軽量クライアントが取引を監査する際に大きな負担がかかります。
マークル木であれば、全データを取得することなくブロック内部の正しさを確かめられるため、仮想通貨全体の利用者が増えても比較的スムーズに運用を続けられます。
改ざん検知の容易さ
一部のトランザクションが書き換えられたり、一部のデータが抜き取られたりすればマークルルートが変化します。ルートの値の整合性を見れば、不正が起きていないかをすぐに判断できるわけです。
ブロックチェーンはブロック単位でつながっているため、一箇所でも改ざんがあれば以後のブロックヘッダー全体が連鎖的に崩れることになります。こうした仕組みが仮想通貨の安全性を高め、信頼性を担保する大きな柱になっています。
軽量ノードの実現
ノードがフルスペックで動作しなくても一連の検証が可能になる点は、ネットワークの分散性を高めるうえでも重要です。
仮想通貨にかかわる全員が巨大なデータを保持するのは非現実的ですが、マークル木を活用すれば、小規模なメモリやストレージでも最低限の検証が行えます。
これにより、モバイル端末や小型デバイスでも仮想通貨が扱いやすくなり、さらなる普及が期待できるでしょう。
マークル木(マークルツリー)を用いた仮想通貨プロジェクトの事例
ビットコイン
ブロックチェーン技術を世界に広めるきっかけとなったビットコインでは、マークル木が誕生当初から採用されています。
ブロックヘッダーに含まれるマークルルートは、すべてのトランザクションを要約したハッシュ値です。
改ざんの有無やブロックの正当性を短時間で検証できる点が多くの支持を集め、ビットコインの分散型システムを下支えしてきました。
イーサリアム
イーサリアムは、ビットコインとは異なるアカウントモデルを採用しているため、「マークルパトリシアトライ(MPT)」と呼ばれる少し複雑な構造でデータを管理しています。
これも本質的にはマークル木と同様に、ハッシュによる階層構造でブロック内の状態を要約していくものです。アドレスごとの残高やスマートコントラクトの状態を効率よく検証し、かつ改ざんを検知できる仕組みになっています。
その他アルトコインでの活用例
ライトコインやリップルなど、多くのアルトコインにもマークル木は実装されています。
ブロックチェーン技術を採用しているプロジェクトであれば、ほとんどの場合マークル木やそれに類する構造が利用されているといっても差し支えありません。
取引の安定性やセキュリティを維持するために不可欠な役割を果たしているからです。
マークル木(マークルツリー)が注目を集める背景と注目のニュース
セキュリティ・透明性強化の重要性
暗号資産取引所の破綻や不正アクセス事件など、利用者保護の観点からセキュリティや透明性が一層求められる流れが強まっています。
ユーザーが自身の資産が確かに存在しているかどうかを検証できる「Proof of Reserves(準備金証明)」でマークル木を用いる事例が増えていることも大きな特徴です。
取引所は顧客資産の総量と自社の保有資産をマークル木によって照合する仕組みを公開し、ユーザーの信頼を得ようとしているわけです。
Verkle木など派生技術の動向
イーサリアムコミュニティを中心に「Verkle木」と呼ばれる次世代のハッシュ木が検討されています。マークル木よりも証明サイズを大幅に削減できる可能性があるとして期待を集めているためです。
証明が小さくなると、さらに軽量なノードの実現が見込まれます。将来的には、高速化やスケーラビリティの向上という点でメリットをもたらすかもしれません。
2025年の注目ニュース
大手取引所がマークル木を使った準備金証明を定期的に開示している動きが継続しています。
FTX破綻以降、ユーザーからの信頼回復を図る一環として、世界的な取引所や日本国内の取引所がこぞって新たな監査レポートを公表している状況です。
イーサリアムでもVerkle木の実装計画が進められており、コミュニティ内での議論が活発化していることが報じられています。
こうした動向から、マークル木という仕組みがセキュリティだけでなく利便性の面でもますます注目されているといえるでしょう。
マークル木(マークルツリー)今後の展望
発展が期待される分野
ブロックチェーン以外でも、膨大なデータを扱う分散システム全般にマークル木を応用する試みが増えるかもしれません。
すでにP2Pファイル共有などでも使われていますが、IoTデバイス間でのデータ検証や大規模データベースの監査手法としてはまだまだ余地が残っています。
クラウドサービスやデータセンターでのセキュリティ強化にも、マークル木が貢献できる可能性が高いです。
課題と乗り越え方
マークル木自体は非常に有用ですが、ブロックチェーンが大きくなればなるほどルートや証明の更新頻度が増え、計算リソースへの負荷が高まる懸念があります。
そこでVerkle木など新しい構造の研究が進められ、ノードの負担を減らす取り組みが活発化しています。とはいえ、どのような新技術も実装や標準化に時間がかかるため、研究開発と実用化が並行して行われる状況が続きそうです。
マークル木(マークルツリー)とは?まとめ
マークル木(マークルツリー)は、仮想通貨やブロックチェーンを学ぶうえで欠かせない技術だと考えられます。複数の取引データを効率的にまとめ上げ、わずかな情報だけで改ざんを検知できる点が最大の強みです。
ビットコインやイーサリアムなど主要なプロジェクトのみならず、暗号資産全般で導入されているため、ブロックチェーン分野に興味のある方はぜひ理解を深めてみてください。
最新の動向を追うことで、今後さらに進化する可能性があることにも注目できます。
読者の皆様がマークル木をきっかけに仮想通貨やブロックチェーンの面白さを実感し、より安全に活用できるようになることを願っています。




