
仮想通貨のステーキングとは?税金や利回り、レンディングとの違いをわかりやすく解説!
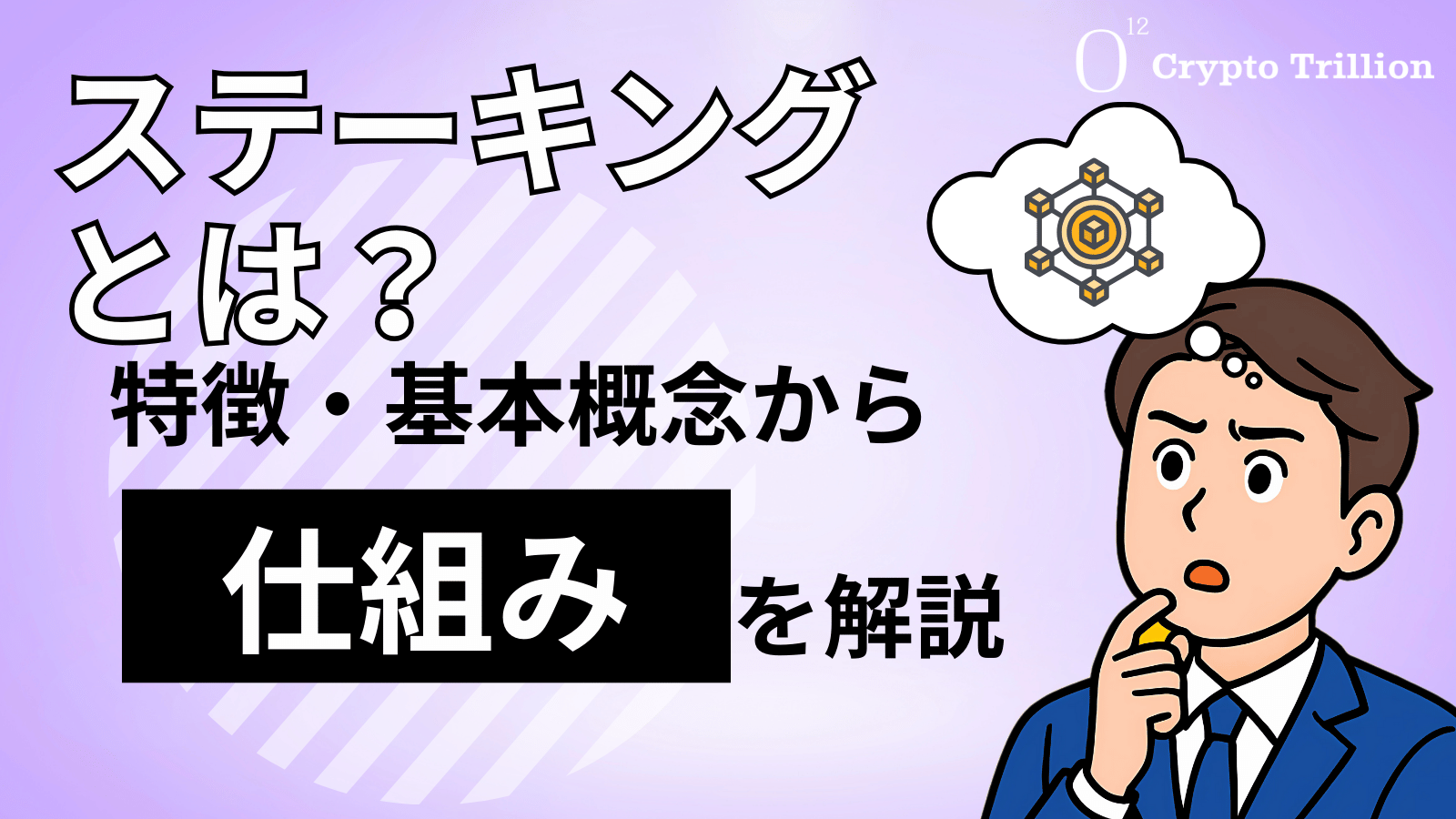
プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- 仮想通貨をブロックチェーン上にロックし、ネットワークの運営に貢献した対価として報酬を受け取る行為
- PoS(プルーフ・オブ・ステーク)は、コイン保有者がネットワーク運営に参加する仕組み
- ステーキング対応通貨を一定数以上ロックすることで、ブロック生成の報酬を得られる可能性がある。
- 代表例としてはイーサリアム、カルダノ、ソラナ(SOL)、コスモス(ATOM)などが有名
- リキッドステーキングの登場により、ロック期間中でも資産を別途活用できる動きが出てきた
- かつてPoWを採用していたイーサリアムが、大型アップデートによってPoSへ切り替え話題になった
- 銀行預金の金利がほぼゼロに近い中、ステーキングでは年数%から10%程度の報酬が見込める
- ステーキングによって獲得した報酬は、日本国内の税法上「雑所得」に区分される
- カルダノでは初期の報酬率が5%前後でしたが、利用者の増加などの影響を受けて徐々に低下
- レンディングは、暗号資産を取引所に貸し出し、一定期間後に利息を上乗せして返してもらう方法
- レンディングと異なり、直接的な借り手との契約は存在せず、ブロックチェーンプロトコルに参加する形
- ステーキングの利回りは、対象銘柄やネットワークの設計など多くの要素に左右される
 Trader Z
Trader Zステーキングに関して申し上げますと、戦略としては「検討に値する選択肢」ではございますが、実行にあたっては非常に慎重な見極めが必要です。
最近「年利10%〜15%の高利回りを実現!」といった謳い文句を目にされることもあるかと存じますが、こうしたプロモーションには注意が必要です。



特に重要なのは、「どのトークンを、どのプラットフォームで、どのような期間ステーキングするか」です。
例えば、イーサリアムを信頼できるプラットフォーム(例:Lido等)でステーキングするのは、一定の合理性があるのですが、あまり知られていない草コインのようなものを、検証の不十分なDeFiサービスにロックすることは、投資ではなくむしろ投棄と言わざるを得ません。
\日本円の入出金・仮想通貨の送金手数料無料!/


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
ステーキングとは?
ステーキングの基本的な概要
ステーキングは、保有する仮想通貨をブロックチェーン上にロックし、そのネットワークの運営やセキュリティ維持に貢献した対価として報酬を受け取る行為を指します。
Proof of Stake(PoS)と呼ばれる仕組みに基づいており、銀行の定期預金に少し似た性格を持っています。
ただし、価格変動リスクやロック期間中の制限などもあるため、預金感覚で利用できるわけではありません。
具体的には、イーサリアム(ETH)やカルダノ(ADA)、ポルカドット(DOT)のようにPoS系のブロックチェーンで実装されている仕組みで、コインをロックしている間は送金が制限される場合があります。
その代わりに、ステーク中の資産に応じて利率相当の報酬を受け取れる可能性があります。
ステーキングを行うことで投資スタイルは「安く買って高く売る」だけに頼らない選択肢が生まれ、暗号資産を長期保有する意欲が高まるかもしれません。
PoS(プルーフ・オブ・ステーク)の基本
PoS(Proof of Stake)は、ネットワーク上の取引データを正しく検証して次のブロックを生成する権利を、コインの保有量や保有期間に応じて割り当てる仕組みです。
たとえば大量のコインを長期間ロックしている人がブロック生成の作業者に選ばれやすい一方、不正行為が行われた場合はロックしたコインの一部が没収されるペナルティも存在します。
これをスラッシングと呼び、悪意ある行為を抑止することでネットワークの安全性を保っています。
ビットコイン(BTC)などが採用しているProof of Work(PoW)では、高性能なコンピューターを使ったマイニング競争によってブロックを生成するため、多大な電力を消費します。
PoSではマイニング機材は必要なく、ロックしたコインが多い参加者ほどブロックの承認に関わりやすい設計になっています。そのため、環境負荷が小さい手法として注目されました。
ステーキング対応銘柄と参加方法
PoSを採用している暗号資産の多くがステーキングをサポートしています。
代表例としてはイーサリアム、カルダノ、ソラナ(SOL)、コスモス(ATOM)などが有名です。
ユーザーがこうした銘柄を保有し、公式ウォレットや取引所が用意しているサービスを通じてコインをロックすると、報酬が付与される可能性があります。
参加方法は大きく分けて2つあります。
1つは自分でバリデーター(検証者)としてノードを運営する方法で、専用のソフトウェアを使い24時間稼働するノードを維持する必要があります。
もう1つは、取引所やステーキング代行プロバイダを活用する方法です。
取引所経由の場合は、対象銘柄を一定数以上持っていれば、アカウント内でステーキングを有効化しておくだけで報酬が分配されるしくみになっていることが多いです。
ステーキングのメリット・デメリット
ステーキングのメリット
ステーキングの大きな魅力は、暗号資産を売却せず持ち続けるだけで報酬が得られるかもしれない点です。
銀行預金に比べて高めの利率が設定されていることが多いので、複利効果が働くと長期的にはまとまった収益が見込める可能性があります。
単なる値上がり益(キャピタルゲイン)頼みではなく、定期的にリワードを受け取れる仕組みがあることで、「増やしながら保有する」新しい投資スタイルにつながるかもしれません。
加えて、自力でマイニング機材を用意する必要がないため、専門的な設備投資や膨大な電力コストを気にしなくても良いケースが多いです。
これは個人にとって大きなメリットになります。環境負荷が比較的小さい技術であるとも言われており、これまでの暗号資産投資に対するイメージを変えるきっかけとなっています。
ステーキングのデメリット・注意点
一方で、メリットだけを期待して飛びつくのは危険です。
代表的な注意点として、ロック期間中は預けた通貨を自由に動かせないことが挙げられます。
ロック中に相場が暴落してしまうと、慌てて売りたいと思ってもすぐに売れない可能性があります。
急に資金が必要になったときにも引き出せないことがあるため、生活費や当面使う予定の資金をステークするのは避けたほうが無難でしょう。
また、暗号資産自体が価格変動リスクを内包しており、報酬として得られる通貨の価値が下落する可能性もあります。
たとえ年利が高くても、通貨の相場が大幅に下がってしまうとトータルで損をするかもしれません。
さらに、ステーキングを提供する取引所やサービス事業者が破綻した場合、預けた通貨が返ってこないリスクもゼロではありません。
国内の交換業者は法律で分別管理が義務付けられていますが、海外サービスを利用する際には十分に注意することが大切です。
ステーキングに税金はかかるのか?
ステーキングによって獲得した報酬は、日本国内の税法上「雑所得」に区分される可能性が高いとされています。
受け取ったコインを法定通貨に換金していない場合でも、報酬として付与された時点の時価を基準に課税対象となると考えられます。
具体的にはステーキングによって新たに得たコインの評価額を計算し、ほかの所得と合算したうえで総合課税の対象になるかたちです。
仮想通貨に関する税務ルールは今も整備途上なので、正式な判断が必要な場合は税理士や国税庁のガイドラインを確認すると安心です。
気をつけたい点としては、ステーキング報酬を受け取った時点の価格が高くても、後から価格が下がるリスクがあるということです。
報酬による利益が課税額を上回らないよう、資産管理と納税資金の確保を計画的に行うと良いでしょう。
報酬を受け取った暗号資産をすぐに日本円に換金するかどうかも含め、税負担を考慮して戦略を立てることが大切です。
ステーキングとレンディングの違いとは
ステーキングとよく比較される仕組みとして、仮想通貨のレンディング(貸し出し)が挙げられます。
レンディングは、ユーザーが自分の持つ暗号資産を取引所や貸付プラットフォームに貸し出し、一定期間後に利息を上乗せして返してもらう方法です。
一般的には「借り手がコインを返済できないリスク」や「サービス提供者の破綻リスク」を考慮する必要があります。
一方、ステーキングはProof of Stakeというコンセンサスアルゴリズムに則り、ロックしたコインをネットワーク維持に役立てることで報酬を得るしくみです。
マイニングのような電力消費は少なく、銀行預金のように保有量に応じてリワードが付与されるイメージに近いかもしれません。
レンディングと異なり、直接的な「借り手との契約」は存在せず、ブロックチェーンのプロトコルに参加する形になるため、仕組みの根本は大きく異なります。
とはいえ、サービス提供者にコインを預ける形態のステーキング代行では、やはり事業者リスクに注意が必要です。
ステーキングの実際の利回りは?
ステーキングの利回りは、対象銘柄やネットワークの設計、参加者数、さらには運営方針の変更など多くの要素に左右されます。
公表された年利がそのまま実現するとは限らず、需要と供給のバランスによって報酬率が変化することがあるからです。
たとえば、カルダノ(ADA)では初期の報酬率が5%前後でしたが、利用者の増加やネットワークアップデートの影響を受けて徐々に低下するケースが見られました。
逆にソラナ(SOL)のように、一時的に年利8%程度まで上昇した事例もあります。
さらに、報酬として得られるコインの価格は市場の動向で大きく変動します。通貨の相場が下がってしまうと、受け取ったコインの数量が増えても最終的に円換算すると思ったほど利益が出ないかもしれません。
複利効果を最大化したい場合は、報酬分のコインを再びステーキングに回す方法もありますが、その際も相場変動リスクはつきものです。
実際の利回りを判断するには、プロトコルが提示しているAPR(年率)だけでなく、相場の読みやネットワークの安定性など総合的に考える必要があります。
なぜステーキングがここまで有名になったのか
高利回りと低金利環境による注目
銀行預金の金利がほぼゼロに近い状況が長く続いているため、預けていても増えにくい現実がありました。
その一方で、ステーキングでは年数%から10%程度の報酬が見込めるという情報が広まり、多くの投資家の関心を集めた経緯があります。
実際にそのような高い利回りを得られるとは限りませんが、現行の低金利と比較すると魅力的に映ることは確かです。
こうした「預けて増える」スタイルに興味を持つ人たちが暗号資産市場に参入した結果、ステーキングは大きく話題となりました。
イーサリアムのPoS移行・主要プロジェクトの影響
イーサリアムはビットコインに次ぐ時価総額を誇り、NFTや分散型金融(DeFi)など多種多様なサービスの土台となっているプラットフォームです。
かつてはPoWを採用していましたが、大型アップデート「The Merge(ザ・マージ)」によってPoSへ切り替わりました。
これはブロックチェーン業界全体にとって大きな出来事であり、「今後はステーキングが暗号資産投資の主流になるかもしれない」と感じる投資家が増えた要因です。
その他にもカルダノやポルカドットなど、初期からPoSを採用していたプロジェクトが着実に成長したことも追い風となっています。
取引所・ステーキングサービスの普及
ステーキングを始める際に重要な役割を果たすのが、大手の取引所やウォレットサービスです。
国内外問わず、多くの事業者がステーキング対応のコインを取り扱い、ユーザーが資産を預けるだけで報酬を受け取れるようになりました。
かつては自前でノードを立ち上げるハードルが高く、専門知識が必要でしたが、取引所が代行してくれることで初心者でも簡単に参加できるようになっています。
このような整備によって、ステーキングの認知度と利用者数はさらに拡大しているのが現状です。
注目のニュース・最新動向
リキッドステーキングの普及
リキッドステーキングとは、ステークした暗号資産に対して発行されるデリバティブトークンを活用し、ロック中でも他の分散型金融(DeFi)で運用できる仕組みです。
たとえばLidoのstETHや、他にも各プロジェクトが提供している流動性確保の手段が該当します。
ロックすることによる流動性の低下をカバーするサービスであり、ステーキングがさらに発展するきっかけにもなっています。
複雑な仕組みではあるものの、流動性を確保したままステーキング報酬が狙える可能性があるため、注目度が高まっています。
新規PoS銘柄と報酬利率の推移
PoSに対応した新しい通貨が次々と登場しており、二桁の年利を設定しているケースも見られます。
ただしこうした高い利率がずっと続くとは限らず、ネットワーク参加者が増えると報酬が薄まることもあるため、将来的な利率低下には注意が必要です。
カルダノのように初期の報酬率は高かったものの、段階的に下がっていったプロジェクトも存在します。
魅力的な利率をうたう通貨のなかには、プロジェクト自体のリスクが大きいものもあるので、ホワイトペーパーやコミュニティの動向を確認しながら慎重に判断したほうが良いでしょう。
日本国内のステーキング事情
国内の取引所もステーキングサービスに力を入れており、対応銘柄の拡充や利便性の向上を追求しています。
たとえばSBI VCトレードやGMOコインなどは、人気銘柄だけでなく新しいPoS通貨も取り扱うようになっています。
日本の交換業者は厳格な法規制のもとで事業を行っているため、海外に比べると利回りが低めになりがちという見解もあります。
しかし、資産の安全面や日本語でのサポートを重視する方にとっては安心材料になるでしょう。
税制上の課題はまだ多く、ステーキング報酬がどのタイミングで課税対象になるのか議論されている途中ですが、今後の制度整備によってはさらに利用者が増える可能性もあります。
ステーキングとは?まとめ
ステーキングは、仮想通貨を長期保有しながら運用する選択肢として急速に認知が高まっています。
ロックによる報酬が期待できる一方で、コイン価格の変動やロック期間中の流動性リスクなどを十分に理解する必要があります。
初心者の方は大手取引所や信頼できるステーキングサービスを利用し、小さな金額から始めてみるのもひとつの方法かもしれません。
技術や税務関連の知識が追いつかない場合は、専門家や公式のサポート窓口を活用しながら、無理のない範囲で進めると安心です。
すでに銀行預金では増えにくい時代だからこそ、ステーキングのように「預けて増やす」方法が選択肢として注目を集めています。
イーサリアムの大型アップデートに代表されるように、今後もステーキング環境は進化していくと考えられます。
投資する銘柄の性質や将来性を見極めながら、メリットとリスクを比較検討し、自分の投資スタイルに合った方法を選ぶことが大切です。
暗号資産の市場は変化が激しいため、最新動向をチェックしながら冷静な判断を心がけてください。




