
仮想通貨の税金をわかりやすく解説|初心者が知っておきたい基礎知識と確定申告の流れ
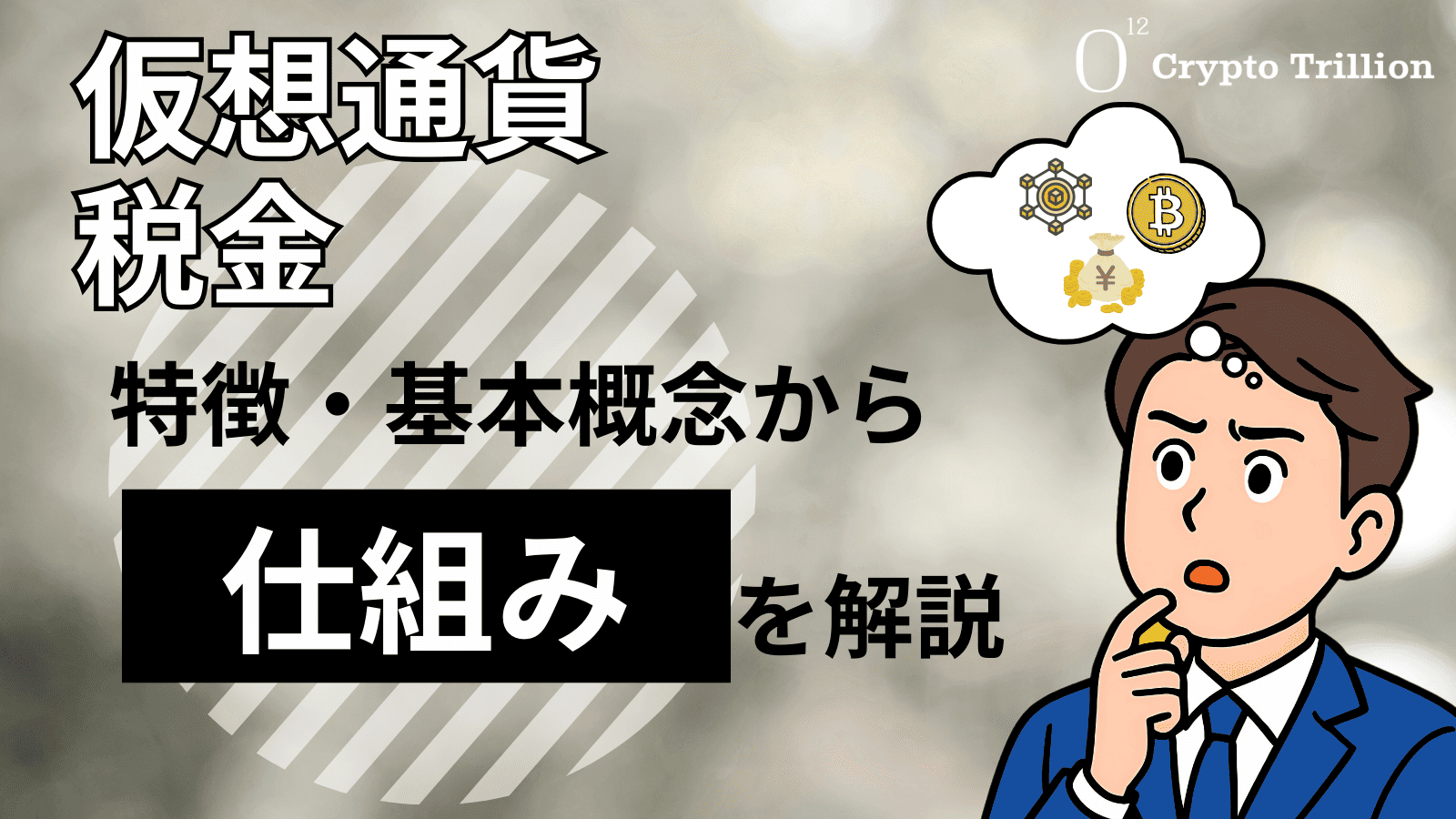
プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- 仮想通貨で儲けが出た場合は基本的に税金の対象になる
- 仮想通貨の利益は雑所得として扱われ、副収入としての雑所得が年間20万円を超えると確定申告をする必要あり
- 仮想通貨は総合課税の対象であり、利益が4,000万円を超える場合には最大55%の所得税がかかる
- 仮想通貨で儲けが出た場合は基本的に税金の対象になる
- 他の暗号資産との交換や、仮想通貨での決済を行った場合
- マイニング(採掘)やステーキングによって仮想通貨を取得した場合
- 仮想通貨の確定申告をしないと本来の税額に加えてペナルティー(追徴課税)が科される
- 期限後に申告・納付した場合に課される無申告加算税(原則5%、税務調査で指摘を受けた場合10%~20%)
- 納付が遅れた場合の延滞税(納付遅延日数に応じた年利の利息)が発生
- 意図的に所得を隠していたと判断された場合は、重加算税(最大35%~40%)
 Trader Z
Trader Z仮想通貨取引にかかる税制は、極めて厳しい状況にあります。
現在の日本における税制では、仮想通貨取引による利益は「雑所得」に分類され、最大で55%の税率が課される可能性があります。
これにより、損益通算が不可(株式やFXの損失と相殺できない)、損失の繰越控除が不可(翌年以降の利益と相殺できない)、短期間で大きな利益を得た場合でも、高税率が適用されます



仮想通貨の確定申告を正しく行うには、まず申告が必要か確認しましょう。会社員は年間20万円以上、フリーランスは48万円以上の利益がある場合、確定申告が必要です。
取引所の履歴をダウンロードし、売買や送金、ステーキング報酬などを整理して利益を計算します。売却や交換、決済、報酬の受け取り時点で課税対象となるため、取引のタイミングにも注意が必要です。
申告書はe-Taxでオンライン提出するか、税務署に紙で提出します。2025年分の締め切りは2026年3月15日です。
【所得税+住民税】税率早見表(2025年版)
| 課税所得金額(合計) | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率(概算) |
|---|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 10% | 約15% |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 10% | 約20% |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 10% | 約30% |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 10% | 約33% |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 10% | 約43% |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 10% | 約50% |
| 4,000万円超 | 45% | 10% | 約55% |


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
仮想通貨の利益は雑所得に分類される
仮想通貨で利益が出た場合、その所得は「雑所得」に分類されます。これは税法上、他の所得(給与・事業・譲渡など)に該当しない収入の一つとして扱われるためです。
たとえば、ビットコインを50万円で購入し、価格が上昇して100万円で売却したとします。この場合、差額の50万円が「利益(所得)」と見なされ、税金の対象になります。
雑所得とは何か
雑所得とは、公的年金や副業収入、講演料、仮想通貨取引など、分類されない所得を指します。特徴として、他の所得と「合算」されて課税されること、損益通算(他の所得との相殺)ができないことが挙げられます。
また、仮想通貨の取引を「継続的かつ事業的に行っている」と税務署に判断されれば、雑所得ではなく事業所得として扱われる可能性もあります。ただし、それには営利性・継続性・反復性などの要件を満たす必要があります。
仮想通貨にかかる税率と「総合課税」の仕組み
雑所得は「総合課税」として扱われ、ほかの所得(たとえば給与)と合算して課税されます。日本の所得税は超過累進課税制度で、所得が増えるほど税率も上がる仕組みです。
以下が、主な課税所得額に対する税率です(所得税部分のみ):
- 〜195万円:5%
- 195万円〜330万円:10%
- 330万円〜695万円:20%
- 695万円〜900万円:23%
- 900万円〜1,800万円:33%
- 1,800万円〜4,000万円:40%
- 4,000万円超:45%
これに一律10%の住民税が加算されるため、最大で55%の税率となる可能性があります。
たとえば、会社員で給与収入が500万円ある人が、仮想通貨で300万円の利益を出した場合、課税所得は約800万円となり、税率23%+住民税10%=33%程度で課税されることになります。
税金が発生する取引タイミングとは
「仮想通貨を買っただけで税金がかかるの?」と心配される方もいますが、税金が発生するのは次のようなタイミングです。
- 仮想通貨を売却して日本円に換金したとき
- 仮想通貨で商品やサービスを購入したとき
- 仮想通貨を別の通貨(例:BTC→ETH)に交換したとき
- マイニング・ステーキング報酬を受け取ったとき
逆に、保有しているだけ(ガチホ)では税金はかかりません。「売った」「使った」「交換した」ときに課税対象となる点を覚えておきましょう。
仮想通貨の利益計算方法と具体例
仮想通貨の利益は基本的に以下の式で計算されます。
利益=売却額 − 取得額 − 経費
たとえば、ビットコインを1BTC=300万円で購入し、1BTC=400万円で売却した場合、差額の100万円が利益になります。ここから手数料や送金コストなどの経費が差し引けます。
移動平均法と総平均法の違い
仮想通貨の取得額(原価)を計算する方法には「移動平均法」と「総平均法」があります。
- 移動平均法:購入するたびに保有資産の平均単価を更新して計算。実際の取得コストに近いが、計算はやや複雑です。
- 総平均法:その年に取得した仮想通貨の平均単価を出し、年末にまとめて計算する方法。一般的に多くの個人投資家が利用しています。
国税庁が提供している「暗号資産の計算書」も、総平均法を前提に作成されています。Excel形式で提供されているため、記入例を見ながら作成するのがスムーズです。
仮想通貨の確定申告が必要な人とは?
以下のいずれかに該当する場合、確定申告が必要になります。
- 仮想通貨による利益(雑所得)が20万円を超える(会社員)
- 仮想通貨収益が唯一の収入(個人事業主や専業投資家)
- 雑所得がある人で、所得税の還付を受けたい場合(控除利用など)
e-Taxなどを使った申告方法
申告には「確定申告書B」を使用し、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxソフトを使えば、パソコンやスマホからオンラインで完結できます。
申告内容には以下のものが含まれます:
- 給与所得(源泉徴収票を基に入力)
- 雑所得(仮想通貨利益)
- 所得控除(ふるさと納税、医療費、保険料など)
- 税額の確認と納税手段の選択(銀行・クレカ・コンビニなど)
仮想通貨に関する申告欄には、「暗号資産に係る雑所得(その他)」を選び、取引履歴に基づいた利益額と経費を入力します。
申告しないリスクと税務署の把握範囲
確定申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合、以下のペナルティを受ける可能性があります。
- 無申告加算税:最大20%
- 延滞税:最大14.6%(年度により変動)
- 重加算税:故意の隠蔽があった場合、最大40%
仮想通貨取引所は、取引情報を税務署に報告する義務があるため、「申告しなくてもバレない」は通用しません。実際に仮想通貨の申告漏れで税務調査が入った事例も多数あります。
また、たとえ利益が20万円以下で申告義務がなかったとしても、住民税の申告が必要な場合があるため、最寄りの自治体へ確認することをおすすめします。
仮想通貨の節税対策|合法的に税負担を抑えるには
仮想通貨の税金は「雑所得」扱いですが、正しい知識と対策をすれば、税金を抑えることも可能です。以下に代表的な方法を紹介します。
必要経費の把握
次のような支出は、仮想通貨取引の経費として計上できます。
- 取引所の売買手数料
- 仮想通貨送金時のネットワーク手数料(ガス代など)
- 利益計算ツールの利用料や仮想通貨に関する有料情報の購読料
- 関連するソフトウェアやセミナーの参加費(合理的であると判断される場合)
経費として認められるかどうかの基準は「利益を得るために直接必要だった支出かどうか」です。領収書や証拠書類は必ず保管しておきましょう。
損失の活用と翌年への持ち越しについて
仮想通貨取引で損失が出た場合、同一年内の仮想通貨利益との相殺は可能です。たとえば、10万円の損と30万円の利益があれば、差引20万円の利益となります。
ただし、雑所得には損益通算や損失の繰越控除が認められていません。つまり、赤字を翌年以降に持ち越すことはできません。
年末に含み損が出ている仮想通貨があれば、年内に売却して損失を確定させることで、利益との相殺が可能になります。
法人化や事業所得の適用について
仮想通貨で大きな利益を継続的に得ている方は、「法人化」や「事業所得での申告」が選択肢になることもあります。
- 法人化:法人税の実効税率は約30%前後。個人の最高税率55%より低く抑えられる可能性があります。経費計上の幅も広がります。
- 事業所得扱い:青色申告で最大65万円の控除や赤字の繰り越しが可能に。ただし、税務署が“事業”と認めるためには、取引の規模や営利性、継続性などが求められます。
これらは有効な節税手段になり得ますが、導入には手続きや判断が必要なため、必ず税理士などの専門家に相談しましょう。
まとめと次のアクション
仮想通貨の利益は「雑所得」として課税され、年間20万円を超えると確定申告が必要になります。売却や交換、使用といった利益確定のタイミングで税金が発生し、計算には移動平均法や総平均法を用います。
確定申告の義務を怠ると、ペナルティを受ける可能性があり、取引所の情報も税務署に共有されているため、安心のためにも正確な申告が欠かせません。
節税対策としては、経費の計上、含み損の活用、利益の分散、そして規模によっては法人化や青色申告の検討も視野に入れるとよいでしょう。




