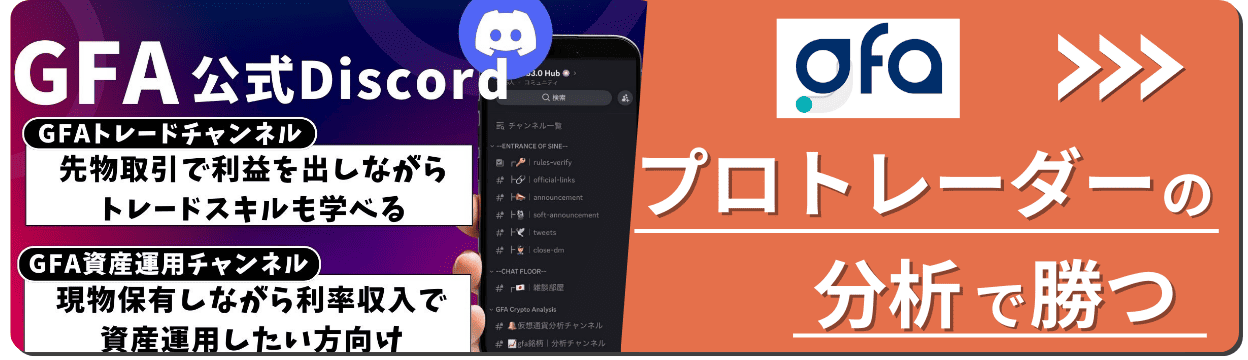仮想通貨ジャスミー/Jasmyとは?将来性やチャートを用いた価格予想など解説!
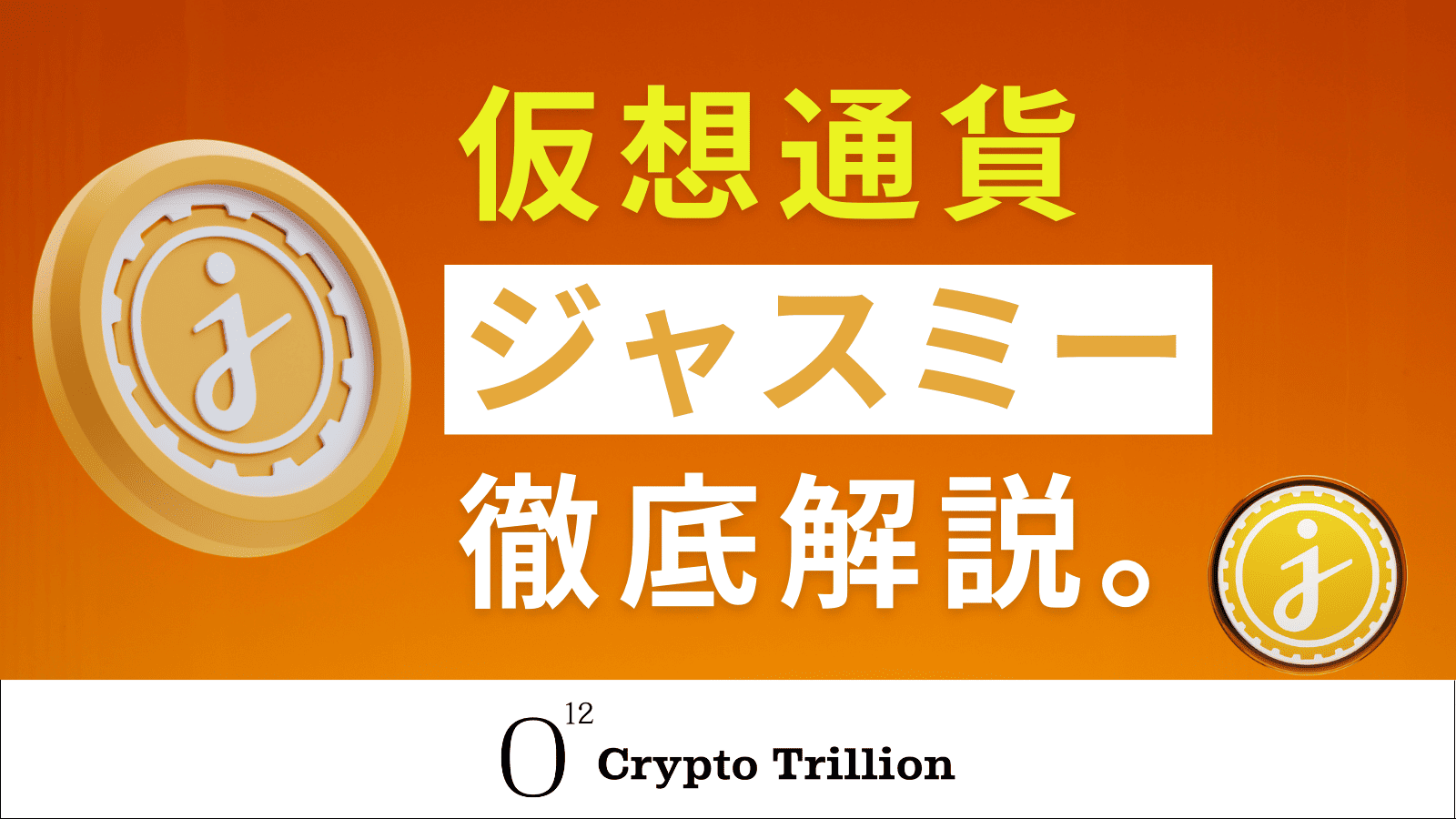
プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- Jasmyは個人データの主権を利用者に取り戻す「データの民主化」を目指す
- Jasmy株式会社は2016年に設立、創業陣にはソニーの元社長である安藤国威氏などが名を連ねる
- 2021年頃からBinanceやCoinbaseなど大手取引所への上場や有名企業との提携を相次いで発表
- 「IoT×ブロックチェーン」という分野に特化しており、日本発であることから国内外の注目を集める
- パナソニックやVAIOなど国内の大手企業との協業を発表し技術面の開発を進めている
- 日本発の暗号資産としては珍しく、金融庁の認可を得て国内取引所にも上場している
- JasmyはEthereumエコシステムの上に築かれているため、他のDeFiやNFTなどと連携しやすい
- スケーラビリティ向上とマルチチェーン戦略を進めるため独自Layer2「JANCTION」を構想
- 個人データを安全に保管するPDLウォレットでユーザーが自身のデータを完全に掌握できる
- ユーザーはSKCによって中央サーバーを通さずに自分のデータ使用履歴を追跡できる
 Trader Z
Trader ZJasmyの掲げる「個人が自分のデータを自分でコントロールできる世界の実現」は、Web3の本質に非常にマッチしています。
現代はGoogleやFacebookといったプラットフォーマーがデータを独占している時代ですが、その構造を覆すというチャレンジは、非常に意義深いです。
このコンセプトが今後、明確なプロダクト・アプリケーションと連動するようになれば、時代の流れに乗る可能性は十分にあります。



Jasmyは、日本の大手取引所(BitPoint、Coincheckなど)で取り扱われており、日本円で直接購入できるという点で、仮想通貨初心者にとってアクセスしやすい銘柄となっています。
この点は、規制が厳しい日本市場で上場審査を通過した実績として、一定の評価に値するでしょう。


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
Jasmy(ジャスミー)とは?
Jasmyのコンセプトと開発背景
Jasmyは、IoT機器から生まれるあらゆるデータを個人が自ら管理し、そのデータを企業やサービスに提供する際にトークンを対価として受け取る仕組みを構築しています。
背景には、現在のインターネット空間が大手プラットフォーマーによってデータを独占されている状況があり、ユーザーが本来もつはずの権利や利益がないがしろにされているという問題意識があります。
この課題を解決するために、JasmyではブロックチェーンとP2P技術を応用し、個人情報や行動履歴を安全に保管する分散型ストレージを用意しました。
利用者は、自分のデータを手元に置いたまま、必要に応じて企業に共有し、その対価としてプロジェクトが発行するJasmyCoin(JASMY)を受け取ることが可能です。
運営企業と主要メンバー
Jasmyを運営するのは、ジャスミー株式会社(Jasmy Corporation)という日本企業です。ソニーの元社長である安藤国威氏や、NFCなど先進技術を手がけていたエンジニア陣が中心となって立ち上げました。
これまでに大手メーカーやIT企業との協力実績があることから、初期段階から話題性と信頼性を獲得しやすかったといえます。
同社は早い段階で国内取引所への上場を実現しており、これは日本の金融庁のガイドラインをクリアする必要があったことを意味します。
金融庁による審査は比較的厳しいとされるため、そのハードルを乗り越えた点もJasmyの信頼を高める材料の一つになりました。
一方でシンガポールなど、海外を拠点としたグローバルな展開にも取り組んでいるため、国内外の両市場で注目を集める存在になっています。
Jasmy(ジャスミー)が注目される理由
IoT×ブロックチェーンの融合
Jasmyが注目を浴びている大きな理由は、IoT(モノのインターネット)分野にブロックチェーンを組み合わせている点です。
IoT機器は、センサーや家電、車両など生活の至るところで使われ始めています。
しかし、それらから生成されるデータは企業が一方的に収集するケースも多く、プライバシー保護やデータ改ざんへの懸念が絶えません。
そこでJasmyでは、ブロックチェーンを使って「いつ誰がどのデータを利用したのか」を透明化し、ユーザー自身がアクセス権を管理できる仕組みを生み出そうとしています。
IoTが作り出す莫大な情報をセキュアに取り扱うことで、新たなビジネスモデルやサービスが登場する可能性もあると考えられます。
日本発プロジェクトによる信頼性
暗号資産のプロジェクトは欧米やアジア圏からの発信が中心で、日本で完結している事例はまだ多くありません。
Jasmyは日本企業が運営する珍しいケースにあたり、国内ユーザーにとっては言語面やサポート面でもメリットがあります。
また規制面でも、海外プロジェクトに比べるとルール順守を徹底しやすい強みがあるかもしれません。
さらに、パナソニックやVAIOなど国内の大手企業との協業がメディアを通じて報じられたことで、Jasmyに対する信頼感が一段と高まりました。
スマートホームやリモートワーク向けのセキュアソリューションなど、日常に近い分野での活用が取りざたされている点も注目を集める理由の一つです。
Jasmy(ジャスミー)の主要な特徴と技術的仕組み
パーソナルデータロッカー(PDL)
PDLの基本構造
Jasmyが提供するパーソナルデータロッカー(PDL)は、利用者が自分のデータを安全に保管するための基盤です。
PDLにはIoTデバイスから日々生成されるログや、サービス利用時に発生する個人情報が暗号化された状態で格納されます。
これらのデータそのものは、P2Pネットワークを活用した分散型ストレージに保存され、改ざんや盗難が起きにくい構造が採用されています。
ハッシュ値などのメタ情報はブロックチェーンで一元管理し、ユーザーのウォレットアドレスと対応づけられます。
これにより、誰がどのデータの所有権を持っているのかを明確にしながら、同時にプライバシーを守ることが可能になります。
ユーザーが得られるメリット
PDLを使うメリットは、ユーザーが自身のデータを完全に掌握できることにあります。
たとえばスマホや家電を通じて得られる行動履歴を、自分の手元に置いたまま、企業に必要な部分だけを提供できる仕組みが整えられています。
データ提供にはJasmyCoinによる報酬が設定されることが想定されており、個人が自分の情報を活かしてリターンを得られる可能性があります。
また、大手プラットフォーマーのサーバーに一括管理される場合とは異なり、分散型の仕組みでデータを保護しているため、情報漏洩リスクを下げられます。
万一のシステム障害が起きても、複数のノードでデータを保持するため復旧がしやすいという点も特徴です。
セキュアナレッジコミュニケーター(SKC)
SKCの技術的背景
セキュアナレッジコミュニケーター(SKC)は、Jasmyが構築したデータ取引の中枢といえる存在です。
分散ID(DID)の概念を取り入れ、ユーザー個別のIDと暗号鍵を結びつけることで、データの真正性を担保します。
P2P通信を採用しているため、中央サーバーを通さずにユーザー間やユーザーと企業間のデータ受け渡しが行われます。
この仕組みによって、データが実際に誰に共有されているのかを追跡できるようになります。
アクセス権の付与や取り消しもユーザー自身が行えるため、これまで不透明だった企業側でのデータ利用状況が可視化される点は大きな変化といえるでしょう。
データ提供と追跡プロセス
SKCを使うと、たとえばヘルスケアのデータや位置情報などを企業に渡す際、どこまで共有するかをユーザーが選択できます。
企業が分析やマーケティングでデータを利用する場合、ユーザーへ明確な利用目的を提示することが求められます。
承諾した内容以外の情報は取得できないため、これまでのように一度登録したらすべての個人情報が流出するリスクが下がります。
提供後に「やはり許可を取り消したい」と思えば、SKCの管理画面から権限を取り消すこともできます。
この一連の流れがブロックチェーン上で記録されるため、過去の履歴をさかのぼって不正や誤用がなかったかを検証することも可能です。
スマートガーディアン(SG)
SGの導入事例
スマートガーディアン(SG)は、IoT機器が本人のものであることを明確化し、外部からの不正アクセスを防止する仕組みです。
たとえばスマートロックや防犯カメラといった日常的に利用するデバイスにSGを組み込むことで、あらかじめ許可したユーザーだけがデータを閲覧できるようになります。
住宅メーカーや電機メーカーとの連携では、SGを活用したスマートホームの実証実験が行われています。
ドアの施錠データや防犯カメラの映像を、自宅の所有者に紐づけた状態でブロックチェーン上に記録し、管理する方法を模索している段階です。
IoTセキュリティの課題とSGの役割
IoT機器は常時インターネットに接続しているため、ハッキングや乗っ取りのリスクと常に隣り合わせにあります。
とくにカメラやマイクが付いた家電はプライバシー侵害につながりやすく、これらをまとめて保護する技術が求められていました。
JasmyのSGは、ユーザーIDとデバイスIDを厳格に結びつけることで、外部からの不正な操作を難しくするアプローチをとっています。
この仕組みを採用すると、たとえば第三者が同じネットワークに侵入してきてもデバイスの操作を実行しにくくなります。
利用者は自分が所有するIoT端末の状態を一元的に把握し、必要に応じてアクセス権を変更できるため、セキュリティリスクを低減できる可能性があります。
Jasmy(ジャスミー)と競合プロジェクトの比較
IOTAとの比較
IOTAはIoT分野の草分け的な暗号資産で、ブロックチェーンとは異なるDAG(有向非巡回グラフ)を使ってトランザクションを処理しています。
マイクロペイメントや機械同士の自動決済を重視しており、汎用性の高さで注目されてきました。
一方、Jasmyは個人が自分のデータを管理する枠組みに力を入れており、同じIoT領域でも守備範囲がやや異なる印象です。
IOTAは独自ネットワークを運営しているのに対し、JasmyはEthereumエコシステムの上に築かれているため、他のDeFiやNFTなどと連携しやすい可能性があります。
IoTeXとの比較
IoTeXはIoT特化型のブロックチェーンを自前で立ち上げ、実際にUcamなどのIoT製品を世に送り出している点が目立ちます。
ハードウェアと独自チェーンを組み合わせることで、ユーザーがデータを暗号化して自分のカメラ映像を管理できる仕組みを実装済みです。
JasmyもIoTを扱いますが、ハードウェアの製造より企業連携やシステム構築がメイン領域といえます。
国内の大手電機メーカーやサービス企業と共同で実証実験を行い、早期に社会実装を狙う姿勢が特徴といえるでしょう。
Heliumなど他のIoT通貨との違い
HeliumはLoRaWANという低電力通信を活用し、ユーザーがホットスポットを設置することで暗号資産を獲得できる仕組みを提供しています。
これはIoTデバイスが全国各地で安定したネットワーク接続を手に入れるための分散型インフラといえます。
Jasmyは通信そのものを提供するわけではなく、IoT機器が生み出すデータの管理・取引をブロックチェーンでサポートする点で根本的に方向性が異なります。
通信領域の整備はHeliumのようなプロジェクトと連携し、データ管理部分で自社技術を生かすようなシナジーが考えられます。
Jasmy(ジャスミー)のチャート価格推移と要因
過去の価格変動とボラティリティ
JasmyCoin(JASMY)は2021年頃にBinanceやCoinbaseなど世界的に有名な取引所に上場し、急激に注目を浴びました。
当時は数倍〜数十倍にもなる乱高下があり、投資家の間で「値動きが激しいコイン」として取り沙汰されました。
しかし、その後の相場下落で大きく値を下げ、一時は上場当初の価格から比べると大幅に下落した時期もあります。
2022年〜2023年は仮想通貨全体が低迷傾向にあったため、JASMYも底値近くで推移していましたが、2024年以降は徐々に値を戻している傾向が報じられています。
こうしたボラティリティの大きさには、投機目的の資金が流入しやすいことや、企業提携ニュースなどの材料が出やすいといった要因があります。
価格を左右する主要ファクター
JASMYの価格に影響を与える主な要因としては、大手企業との提携アナウンスや技術開発の進捗が挙げられます。
たとえばパナソニックとの共同開発が具体的に進んだと報じられた時期には価格が大きく動きました。
その他、海外での規制ニュースや国内の税制変更によって暗号資産全体の相場が上下する際にも、JASMYの価格は連動する場合があります。
また、SNSや投資コミュニティでの評判が急速に広がり、一時的に価格が上昇するケースもあり得ます。
反面、過度な期待による急騰は、その後の急落リスクにつながるかもしれません。
とりわけ初心者にとっては、情報が交錯する場面で正しい見極めをするのが難しいと感じることもあるでしょう。
実際のチャートから見る価格予想
2023年末から2025年の春にかけて、JASMYは底値圏を脱した後に一定のレンジで上下動を続けながら、やや上向きのチャネルを形成している時期があったとされています。
企業提携やJANCTION関連のニュースが出るたびに上昇のきっかけが生まれていますが、暗号資産全体がリスクオフに傾いた局面では再び下振れすることが見受けられました。
実際のチャートは、以下のサイトで確認することができます。
- TradingView (JASMYUSDT): https://jp.tradingview.com/symbols/JASMYUSDT/
- CoinMarketCap (JasmyCoin): https://coinmarketcap.com/currencies/jasmycoin/
これらのチャートを見てみると、上場当初の高騰から大幅に下落した後、2024年以降に緩やかなリバウンドを試みているように見えます。
上昇トレンドを明確に形成しているわけではないものの、底値圏からやや高い水準にとどまっているのは、開発や協業の進展にともなう期待感があるとも推測できます。
一方で、チャート上では何度か直近高値を試して失敗した場面もあり、一定以上の価格帯では売り圧力が強いことが伺えます。
過去のデータからすると、企業ニュースなどのポジティブ材料が出た直後に一気に買いが入る傾向がある反面、利確や投機筋の動向が重なると短期間で価格が戻ってしまうケースも多いようです。
Jasmy(ジャスミー)の注目ニュース
独自Layer2「JANCTION」構想
2025年に入ってから、Jasmyは独自のレイヤー2ブロックチェーン「JANCTION」の開発を進めていると発表しました。
JANCTIONはEthereumをメインとしつつ、オフチェーンや他チェーンとの相互運用を視野に入れた設計が予定されています。
ChainlinkのCCIP(Cross-Chain Interoperability Protocol)を導入する構想も明らかになっており、今後はEthereum以外のプラットフォームからもJasmyCoinを使いやすくなる可能性があります。
レイヤー2を実装することで、ガス代や速度の問題を改善し、大量のIoTデバイスがスムーズにトランザクションを行える環境を目指している点がポイントです。
特にIoT領域ではリアルタイム性と手数料の安さが求められるため、この取り組みは今後の普及を左右する要素になるでしょう。
大手取引所での取扱いと市場流動性
2025年3月には、Jasmyがマーケットメイカー企業と提携して流動性を改善すると発表しました。
これにより、取引所での板が薄くなりすぎる状況を防ぎ、過度な価格乱高下を抑える狙いがあるとみられています。
一方でBinanceでは、取扱銘柄を定期的に見直す際にJASMYが「監視中」の対象になったという報道もあり、市場から注目が集まりました。
監視リスト入りは必ずしも上場廃止を意味するわけではありませんが、取引所としては流動性や開発状況などを総合的に評価していると考えられます。
Jasmy側はコミュニティと協力してプロジェクトの実績をアピールしており、上場維持に向けた動きが進行中です。
新たな提携・実証実験の進展
国内ではスマートホームやリモートワーク分野だけでなく、医療やスポーツ分野でもJasmyの技術を活用する取り組みが報じられています。
たとえばゲノム情報を分散管理し、研究機関に対して必要な範囲だけ提供する仕組みを試みるプロジェクトなどが一例です。
これは患者のデータに対して報酬が支払われる可能性を示唆するモデルで、ブロックチェーンを用いて精密医療を推進する取り組みとして注目を浴びています。
また、スポーツではプロ野球チームの入場管理システムにPDLの仕組みを組み合わせる実証が行われ、観客の個人情報や健康状態を安全に扱いつつデータを分析する試みに挑戦しているとされています。
こうした多様な領域への展開事例が増えるほど、Jasmyの知名度や評価が高まる可能性があります。
Jasmy(ジャスミー)の将来性と投資リスク
エコシステム拡大の可能性
Jasmyが扱う「データの民主化」は、Web3時代において注目度の高いテーマです。IoT機器が増えれば増えるほど、データ管理やプライバシー保護の重要性は高まります。
地方自治体やスマートシティなどの公共領域でも、個人情報の取り扱いには注意が求められるため、Jasmyの技術が採用される場面が今後広がるかもしれません。
企業とユーザー間の取引にとどまらず、医療分野や保険分野など、センシティブな情報を取り扱う産業でもJasmyの枠組みが使われる可能性が指摘されています。
成功すればエコシステム全体の成長が見込まれ、結果的にJASMYの需要が高まることにつながるかもしれません。
規制リスクと課題
一方で、暗号資産は国や地域によって規制が異なるため、国際的に事業を展開するJasmyにとっては難しい舵取りが求められます。
日本では比較的厳格な基準を満たしている一方、海外で新たな法改正が行われることでサービス内容を変更しなくてはいけないケースも考えられます。
また、IoT分野そのものが急速に進化しているため、後から登場する新しいプロジェクトがJasmyよりも優れたソリューションを提示する可能性も否定できません。
技術開発の遅れや企業との提携が思うように進まない場合、投資家の期待を集めにくくなることが懸念されます。
Jasmy(ジャスミー)とは?まとめ
Jasmyは日本企業が主導するIoT特化型のブロックチェーンプロジェクトであり、個人データの管理をユーザー側に取り戻すという明確なコンセプトを掲げています。
ソニー出身の経営陣や国内大手企業との実証実験が相次いで報道され、独自Layer2「JANCTION」の開発も進行していることから、今後の成長に期待をかける声は少なくありません。
ただし、暗号資産特有の大きな価格変動リスクや規制面のハードルも存在するため、投資を検討する際は注意が必要です。
IoTはこれからますます普及が見込まれる分野であり、そこで生まれるデータをいかに安全かつ効率的に扱うかは大きな課題です。
Jasmyが提示する「パーソナルデータロッカー(PDL)」や「セキュアナレッジコミュニケーター(SKC)」のモデルは、従来の中央集権的な管理方式を見直すきっかけにもなっています。
今後は海外企業との連携拡大や地域レベルでのスマートシティ導入など、さまざまなシナリオが考えられます。いずれにしても、投資判断には最新の動向とリスク評価が欠かせないでしょう。
気になる方は公式発表や信頼できるメディアからの情報を追いかけながら、自分のスタンスに合った方法で検討を進めてみてください。