
Hivemapperとは?運転で稼ぐ仕組みやHONEYトークンの将来性など解説!
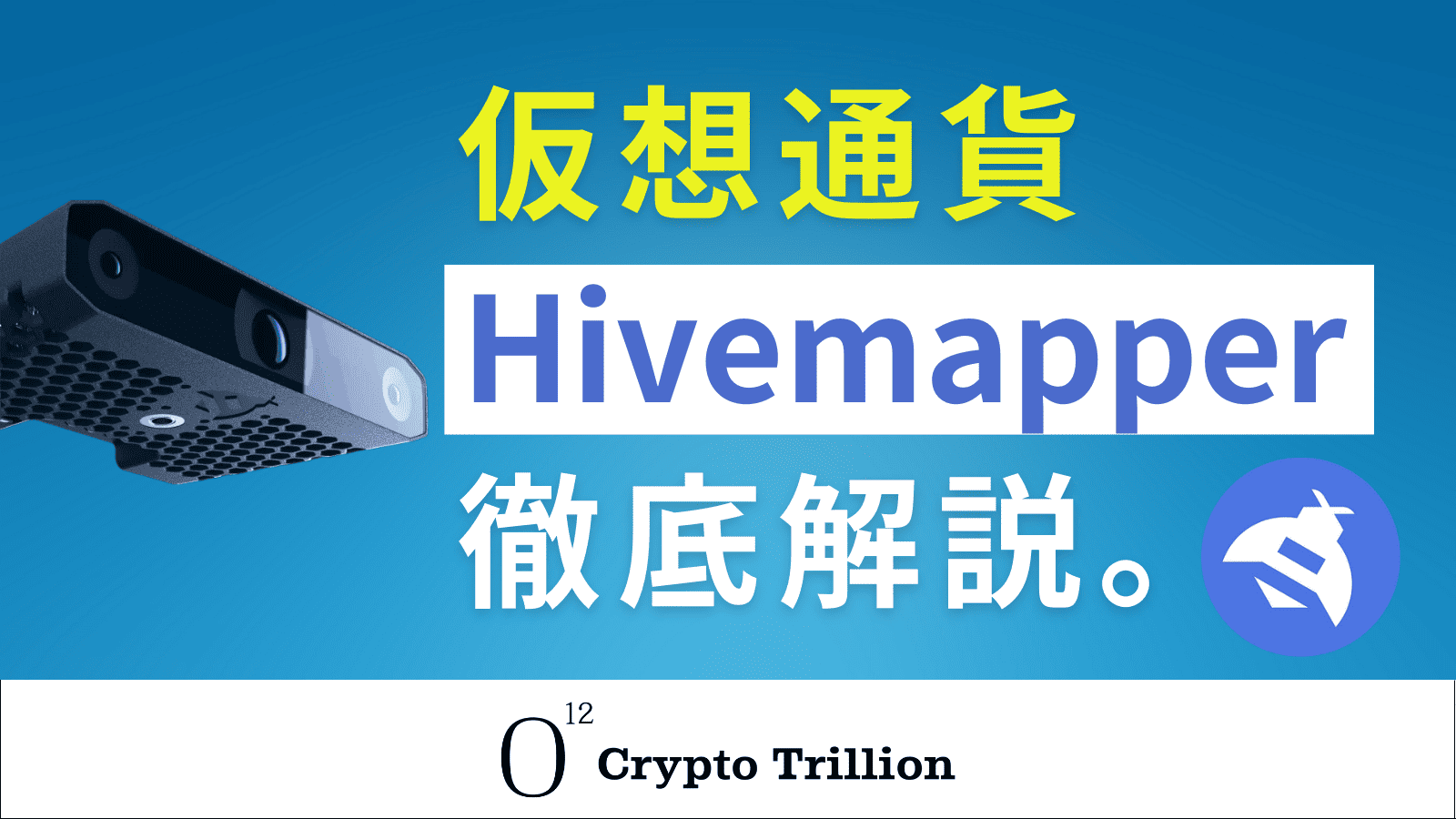
プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!
- 地図インフラをブロックチェーン技術で分散化することを目指して運営されているプロジェクト
- ドライバーが専用ダッシュカムを使って地図データを収集し、貢献度に応じて仮想通貨HONEYを得られる
- 世界中の参加者が走れば走るほど、リアルタイムに近い形で地図が更新されていく仕組み
- DePIN(分散型物理インフラネットワーク)ジャンルに位置付けられ、地図版のHeliumとも呼ばれる
- HONEYトークンはSolanaブロックチェーン上で発行され、最大供給量は約100億枚
- 分散型マッピングは専用ダッシュカムによる走行映像のアップロードとAI解析の組み合わせで成立する
- Drive to Earnという報酬スタイルにより、走れば走るほど地図のカバレッジと品質が高まります
- 地図データが作られるたびに新規発行が進む一方、サービス利用時のバーンによって循環量が調整される仕組み
- 市場需要が高まればトークン価格に上昇圧力が働く可能性がありますが、供給増とのバランスに注意が必要
- 大手地図サービス企業TomTomとの連携強化によりリアルタイム交通データの活用が進む可能性
 Trader Z
Trader Zこのように、「日常の移動」がトークンによって報酬化される構造は、非常に革新的です。
特に、配送業やライドシェア、物流など、日々車で移動することが多い方々にとって、今後非常に親和性の高いモデルとなり得るでしょう。



とはいえ、現時点では以下のような課題も存在します。
利用には専用のカメラ(Dashcam)の購入が必要であり、普及のためにはコスト面でのハードルがあります。
報酬となるHONEYトークンの価格に依存するため、市場価格の変動がユーザー獲得・維持に影響するリスクがあります。
しかし、このような課題を一つ一つクリアしていければ、Google Mapsのような従来の中央集権的地図サービスに取って代わる存在になる可能性もあるでしょう。


Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。


監修 Trader Z
ディーリングアドバイザー
世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。
2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。
Hivemapper(HONEY)とは?特徴と技術的背景
Hivemapper(HONEY)とは?
Hivemapper(ハイブマッパー)は、地図インフラをブロックチェーン技術で分散化することを目指して運営されているプロジェクトです。
専用のダッシュカメラを車に搭載し、移動時に映像を撮影しながら地図データをクラウドにアップロードすると、その貢献度合いに応じてHONEY(ハニー)というトークンを受け取ることができます。
世界中の参加者が走れば走るほど、リアルタイムに近い形で地図が更新されていく仕組みが最大の特徴です。
このプロジェクトは、既存の地図サービスが数年に一度しか更新されない課題を解決できる可能性があります。
Googleストリートビューや専門業者による調査だけに依存せず、日常の走行データをAI解析と組み合わせて高精度な地図を作り出そうとしている点が大きな強みです。
地図という巨大な市場領域に暗号通貨のインセンティブを導入するスタイルは、同じく分散型インフラを構築するHeliumと似たアプローチが見られます。
HONEYトークンはSolanaのブロックチェーン上で動作しており、トランザクションの高速性と手数料の安さがメリットとして挙げられます。
今後、多くの地図関連サービスや企業がHivemapperのネットワークを活用するようになれば、HONEYの実需が高まり、プロジェクトのさらなる発展が期待されます。
分散型マッピングのメカニズム
Hivemapperでは、リアルタイムに近い地図更新を実現するために、参加者それぞれがカメラを通じて映像を収集し、それをAIで解析するというプロセスを重視しています。
車に設置した「Hivemapperダッシュカム」がGPS情報と映像を連動させる仕組みになっているため、世界のどこで走っていても地理情報が自動的に送信され、道路や建物、標識などの詳細データに変換されます。
この映像解析には「Map AI」と呼ばれる独自のアルゴリズムが使われており、複数の参加者から寄せられる映像を照合しながら、地図の整合性や精度を高めていきます。
人が手動で行う作業を極力減らし、自動的に地図データがアップデートされる点が画期的です。
同時に、コミュニティメンバーが重要なランドマークや標識をタグ付けしたり、誤認識を修正したりする協働プロセスも実装されています。
このようにAI解析とコミュニティ参加によって、地図の精度は日々向上し続ける設計です。
走行データが多い場所ほど短いサイクルで更新が行われていくので、大都市の主要道路などは既存サービスと比べて圧倒的な更新頻度が期待されています。
一方、まだ参加者が少ない地域や国では、カバレッジを増やすことが課題となります。
そのため、初期段階のHivemapperでは未開拓エリアを走るドライバーに対して高い報酬を設定するなど、各種インセンティブ設計も取り入れられています。
Drive to Earn:走って稼ぐ仕組み
Hivemapperは、「Drive to Earn」という形で活動を促進しています。
これは、仮想通貨の分野で「○○ to Earn」というモデルが増える中、運転を伴うプロジェクトとして注目されるものです。
たとえば、歩くだけで仮想通貨を得られるMove to Earnや、無線通信のネットワーク構築を行うHeliumのように、現実世界の行動やインフラを必要とする仕組みと似ています。
実際に運転することにより新しい道路データを収集すれば、新規カバレッジ(未走破地域)に対して高めのHONEY報酬が発生します。
すでに登録された地域を走っても、道路の最新状況を更新できるため一定の報酬は用意されているようです。
こうした仕組みによって、参加者は普段の移動ついでにトークンを獲得しながらマッピングに協力できる点がメリットとされています。
また、専用ダッシュカメラの購入や設置が必要になるものの、車移動が頻繁な地域や職業ドライバーであれば比較的手軽に導入できる可能性があります。
日々の走行距離が長ければ、それだけ地図データ貢献が増し、報酬としてのHONEYを受け取る機会も広がる仕組みです。
ただし、燃料費や機器購入コストを上回る報酬が得られるかは地図需要や仮想通貨市場の動向に左右されるため、参加を検討する人にとってはリスクとリターンを慎重に検証する必要があるでしょう。
Hivemapper(HONEY)トークンの役割とトークンエコノミクス
HONEYトークン供給量と報酬設計
HONEYトークンは初期段階で最大供給量を定め、そこから地図構築の進捗に合わせて新規発行される設計が採用されています。
既存の暗号資産に多い一括発行とは異なり、走行データの収集によって少しずつ報酬が生まれるしくみが特徴的です。
ネットワークが拡大し、世界各地のマッピングが進めば進むほど、HONEYトークンの発行残高は増えていきます。
初期配分としては、コミュニティの報酬が最も多く設定されており、チームや投資家への割当も明確に公表されています。
一定のロックアップ期間や権利確定スケジュールが存在するため、投資家の大量売却が即座に行われにくい措置が敷かれています。
ただし、長期的に見ると徐々に市場への供給量が増えることになるため、需要側の伸び具合がトークン価格に与える影響は大きいと言えます。
マッピング報酬は地域やデータの質など複数の要因で変動します。たとえば、全く走行データのない地域で新しく映像を提供すると報酬が高くなる傾向があります。
既に走行された道路でも情報更新が進む場合は報酬が一定程度付与されるため、必ずしも新規エリアを狙わないと稼げないわけではありません。
こうした仕組みによって、都市部と地方の両方で地図の更新が進みやすくなる点が考慮されています。
Burn & Mintモデルの特徴
Hivemapperでは地図利用者がHONEYを支払うとき、トークンが焼却(バーン)される構造が導入されています。
地図のAPIを利用したい企業や開発者はHONEYを一定量消費することになり、利用量が増えれば増えるほどトークンの総供給量は減る方向に向かう可能性があります。
完全なバーンではなく、一部はコミュニティへの再分配に充てられるモデルが採用されており、焼却と同時に新規発行が行われる仕組みを「Burn & Mint」と呼ぶ場合があります。
実際には、焼却トークンのうち何割かが再び報酬として割り当てられるため、供給総量が一気に減るわけではありません。
地図の利用が拡大すればHONEYの消費も増え、トークン供給を抑制する効果が高まります。
逆にまだ商用利用が少ない時期や仮想通貨全体が下落傾向の場合は、発行量の増加が上回り、価格が弱含む可能性があります。
投資判断を行う際は、Burn & Mintがどの程度機能しているかと、実際にHivemapperが地図サービスとして定着しているかを見極める必要があります。
Hivemapper(HONEY)の投資判断ポイント
主要取引所と上場状況
HONEYトークンは、米国や欧州を中心とした海外取引所をメインに上場が進んでいます。
日本円で直接取引できる機会は限定的かもしれませんが、一部の取引所ではUSDTなどのステーブルコインを介して売買が可能です。
上場先が増えれば増えるほど流動性が高まり、価格形成が安定する見込みがあります。
ただし上場が進むにつれて、投資家やプロジェクト初期関係者のロックアップ解除が重なり、市場に大きな売りが出やすくなる時期も存在します。
いつ、どのような条件でロックが外れるのかを事前に理解しておくと、急激な価格変動に備えられるかもしれません。
さらに、取引所が増えれば利用者も多様化するため、流動性向上によるメリットがある一方で投機的な動きも強まりやすい点に留意が必要です。
注目すべきロードマップとパートナーシップ
Hivemapperは、今後数年間で地図カバレッジを世界規模に拡大し、企業や公共機関への地図データ提供を本格化させるロードマップを掲げています。
AI解析の精度向上やカメラデバイスの改良など、技術面での改善も継続的に進める方針です。
その一環として、大手地図企業や自動運転関連企業との提携が発表されることが増えてきました。
既にアメリカやヨーロッパを中心に地図APIの供給を行っており、その実用性が認められればHONEYの需要が飛躍的に拡大する可能性があります。
とりわけ自動運転など、車両の位置情報が極めて重要な分野でHivemapperのリアルタイム更新が有効に機能する場合は、業界からの期待が大きいでしょう。
投資家としては、これらの提携やロードマップ達成が実際にどこまで進んでいるかを見極めることが重要です。
仮に大手企業との協業が進めばHONEYの供給がバーンによって抑制され、価格が強含みになりやすいかもしれません。
逆に計画が思うように進まず、地図データの利用が増えない場合は、報酬としてのトークン発行だけが続いて供給過多になりやすい点に留意してください。
Hivemapper(HONEY)がここまで有名になった理由
既存マッピングサービスとの比較優位
Hivemapperは、世界の地図を数年置きに撮影車や航空写真で更新しているスタイルから一歩進み、ユーザーの日常走行によって地図をリアルタイムに近い形でアップデートする形態を打ち出しました。
GoogleストリートビューやAppleマップといった大手が頻繁に更新している印象を持たれていても、実際には地域によっては更新サイクルが長いケースが存在します。
一方、Hivemapperは誰かがその地域を車で通った瞬間に新たな映像を取得し、AI解析によってその場所の最新情報が地図に反映される可能性があります。
店舗の新規開店や道路工事といった変化が多いエリアで特に強みが出る設計です。
Googleやその他大手サービスとの直接的な比較が行われるようになり、分散型かつ短期周期の更新という点で話題を呼んでいます。
市場とコミュニティからの評価
Hivemapperが広く知られるようになった背景には、Heliumの創業者が参加している事実や、複数の有力ベンチャーキャピタル(VC)から資金を調達した実績が関係しています。
DePINという新しいインフラ構築の分野で先行していたHeliumが注目を集め、同様のモデルで地図分野を切り開くHivemapperも自然と注目度が高まりました。
コミュニティ面では、SNSなどを通じて実際のユーザーが走行データをアップロードしながら「こんなところも地図化できる」という事例を共有する動きが活発です。
大手取引所への上場や企業連携のアナウンスがあると価格が反応しやすい傾向も見られます。
まだ発展途上のプロジェクトですが、地図という巨大産業を分散型で切り拓こうとしている点で、特に開発者や未来志向の投資家から期待されています。
Hivemapper(HONEY)注目ニュース&今後の展望
TomTom社との連携強化
2025年に入り、Hivemapperは欧州を拠点とする大手地図サービス企業TomTom社との連携強化を発表しました。TomTomはカーナビゲーションや交通情報の分野で世界規模のシェアを誇ります。
両社の提携によって、Hivemapperが収集する道路映像や標識データがTomTomのリアルタイム交通情報と統合される試みが進められているようです。
これが実用化されると、従来よりも細分化された道路状況や地域の変化を反映できる可能性があります。
公表されている情報によると、TomTom社内でもHivemapperの走行データを研究し、自社製品への統合を検討している段階とされています。
地図APIの利用料がHONEYで支払われるケースが増えれば、トークンの需要とバーンが加速することが期待されていますが、まだ具体的なスケジュールは流動的です。
AI搭載ダッシュカムの新リリース
2025年4月時点で「Beekeeper」という新たなAI搭載ダッシュカムがリリースされました。
従来モデルより撮影品質が大幅に向上し、車線変更や標識の読み取りなど、より詳細なデータが自動で解析される機能が組み込まれています。
企業向けには車両管理や運行最適化のサービスとしての展開も視野に入れられているため、単に仮想通貨報酬を得るだけでなく、業務効率化ツールとしての利用場面も拡大しています。
すでに北米の一部運送企業がテスト導入を開始し、車両の走行ルートを最適化したり、安全運転支援に活用したりする動きが報告されています。
こうした実需要の拡大は、HONEYトークンへの好影響をもたらす可能性がありますが、まだ導入企業の数が限られている段階です。
今後の拡販状況によっては、ドライバー以外の法人ユーザーがHivemapperに参加するきっかけにもなり得ます。
Hivemapper(HONEY)とは?まとめ
Hivemapper(HONEY)は、分散型マッピングという新しいアプローチで地図インフラの変革を目指しています。
結論としては、走行データを提供すればトークン報酬を得られる仕組みが実用段階に入り、実際に使われ始めている点が他の暗号資産にはない強みになっています。
2025年時点でTomTomなどの大手企業との連携が進んでおり、AI搭載ダッシュカムのリリースも新しい需要の創出に寄与するかもしれません。
HONEYの価格は供給増とBurn & Mintによるバーン量、そして地図サービスの需要拡大のバランスに左右されます。地図業界は非常に大きな市場規模を持つため、今後のロードマップ実現次第で大きく成長する可能性があると考えられます。
ただし、仮想通貨市況全体の影響を受けることや、プロジェクトの実用化が想定どおり進まないリスクは無視できません。
Hivemapperの運営方針や開発進捗をチェックし、実際にどれだけ企業利用が拡大しているのかを確認することが大切です。
運転をしながらトークンを得られる点は魅力的ですが、期待だけで飛びつくのではなく、コストや地域特性を見極める必要があるでしょう。
分散型地図というコンセプトが今後の社会で受け入れられるかどうかは不透明な部分もあるため、興味を持った場合は公式情報やコミュニティを定期的に確認しながら判断することをおすすめします。

