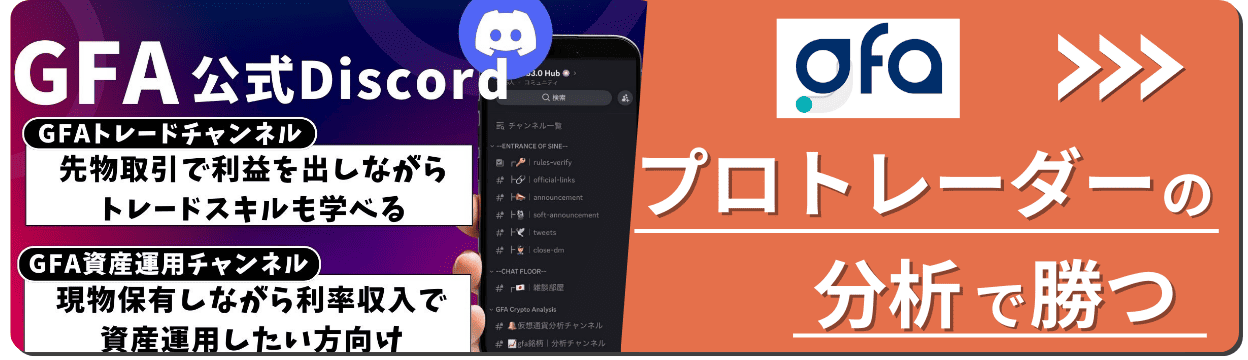イーサリアムR1が登場、ネイティブトークンなしの中立的L2スケーリングソリューション

イーサリアム・エコシステムの一部開発者グループが、新たなレイヤー2スケーリングソリューション「Ethereum R1」を発表した。特徴的なのは、R1にはネイティブトークンが存在せず、資金調達も全て寄付によって賄われているという点である。開発はイーサリアム財団とは無関係に行われている。
5月1日にXで投稿された声明によれば、Ethereum R1は「中央集権的な依存関係やリスクの高いガバナンスから解放された、中立性と検閲耐性を重視したロールアップ」であるという。チームはさらに「多くのL2は、もはやイーサリアムのスケーリング解決策ではなく、独立した新たなL1のように振る舞っている」とし、既存L2の私的割当や不透明なガバナンス構造に懸念を示した。
イーサリアムのL2拡張戦略に潜むジレンマ
Ethereum R1の発表は、現在のL2中心のスケーリング戦略に対して懐疑的な見方を投げかけるものとなっている。2024年3月に実施された「Dencun」アップグレードにより、イーサリアムL2ネットワークの手数料は大幅に低下し、同年9月にはイーサリアム本体の収益が99%減少した。
その結果、2025年4月の時点でイーサリアムL1の平均取引手数料は約0.16ドルとなり、5年ぶりの低水準を記録している。この手数料の低下は、L1におけるブロックスペースの需要減少を意味しており、ネットワーク維持の観点から課題視する声も上がっている。
L2拡大は価値か、それとも搾取か
このような状況に対し、一部では「L2の成長がL1の収益性を損なっている」との批判も存在する。つまり、スケーリングの名目でL2が拡大しすぎると、結果的にイーサリアムL1の健全性を脅かすという見方である。
一方、L2の多様性を肯定する声もある。ブロックチェーン抽象化ソリューション「Avail」の共同創業者Anurag Arjun氏は、「イーサリアムは単一チェーンではなく、用途に応じた選択肢を持つマルチチェーン構造を提供している点に価値がある」と述べており、L2拡大は機能ではなく「バグ」だという指摘には異を唱えている。
今後の展望とEthereum R1の意義
Ethereum R1の登場は、あくまで中立性と分散性を重視したスケーリング手法への回帰を目指す動きとして評価できる。ガバナンストークンやトークン報酬といった経済的インセンティブが絡まないことで、長期的には本質的なイーサリアムの価値観(オープン性・分散性)を体現するレイヤー2として存在感を高める可能性もある。
トークンレスで透明性のあるスケーリング解決策が、今後どのようにL2市場で受け入れられるかが注目される。R1は、商業的成功を狙う既存L2とは一線を画す「中立的L2」として、ユーザーからの支持を得られるかどうかが鍵となるだろう。
GENAIの見解
 GENAI
GENAI注目すべき点は、トークンを一切発行しないという姿勢です。これは、資本市場や投機的インセンティブに依存せず、純粋にネットワーク中立性と分散性を追求する姿勢を明確に示しています。
昨今のレイヤー2プロジェクトは、投資家向けのプレセールやガバナンストークンを伴う設計が一般的となっており、その構造がしばしば中央集権的になっているのが実情です。Ethereum R1は、こうした流れに対する「倫理的カウンター提案」とも言えるものであり、Ethereumの創設理念に立ち返るものとして高く評価されるべきだと思います。
また、L1の手数料収入が激減している中で、L2の拡大がL1の持続可能性に悪影響を与えるのではないかという議論もあります。そうした背景のなかで、Ethereum R1がL1と価値観を共有しながらもスケーラビリティを提供しようとしている点は、今後のL2設計の方向性に一石を投じる可能性があると見ています。
このような「ノンプロフィット」「ノントークン」「非中央集権」なL2モデルが市場でどれほど受け入れられるのかは未知数ですが、エコシステムの健全性や選択肢の多様化という観点から見れば、非常に意義ある取り組みであると感じています。