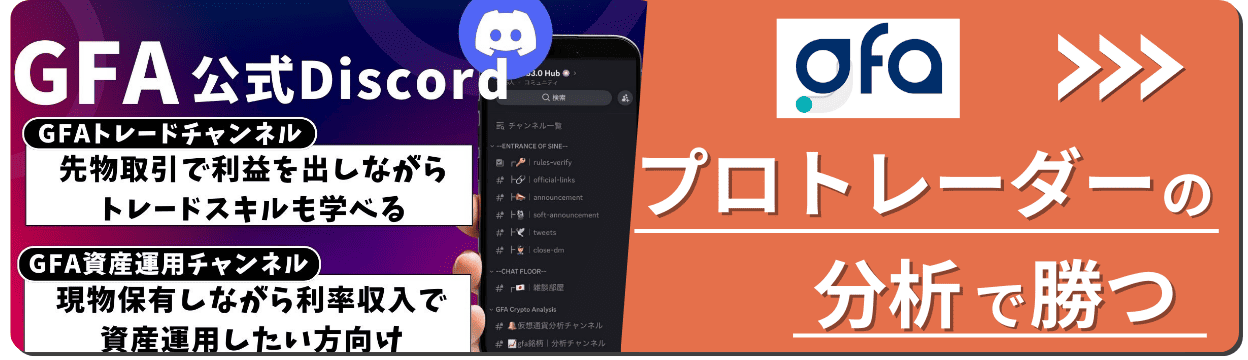ビットコイン購入がアジア企業で加速|世界中に広がりつつある『マイクロストラテジーモデル』とは?

ビットコイン(BTC)を企業の資産戦略に取り入れる動きが、アジアでも本格化している。日本のメタプラネット(Metaplanet)および香港のHK Asia Holdingsが、積極的なビットコイン購入を進めていることが明らかとなった。
メタプラネット、5,000BTCに到達 目標の半分に
東京証券取引所に上場するメタプラネットは、4月24日に145BTC(約19.2億円)を追加購入したと発表。これにより、保有総量は5,000BTCとなり、2025年末までに1万BTC保有を目指す「ビットコイン戦略」の50%を達成した。
同社は社債発行やオプション取引(キャッシュ担保型BTCプット売り)などを活用し、調達資金をもとに継続的なビットコイン購入を進めている。また、2026年末までには21,000BTCの保有を目指す長期戦略も打ち出しており、マイケル・セイラー氏率いる米マイクロストラテジーの手法を参考にしているとされる。
なお、この戦略が注目を集める中、メタプラネットの株価は2024年以降で3,000%以上の上昇を記録している。
HK Asia Holdings、約8,350万ドルの資金調達を発表
香港の上場企業HK Asia Holdingsも、約8,350万ドルの資金調達計画を発表した。4月23日の発表によると、株式と転換社債を通じて調達される予定で、新株発行は発行済株式の0.82%相当にあたる。
今回の調達目的についてビットコイン購入とは明言されていないものの、2月に初のビットコイン購入を行い、その直後に株価が倍増した経緯から、市場では**「さらなるビットコイン購入のための資金調達ではないか」との憶測**が広がっている。
実際、HK Asiaは2月16日に初のビットコイン取得を行った後、2月20日にはさらに7.88BTCを追加購入しており、平均取得価格は97,021ドルである。
4月24日時点の同社株価は、香港市場で前日比約5.4%上昇している(Google Finance調べ)。
セイラー氏のマイクロストラテジーがモデルに
これらアジア企業の動きは、マイクロストラテジー(現:Strategy)による先進事例に倣ったものとみられる。マイクロストラテジーは、転換社債やATM増資を活用してビットコインを積極的に買い増し、現在は538,200BTC(約8兆円相当)を保有する世界最大の上場ビットコイン保有企業となっている。
同社は2月にも20億ドルの転換社債発行を発表しており、その戦略は今なお継続中である。
マイクロストラテジーモデルとは何か?
マイクロストラテジー(現・Strategy)は、かつて企業向けのBI(ビジネスインテリジェンス)ソフトウェアを主力とするナスダック上場企業であったが、2020年8月より企業戦略を大きく転換し、ビットコイン(BTC)を中核資産とする「ビットコイン準備金モデル」を採用した。
この戦略は世界中の企業に影響を与え、「マイクロストラテジーモデル」として知られるようになった。
戦略の3つの柱
1. キャッシュ資産のビットコイン化
マイクロストラテジーは、最初に保有していた約2億5,000万ドルのキャッシュで21,454BTCを購入。その後も継続的に買い増しを行い、2025年4月現在で53万BTC以上を保有するまでに至っている。これは企業として世界最大のビットコイン保有量である。
2. 転換社債・ATM増資を活用した調達戦略
同社は、単なる自己資金による購入にとどまらず、転換社債(Convertible Notes)やATM(At-the-Market)株式増資などの資本市場手法を用いて、資金調達を継続している。たとえば、2024年には0%金利の社債で20億ドルを調達した。低金利かつ株主希薄化リスクを抑えた調達方法により、ビットコイン購入を加速している点が特徴的である。
3. HODL(長期保有)戦略の徹底
マイクロストラテジーは、購入したビットコインを一切売却せず保有し続ける方針(いわゆるHODL)を貫いている。これにより、同社の株式は「間接的なビットコインETF」のような位置づけとなり、株価上昇と市場からの注目を同時に獲得している。
なぜこの戦略が注目されるのか?
- インフレヘッジとしての非インフレ資産であるビットコインの優位性を最大限に活かしている。
- 財務レバレッジを用いてビットコインに集中投資することで、株主に対して超過リターンをもたらす可能性がある。
- ビットコイン価格の上昇により、保有資産価値と株価が連動して上昇しやすくなる。
- 同社株式が「BTC保有企業」としてETF代替となり、投資家にとって魅力的な上場ビットコイン投資手段になっている。
マイクロストラテジーモデルは世界中に広がりつつある
マイクロストラテジーモデルはもはやアメリカやアジアに限定された現象ではなく、グローバルな金融戦略の一選択肢として認知され始めている。
この動きは、今後ビットコインの需給構造や価格、さらにはマクロ経済にも影響を与える可能性がある長期的トレンドであると言える。
GENAIの見解
 GENAI
GENAI日本のメタプラネットや香港のHK Asia Holdingsが先導する今回の動きは、ビットコインを企業の財務戦略の中核に据える“マイクロストラテジーモデル”のアジアへの本格的な波及を象徴する重要な転換点であると見ています。
特に注目すべきは、メタプラネットが社債やオプション戦略を用いて段階的にBTCを積み増している点です。これは、単に余剰資金をビットコインに替えるという短期的な判断ではなく、金融的な仕組みを活用してビットコインへの長期的な資本配分を行う、極めて高度な資産運用戦略であると評価できます。
また、HK Asia Holdingsのように、まだ保有量は小規模でも市場からの反応が極めてポジティブであることは、「ビットコイン=企業価値の成長エンジン」として投資家が認識し始めている兆候です。これは、ビットコイン保有が“株価のてこ”としても機能することを示しており、他の上場企業にも強いインセンティブとなるでしょう。
この動きは、アジア圏の企業だけでなく、新興国のインフレ耐性を求める企業や、通貨不安のある地域においても有効な事例となり得ます。中長期的には、これが「法人によるビットコイン需要の新しい柱」となり、マイニング報酬の半減やETFによる需要と並ぶ三本目の支柱になる可能性があります。
結論として、今回のニュースは単なる企業による買い増しではなく、アジアにおける“ビットコイントレジャリースタンダード”の到来を予感させるエポックメイキングな動きであると考えております。今後もこの潮流が拡大するか、継続的に注視する必要があります。