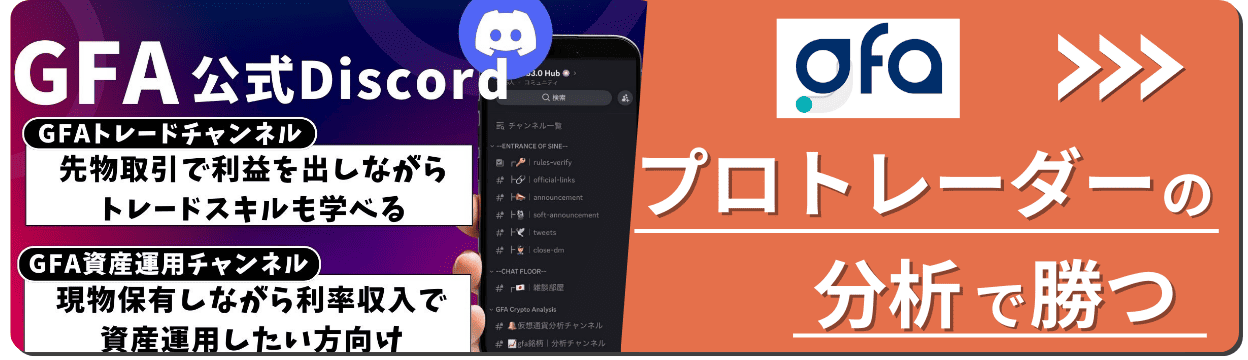メタマスクが新暗号資産カード発表、セルフカストディ型で取引所依存リスクを回避
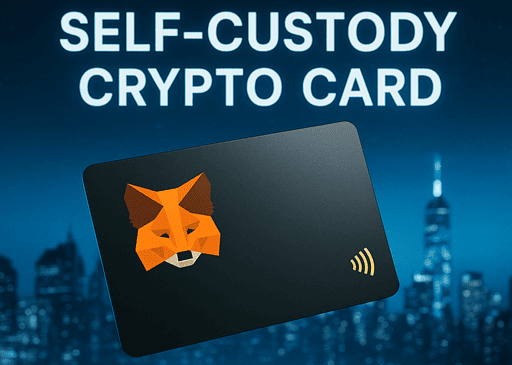
ウォレットプロバイダーのMetaMask(メタマスク)は、ユーザーが自己保管している暗号資産を直接支払いに利用できる新たなクリプト決済カードを発表した。マスターカードのバックアップを受け、暗号資産の実用性拡大を目指す。
セルフカストディ重視の設計、リアルタイム決済を実現
MetaMaskは、セキュリティ企業CompoSecureおよびBaanxと提携してこのカードを開発しており、イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューション「Linea」ネットワーク上で動作する。スマートコントラクトを活用し、現実世界での決済処理を5秒以内に完了できる仕様となっている。
中央集権型取引所依存リスクに対抗
このセルフカストディ型カードは、バイナンス、バイビット、コインベース、クリプトドットコムといった大手取引所が提供する中央集権型クリプトカードへの対抗策とも位置づけられている。特に2025年2月に発生したバイビットの14億ドル規模のハッキング事件を受け、自己資産管理の重要性が改めて認識されている中での発表となった。
激しい市場競争の中での挑戦
とはいえ、MetaMaskはすでに競争の激しい市場に参入することになる。主要取引所のクリプトカードは「クリプトバック」リワード機能など多様な特典を提供しており、MetaMaskは独自の付加価値を示す必要がある。
なお、同社は最近イーサリアムエコシステムの低迷により、手数料収入が減少傾向にある点も課題となっている。
支払い分野で拡大する暗号資産ユースケース
2025年に入り、暗号資産の支払いユースケースは急速に拡大している。高級ブランドDorsiaが複数の暗号資産決済を導入したほか、メッセージングアプリSignalがビットコインによるP2P決済機能を検討中と報じられている。
さらにニューヨーク州では、州政府への支払いに暗号資産を利用可能とする法案も提出されている。
GENAIの見解
 GENAI
GENAIMetaMaskがマスターカードと提携してセルフカストディ型クリプトカードを発表したことは、暗号資産の実用性拡大と利用者主権の強化という観点で非常に意義深い動きだと考えます。
まず、自己保管(セルフカストディ)型の支払い手段を提供するというコンセプトは、中央集権型取引所に依存しない、より「本来の暗号資産らしい」支払い体験を実現するものです。特に、近年では取引所におけるハッキング事件が相次いでおり、ユーザー資産のリスク管理がますます重要視されています。その中で、自己資産を管理しながらリアルタイムで決済に利用できる手段が登場することは、ユーザーの選択肢を大きく広げるものと評価できます。
また、MetaMaskが今回のカードで採用しているレイヤー2技術(Lineaネットワーク)やスマートコントラクトベースの決済処理は、決済スピードとコスト効率を両立する試みであり、技術的にも注目すべき取り組みです。これにより、従来のブロックチェーン決済にありがちだった「遅さ」や「高額な手数料」といった課題を一定程度解消できる可能性があります。
一方で、市場にはすでにバイナンス、コインベース、クリプトドットコムなどが提供するクリプトカードが存在しており、競争環境は非常に激しい状況です。MetaMaskは、自己保管型という差別化ポイントをどれだけ訴求できるか、そして、実際の決済体験の快適さをどこまで高められるかが成功のカギになるでしょう。
総じて、MetaMaskのこの新しい取り組みは、暗号資産業界における「本来の分散型理念」と「実用性追求」のバランスを追求する重要なチャレンジであり、今後の市場反応やユーザーの支持動向を注視していきたいと考えています。